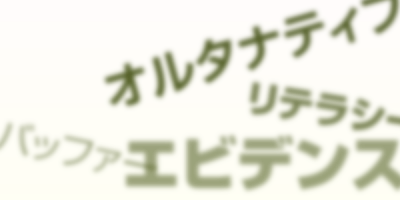『ダンス・ウィズ・ウルブズ』と『アバター』において観客の解釈や心情がどのように誘導されるかについて考えています。その一環として前回は,『ダンス・ウィズ・ウルブズ』がインディアンをどのようにとらえているかを確認しました。そして,今回は白人がどのように描かれているかを取り上げます。
『ダンス・ウィズ・ウルブズ』の白人はまず,強欲な存在として描かれます。彼らはインディアンの土地を侵します。そして,毛皮と舌の肉を取るためだけにバッファローを殺します。白人のハンターが通った跡には,おびただしい数の,皮を剥がれたバッファローの死体が横たわっています。
これはスー族にとって悲しくも残酷な光景です。スー族もバッファローを狩りますが,彼らは狩りの前に祈りを捧げ,感謝しつつバッファローのすべてを消費します。スー族にとってバッファローは,生活の糧であるとともに,大地と自分たちをつなぐ存在であるかのようです。ところが,白人は金のために容赦のない殺戮を行うのです。
この映画の白人はまた,無慈悲な利己的存在でもあります。ダンバー中尉がスー族の服装で前哨地に戻ると,そこに到達していた騎兵隊(白人のみで構成)はためらいもなく彼に対し発砲し,彼の馬を射殺してしまいます。この馬は,ダンバーにとって共に戦場を駆け抜けた戦友でもあります。シスコ (Cisco) という名前があります。撃たれた馬の苦しそうな表情がアップになります。主人公の悲しみと怒りがスクリーン一面に広がります。
また,この映画にはスパイヴィーというそれはそれは賎しい兵卒が登場します。彼はダンバーがすべての記録を綴った日誌を盗み出します。その日記帳にはダンバーが騎兵隊員であることを証明する命令書も綴じられています。ですが,そのことを知りながらも,スパイヴィーは平気で嘘をついて日誌を隠してしまうのです。
そして,極めつけは狼殺しです。ダンバーは前哨地にひとりで滞在するあいだに,野生の狼を手なずけてしまいます。彼と狼がじゃれ合うところを見て,スー族の人たちは彼を「狼と踊る男」(Dances with Wolves) と名づけます。映画のタイトルにかかわる大事な狼です。狼は鎖に繋がれ護送されるダンバーのことを心配そうに遠目に見守ります。その狼を,騎兵隊員たちは単なる余興で争うように撃ち殺してしまいます。

野生の狼とはいえ,人になついたらそれは犬と同じです。ツー・ソックス (Two Socks) という名前もつけられています。そして,犬殺しはハリウッド映画のタブーだったはずです(第50回を参照)。これで馬と犬という,アメリカ人にとって思い入れの強い動物が相次いで殺されたことになります。(ちなみに,狼のツー・ソックスも馬のシスコもエンドロールにキャストとして名前が挙がっています。この2頭はそれほどの存在感があるわけです。それから,カットの写真は眠っている狼を撮ったものだそうです。ご安心を。)
白人はまた,無知な存在でもあります。彼らは,インディアンを人として理解しようとしません。また,先ほどのスパイヴィーなどは,ダンバーの日誌をくすねますが,彼は字が読めません。彼には,用を足した後の紙としてしかこの日誌の価値はないのです。
このように,『ダンス・ウィズ・ウルブズ』では,愚かで身勝手な白人の姿が執拗に描写されます。
なぜ,これほどまで徹底して白人側の醜さを強調したのでしょうか。
それは,それまでのハリウッド映画(西部劇)の伝統に逆らって,インディアンの側に観客を連れて行くためです。騎兵隊を皆殺しにするインディアンは,それまでのステレオタイプに従えば,(敵対的なエイリアンと同様,)せん滅されるべき存在となるはずです。
実際,観客の(そして映画会社や出版社の)心をインディアンの側に引きつけるのは,簡単ではなかったようです。脚本のマイケル・ブレイク (Michael Blake) は,『ダンス・ウィズ・ウルブズ』のシナリオを依頼されることなく自主的に書いたのですが,シナリオは売れないままでした。そこで,彼は小説としてこの話を書き直します。しかし,白人を批判する内容があだとなり,小説の原稿も出版のめどがなかなか立たなかったそうです。
そのような経緯を経て映画化されたこの作品は,スー族の誠実で暖かみのある姿を丹念に伝え,白人の強欲で醜いありさまを執拗に描きます。スー族と主人公は,容赦のない白人たちに追い込まれてやむなく立ち上がった,そう解釈させるためです。観客の受け取り方を用意周到に誘導し,映画に説得力を持たせるためです。西部劇に根強く残るステレオタイプを乗り越えるには,このような物語の展開が必要だったのです。