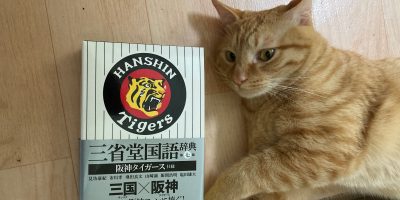太宰の最晩年のエッセイに、『如是我聞』という作品がある。
太宰が最も嫌悪した、“既成の権威”なるもの。『如是我聞』には、死を決意した彼が、この“既成の権威”に対して抱いたどうにも収まりようのない反抗心が、なりふり構わずにつづられている。太宰のエッセイとしては最もよく知られたものであり、いい意味でも悪い意味でも、太宰文学を代表する作品ともいえるだろう。
しかも、タイトルそのものが四字熟語であるとくれば、『太宰治の四字熟語辞典』としては、取り上げぬわけにはいくまい。
しかし、構想を練り始めたかなり初期の段階で、この「辞典」の最後は、『人間失格』のタイトルそのものを“四字熟語”として取り上げようと決めていた。そのために作品の年代順に構成するとなると、『如是我聞』は『人間失格』の直前に来る。タイトル=四字熟語というタイプのものが続くのは、構成上、あまりおもしろくない。
ならば、『如是我聞』の本文中から、なにかを別のものを探すしかない。そう思って再読した結果、ひっかかったのは「三拝九拝」という四字熟語だった。
*
『如是我聞』の中に、この四字熟語は2回、使われている。いずれも、“既成の権威”にこびへつらう評論家たちを、罵倒する文脈だ。1度目は、「レッテルつきの文豪の仕事ならば、文句もなく三拝九拝し、大いに宣伝これ努めてい」ると評論家たちを批判する。2度目は、「ある老大家の作品に三拝九拝し」ている評論家について、「奴隷根性も極まっていると思う」と容赦ない。
太宰は天才なのだから、評論家たちのことなど気にせずに、ゆったりと構えていればいいのに。そんなふうに、思わないでもない。しかし、それはともかく、「三拝九拝」は何度もおじぎをすることであり、それが「三」「九」という具体的な数字で表されているところに特徴がある。3度ならともかく、実際に9度もおじぎするヤツは、そうはいまい。太宰のいつもの誇張表現である。
しかし、『如是我聞』では、その大げさな感じがユーモラスな方向ではなく、どこかトゲトゲしい方向に進んでいるように、ぼくには感じられる。このエッセイを「胸のすくような名文」と呼ぶ人もいるが、ぼくはどうも好きになれない。もっとも、そのやぶれかぶれ具合にこそ、太宰の苦悩を見るべきなのだろうけれど……。
*
この四字熟語について語るとすれば、とりあえずは語源を確認しておかねばならない。辞書類には確とした語源説は載っていないが、「三跪九拝」と関係がありそうだ。
「三跪九拝」というのは、中国清朝の皇帝に対する礼「三跪九叩頭」のことだ。ひざまずいて、3回、額を地面に付ける。それを、3度くり返す。かつては、中華帝国の皇帝の前に出れば、だれであっても、この七面倒くさい礼法を守らねばならなかった。それをめぐって、イギリスのマカートニーや、日本の副島種臣といった“近代国家”の外交官たちがいろいろと苦労したのは、有名な話だ。
つまり、「三拝九拝」は、歴史的事実なのだ。そこには、中華帝国の偉大さと、時代の流れに対応できぬ苦しみとが潜んでいる。それは、誇張などではないのだ。
そのことに思い至ったとき、さすがの太宰の誇張表現も、急速に色褪せていくように感じられた。そうして、ぼくは『如是我聞』を取り上げることを、すっかり諦めてしまったのだった。