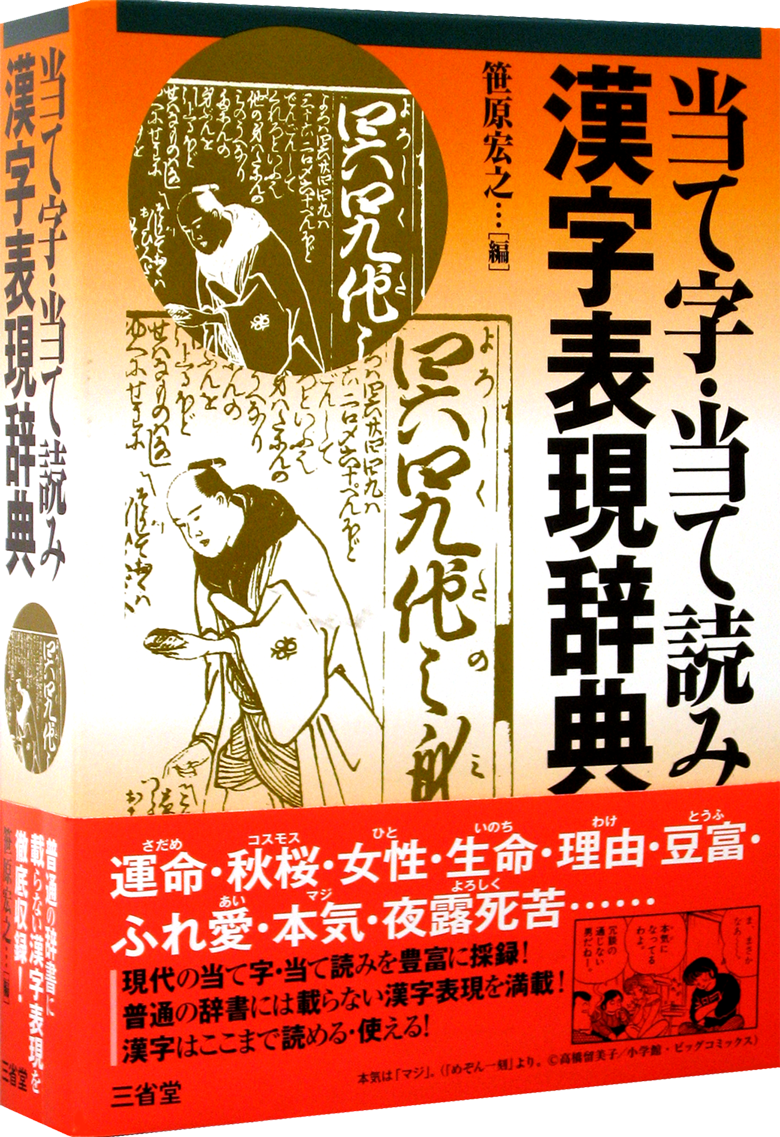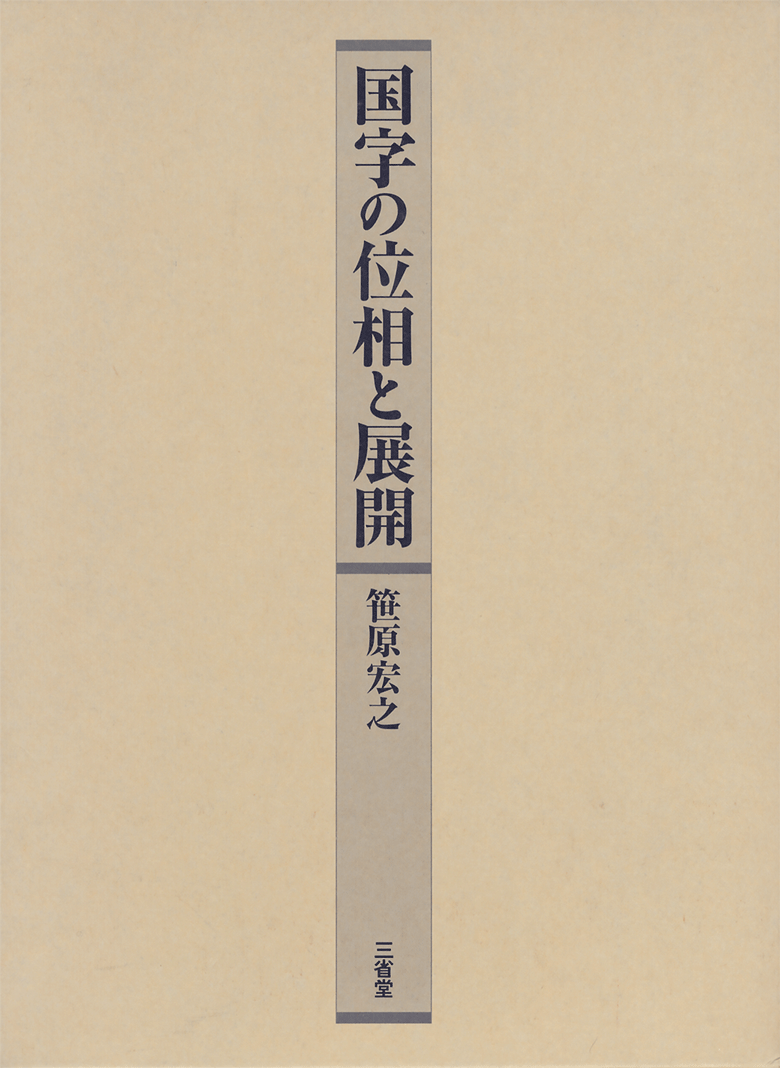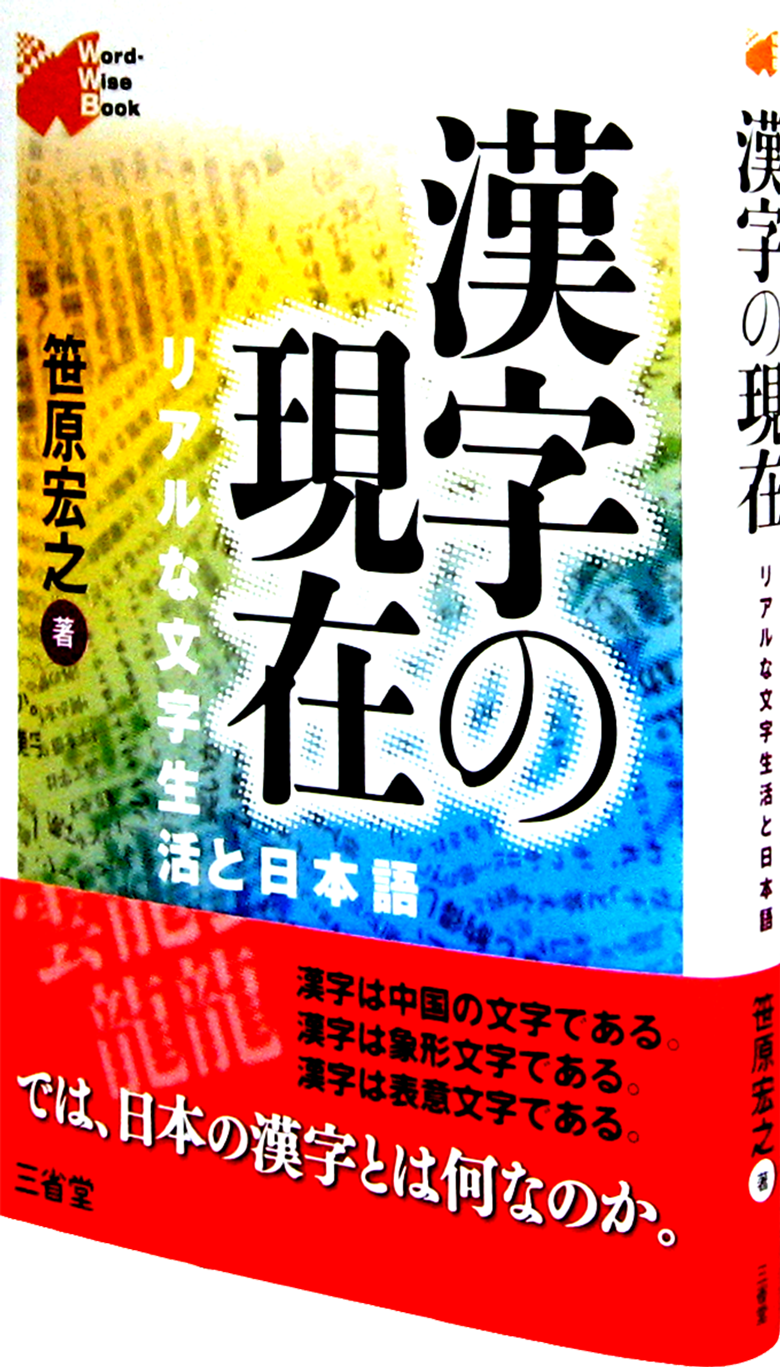「まじめ」という語は、「正(まさ)しき目」ないし「真し目」、あるいは「真筋目」からできたものだ、とする語源説がある。「まじまじと見る」の「まじまじ」は真顔の意もあり、関係があるとされることもある。
江戸時代に、真剣さ、本気さ、そしてそうした状態を感じさせる顔つきや態度という意味をもつ口頭語として現れた語であるようで、『日本国語大辞典』第2版などによると、370年ほど昔の文献に登場する。「まじめなるかほ」と、仮名草子『仁勢物語』下(早稲田大学蔵)に用いられている。
江戸時代のうちに、漢字による「真面目」という表記が現れる。たとえば、「真面目(まじめ 振り仮名)くさつて」と、松亭金水(1795-1862年)の人情本『秋色絞朝顔』初編下第六回(早稲田大学蔵)にあるように使われていく。
この漢字3字による表記は、中国では蘇軾も用いているが、それは実相を意味する漢語としての「真面目」(シンメンボク・シンメンモク)であった。この漢語の文字列を、語義の差を超えて「まじめ」の表記に利用したものであろう。「真面目(まじめ)」という普通とも思われている表記を『当て字・当て読み 漢字表現辞典』に取り上げたのは、そういう不整合をふまえてのことである。江戸時代の後期には、この音読みの語が「まじめ」という意味でも使われるようにさえなり、「まじめ」と「真面目」はより一体化した。
ほかにも表記は試みられた。「天秤真地目」(てんびんのまじめ)という狂歌師がいたようであるし、ほかに、元禄には「目静」と書かれることもあった(『反故集』)。『倭訓栞』後編には「交睫を読めり まじ\/も同じ」ともある。「交睫」(こうしょう)は漢語では睫(まつげ)を合わせる、つまり眠ることであるが、交えると目という構成としたのであろうか。ともあれ、「目」という点で、「まじまじ」という語とのかかわりがここにも現れている。滑稽本には「老実」という熟字訓も記されている。
「まじめ」という語は、人々に使われていく中で次第に多義性を帯びていき、明治に入る頃には、誠実である、誠意がある、という派生した意味でもよく使われるようになる。
明治期以降には、「真面目」が勢力を得る。坪内逍遥、二葉亭四迷、尾崎紅葉、樋口一葉、そして夏目漱石、志賀直哉などの作にも見られる。明治時代には、漢字で、あるいは熟語で何とか意味を表そうとすることが増え、
「正首」 「老実」 「篤実」 「質朴」
「尋常」 「真実」 「真摯」 「樸実」
などといった熟字訓も使用されている。ここには明治期の新作と思しきものが多数見受けられる。
なお、「真面目」と書いて「まこと」とも読ませ、また、「老実」「忠実」と書いて「まめ」とも読ませる例もあり、それら相互に関連が読み取れよう(後者の「まめ」には「豆」も当てられることがある)。
そして、明治期には「真地目」という、発音に合わせて真ん中の1字を取り換えたような表記もときとして行われた。
国語辞書も対応を始める。ヘボンは『和英語林集成』において「馬自物」という珍しい表記を示す(1867初版(明治大学図書館蔵p253)、1872再版(国会図書館蔵p295)。『日本国語大辞典』第2版では「馬出物」とする)。この和英・英和辞書には珍しい表記が散在していたのだが、第3版ではこの「馬自物」という漢字表記も消えている。
大槻文彦は、国語辞書『言海』(1889)において、「まじめ」の項目に「真面目」という漢字表記を掲げた。山田美妙『日本大辞書』(1893)もまた「まじめ」に「真面目」を掲げている。19世紀末には、数ある「まじめ」の漢字表記の中から、「真面目」が人口に膾炙していたようで、広く使われるようになっていった。「まじめ」というかっちりとした意味をもつ語には、きちんとした佇まいをもつと感じられる漢字こそがふさわしいと多くの人々に意識された結果なのではなかろうか。
しかし、この「真面目」は、多難な時代の中で翻弄されていく。 (続く)