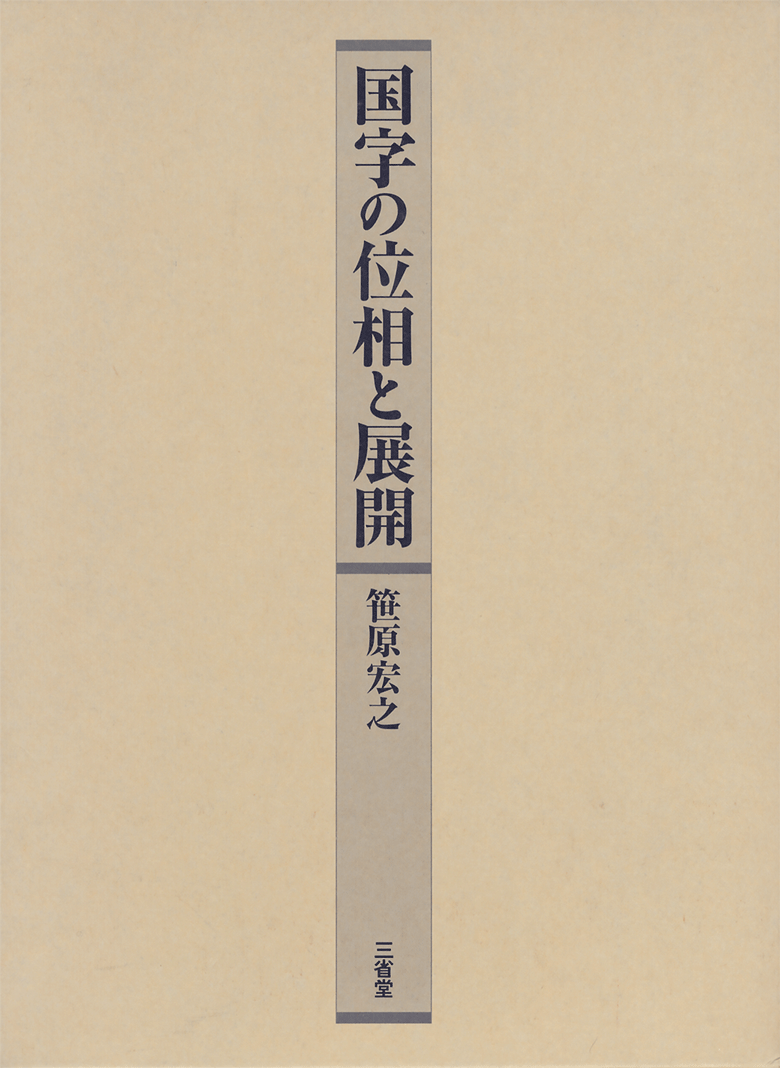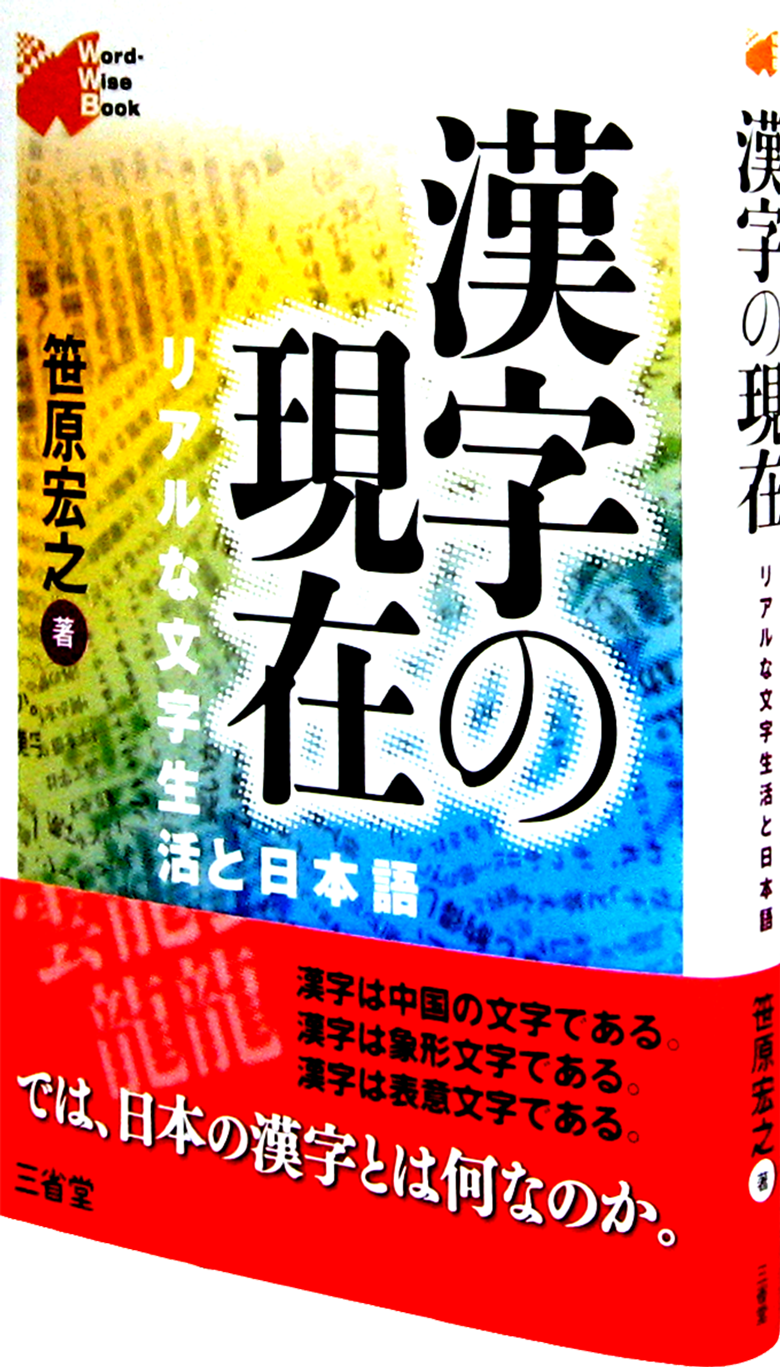夕刻、書店街に連れて行ってもらった。本を探して路地裏にまで行くと、往年の香港の九龍城もかくや、と思わせるようなワクワクしてしまう空間へ。便利なGoogle Earthだってここまでは入り込んで見せてはくれまい。
地元の先生は普通に入っていく。ついていくと、アーチの中は薄暗い。生活圏を垣間見られた。通りの窓から誰かの室内が見え、筆字の漢字文が額に入っているようだ。フランス統治時代からの有名なアイス屋がなぜかそこにあり、一番おいしくて人気だという大豆から作られたアイスを買ってかじる。
ベトナムでは本は「冊」、助数詞は「巻」。日本では「1冊の本」「本1冊」が一般的で、「冊子」や「1巻」というと質が変わる。中国では「1(一)本書」が普通の言い方。韓国は、なんとベトナムと同じだ。漢字は失われてたとしても、古い中国語は、辺境に残りやすいのだ。
本屋に入ると、表紙に漢字が散見される。クオックグウと併記されたものがある。漢字の方が従の存在であるものが多い。書店はあえて避けていた場所なのだが、やはり路上で分かることは限られている。店内にいると時間がどんどん過ぎてゆく。中国の書店に入る時と同様に、あまり期待しないで行ったのだが、意外と面白い本が置いてある。ベトナムの人は、中国の古典に出る故事を概して好むのだそうで、日本でもよく尋ねてくる方がおいでである。日本語以上に、漢語のままであっても、自国語に取り込みやすいようだ。

(クリックで拡大)
36KẾ
これは虚を突かれた。すぐに、逃げるにしかず、逃げるが勝ちで有名な兵法、「三十六計」と察することができたのは、表紙を見たお陰だったか。日本語でも、漢数字を読みやすくアラビア数字に変えることが進んでいるが、さすがに「36計」とは書きがたい。韓国ではどうだろう。やはり「三十六計」をそのままハングルに直した「삼십육계」あるいは「36계((g)gye ケ)」と書くとのこと、漢字を廃するとアラビア数字への抵抗感も薄れる。
本来の表記が漢字であると意識にも焼きついていると、かえって当てアラビア数字、当てローマ字というように感じてしまう。こうした概念も、当て字など表記を広く捉え直すためには必要なのであろう。ここに日本人のいだく違和感は、漢籍に出たことが明白な歴史的な用語で、他の数字が代入もできないためであろう。
もちろん日本でも、どこまでを漢数字で、どこからをアラビア数字で迷うことがある。出版も新聞も悩み続けてきた問題だ。「10人から数100人」、「10人から100数十人」といったケースでは後ろの数字を「数百」「百数十」とすれば、表記上の対称性は犠牲となり、泣き所といえる。さらに、「50歩100歩」なんてものも見ることがある。アラビア数字は、表意文字といわれるだけに何とでも読め、漢数字もそれに準じる面を持っている。中国の学生がある時、「〇〇七」という数字はスパイのようだ、と話した。漢数字を格が高いものとしがちな日本人だが、さらに微妙な感覚の差が漢字圏内ではありそうだ。
学生もよく「1番好き」と書いてくる。順位は「1番」、副詞は「一番」、あるいは「いちばん」とするルールも一部にはある。しかし、テレビ字幕もしょっちゅう「1番」と表示する。横書きだからかと思っていると、学生が縦に書いた原稿用紙にも出てくるときがある。
ベトナムの本屋に戻ろう。現代の北京語だけでなく、日本語の教科書も置いてあり、表紙にはそれらの漢字が印刷されているのは当然である。
ベトナム語の本にでも、表紙や背表紙に漢字が見られる。「金瓶梅」など中国物に多く、
孫(簡体字)子兵法
内経(簡体字)
大伝(簡体字)
などと簡体字が目立つが、
三國演義
など繁体字も散見される。それらにはクオックグウが添えられているのが常であり、無いものは筆字による雰囲気を醸し出すための装飾としての使用のようだった。