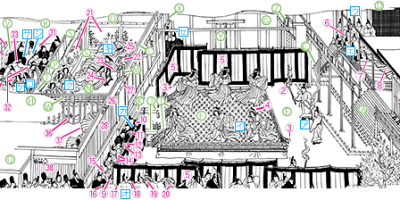中学の時に『旺文社国語辞典』を買ってから、私の国語辞典生活は、長らくこの1冊に支えられていました。正確には、中学2年で祖父の『広辞苑』(岩波書店)初版を譲り受けたし、部屋に飾ってあった『日本国語大辞典』(小学館)も、いつしか使うようになっていました。でも、大学に入るまで、ふだん使う辞書は『旺文社』1冊きりでした。

国語辞典を比較して論じる文章を目にすることもあり、辞書ごとに語釈などの特徴が違うのは、なんとなく分かり始めてはいました。特に、井上ひさしさんが『本の枕草紙』(文藝春秋、1982年)で述べている辞書論は、おもしろく読みました。
井上さんは、『新明解国語辞典』(三省堂)、『広辞苑』、それに『岩波国語辞典』の語釈を比較します。たとえば、「学際」の説明のしかたは、『新明解』は〈解説が自家中毒症状〉、『広辞苑』は〈平明を装っていて、その実、まことに曖昧〉とする一方、『岩波』は〈平易でよくわかり〔略〕「立て付け」のよい解説〉と高く評価します。
『岩波』の語釈の中でも、井上さんに〈これは凄い辞典だ〉と言わしめたのは、「右」の語釈でした。初版以来、基本的に変わらず、こうなっています。
〈相対的な位置の一つ。東を向いた時、南の方、またこの辞典を開いて読む時、偶数ページのある側を言う。〉(第七版による)
読者が今開いているページそのものを例に使うのですから、これほど確かな説明はありません。まさに名語釈です(後に、『三省堂国語辞典』もこの説明を採用しています)。
ただ、私は、これを読んで『岩波』を買いに走るところまでは行きませんでした。手元の『旺文社』の語釈をいくつか確かめて、べつに悪くない説明だったことに安心し、それきりになりました。やはり、語数の多い辞書が1冊あればいいと思いました。
こういう辞書観が変わったのは、大学3年の春でした。当時愛読していた情報誌『ぴあ』の読者欄で、たまたま、辞書の語釈を引用したこんな投書を見つけました。
〈善処――うまく処理すること。〔政治家の用語としては、さし当たってはなんの処置もしないことの表現に用いられる〕…最近何かと話題に出てくるS堂S国語辞典より。〉(『ぴあ』1988.4.29 p.122「はみだしYouとPia」)
辞書の常識をくつがえす辞書
これは現実の国語辞典でしょうか。おもしろすぎるではありませんか。〈最近何かと話題に出てくる〉と言うからには、ほかにもこんな皮肉の利いた語釈があるというふうに読めます。もしそうなら、辞書の常識をくつがえす辞書だと思いました。
私はついに書店に走り、〈S堂S国語辞典〉が『新明解国語辞典』であることを突き止めました。後に赤瀬川原平『新解さんの謎』(文藝春秋、1996年)などで取り上げられ、独特の語釈が有名になりましたが、それ以前から一部では人気があったのです。
『新明解』は、私にとっての2冊目の小型国語辞典として、本棚に収まりました。この時点で、辞書を選ぶ観点として、「収録語数」などのほかに、「語釈」が加わったことになります。もっと言えば、「語釈が笑える」という、いささか興味本位の観点です。
実際、『新明解』の語釈はユニークでした。たとえば、「読書」を引くと、他の辞書に比べて異様に詳しい説明の後に、さらにつけ足してこう書いてあります。
〈寝ころがって漫画本を見たり 電車の中で週刊誌を読んだりすることは、勝義の読書には含まれない〉(第六版による)
総じて、この辞書については、「語釈に主観が入っていておもしろい」という肯定的な意見と、「語釈が主観的で感心しない」という否定的な意見とがあります。でも、そのどちらも的確ではないと、私は思います。
『新明解』の語釈は、べつに編者が主観を交えて書いているわけではありません。「政治家の言う『善処』は『何もせず』」「寝転んでまんがを読むのは読書でない」などの説明は、日本語を話す人々の間に昔からあった見方です。自分が賛成か反対かはともかく、広くそういう見方があることを踏まえなければ、日本語をうまく使うことはできません。
「鴨」を引くと〈肉はうまい〉などとあるので、「編者はカモの肉が好きらしい」と評する人もいます。でも、これも、昔からカモの肉がうまいと思われてきただけのことです。「鴨葱」ということばがあるくらいです。決して編者個人の主観ではありません。
つまり、『新明解』の語釈の特徴は、ことばの用いられてきた文化的背景までを含めて記述するところにあります。そのことに気づくのは後年のことで、当時は単純に「過激でおもしろい辞書」として、私のお気に入りに加わりました。