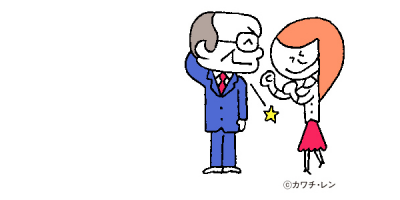1901年5月、黒沢は日本への帰国の途に付きました。エリオット&ハッチ社の輸入代理店として、開発したばかりのカタカナ・ブック・タイプライターを、日本で売りさばこうと目論んでいたのです。東京の京橋区弥左衛門町に、黒沢商店という名の小さな店を構えた黒沢は、さっそく、ブック・タイプライターの売り込みを始めました。逓信省の大岩を頼って、日本橋の東京郵便電信局に2台のカタカナ・ブック・タイプライターを納め、さらには、汐留の築地電信局との電信実験にも立ち会いました。しかし、実験はうまくいきませんでした。カタカナ・ブック・タイプライターの動作は、あまりにも緩慢で、和文モールスの受信スピードに追いつけなかったのです。しかも、動作音もかなり大きく、モールス受信の妨げとなりました。電信局への売り込みは、あきらめざるを得なかったのです。けれども、そんなことでメゲる黒沢ではありません。ブック・タイプライターをどんどん売り込むべく、外務省や他の省庁にも日参しました。

丸善のタイプライター広告(『學の燈』1900年10月号)
黒沢の売りは、タイプライターのメンテナンスを黒沢商店がおこなう、という点でした。どんなに高価なタイプライターを輸入しても、継続的にメンテナンスしなければ、結局、故障して動かなくなってしまいます。当時、黒沢のライバルは、丸屋善吉商社(丸善)が輸入していた「Wellington No.2」で、軽量小型が売り物でした。28キーでダブル・シフト84字の「Wellington No.2」は、しかし、スラスト・アクションという独特の印字機構のために、故障が絶えなかったのです。一方、黒沢が扱っているエリオット&ハッチ・ブック・タイプライターは、かなり重厚なデザインではあるものの、やはり故障がつきものでした。そこで黒沢は、ブック・タイプライターの故障修理とメンテナンスを、黒沢商店自身がおこなうことで、顧客を獲得しようとしたのです。
1902年4月5日、27歳の黒沢は、竹中きくと結婚しました。結婚式は、牧師立ち会いのもと、キリスト教式だったようです。翌年には、長男の敬一も生まれ、順風満帆とまではいかないものの、ブック・タイプライターの売り上げも徐々に伸びてきていました。しかし、不安な要素もありました。輸入元のエリオット&ハッチ社が、1903年2月28日、オハイオ州クリーブランドのフィッシャー・ブック・タイプライター社との合併を発表し、6月15日にエリオット・フィッシャー社となったのです。合併とは言うものの、工場はクリーブランドに一本化されて、ニューヨークには事務所だけが残りました。とどのつまり、旧エリオット&ハッチ社のブック・タイプライターの生産は減らして、フィッシャー・ブック・タイプライターの方を生産していくことになったのです。黒沢がこれまで販売してきたブック・タイプライターは、今後はメンテナンス部品が手に入らなくなっていくことが予想されたのです。
(黒沢貞次郎(5)に続く)