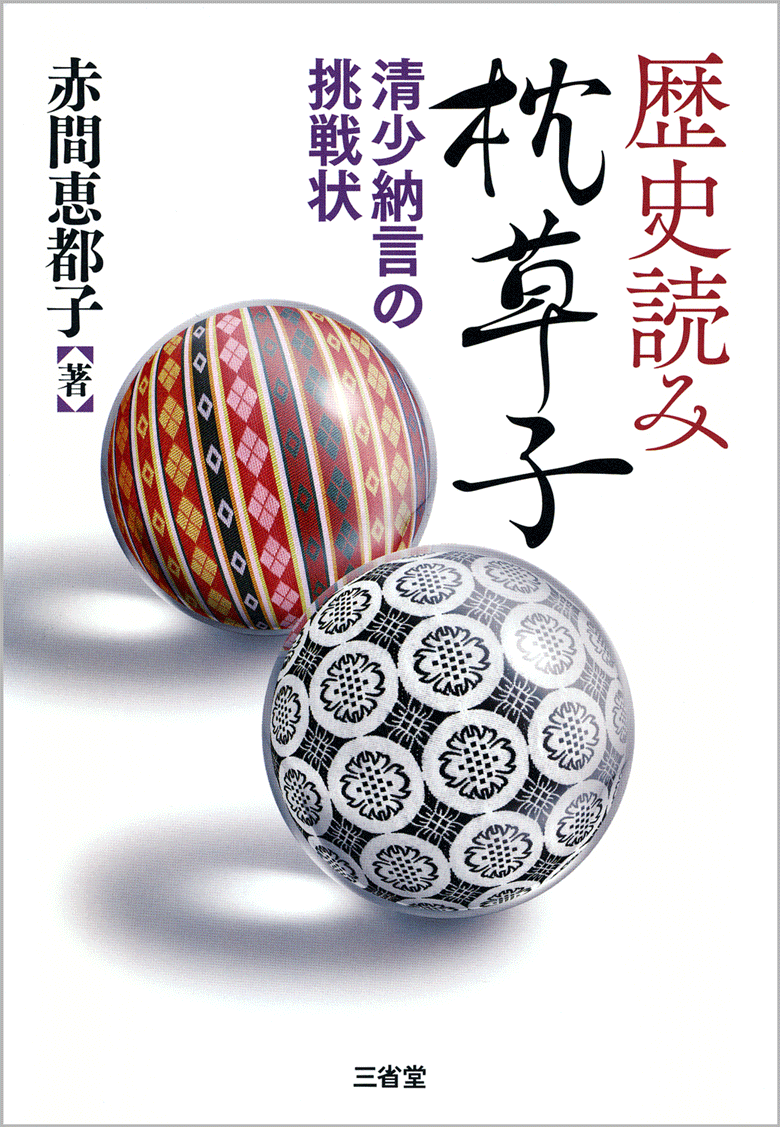定子の父の関白道隆は容姿の美しい人だったようです。『大鏡』には、43歳で亡くなる直前の道隆の姿を目にした源俊賢(としかた)が、「病づきてしもこそかたちはいるべかりけれ(病気にかかった時こそ、美貌は必要なものだったよ)」と言ったと記されています。
その道隆の血を引いた定子の兄の伊周(これちか)は少しふくよかな体格だったようですが、見栄えは悪くなかったようです。清少納言の宮仕え第2日目に登場した彼は上下紫の直衣姿で、雪景色の中にくっきりと映えて、「いみじうをかし(とてもすてきだ)」と書かれています。
当時は台風や雷雨など天候に異変が起こった後には、荒天見舞いの殿上人が後宮を訪問します。邸のどこかが壊れたり、通り道に支障が生じたり、何か不都合はないかを確認する為でもありました。伊周も妹中宮の積雪見舞いに訪れたのですが、そこで二人の間に交わされた和歌を踏まえた応酬は、几帳の後ろから覗いていた清少納言を瞠目(どうもく)させます。
物語にいみじう口にまかせて言ひたるに、たがはざめりとおぼゆ。(物語でどこまでも口から出任せに言っている理想的な情景と、ちっとも違いはないようだと思われる)
日常会話で和歌を交えて応酬するなど、物語の世界だけの話だと思っていたのに、それが、現実に目前で行われていることに感銘を受ける清少納言。さらに、この時の定子の姿を描写した後には、次のように記されます。
絵にかきたるをこそ、かかる事は見しに、うつつにはまだ知らぬを、夢の心地ぞする。(絵に描いてあるものではこのような場面は見たが、現実世界ではまだ知らないのに、夢のような気持ちがする)
物語や絵のような現実離れした世界、これが、はじめて上流貴族社会に接して抱いた清少納言の感想でした。周りの情景にすっかり心を奪われ、田舎者の傍観者として後宮をながめている清少納言に、この後大変なことが起こります。女房の誰かにそそのかされた伊周が、清少納言を見つけて、すぐ側までやってきたのです。
伊周は清少納言が隠れていた几帳をどかして目の前に座ります。そして、宮仕え前に耳にした清少納言に関する噂を持ち出して、これは本当なのかと聞いてきます。それまでの伊周は、清少納言にとって遙か遠い存在でした。見物好きの清少納言が、いつか天皇の行列を見に言った折、行列に加わっている伊周がちょっとでも彼女の乗っている車の方に目を向けたたけで、簾(すだれ)を引いて隙間をふさぎ、車中で扇をかざして透き影も見えないように顔を隠していたのに、今、その伊周が目の前で直接自分を見つめているのです。
身の程もわきまえずにどうして宮仕えに出てきてしまったのかと、冷汗もしたたり落ちる状態の清少納言。対する20歳そこそこの大納言伊周は、清少納言が顔を隠している扇まで取り上げてしまいます。仕方なく髪を振りかけて顔を隠そうとしますが、今度はまったく自信のない髪筋を見られているのが恥ずかしくてたまりません。
一方、伊周は清少納言の扇をもてあそびながら、「この絵は誰にかかせたのだ」などと言ってなかなか返してくれません。清少納言はついに袖を顔に押し当ててその場に突っ伏してしまいました。化粧の白粉が着物に移って顔は斑になっているにちがいないと思いながら…。
追いつめられて身動きも出来ない清少納言に、助け舟を出そうとしたのは中宮定子でした。何かの本を取り出して兄を自分の方へ来させようとしますが、伊周は清少納言が自分を離してくれないのだととんでもない冗談を言い、さらには、清少納言が世間の書家の筆跡を全て知っているから本をこちらによこすようにと言うのです。
関白家のお坊ちゃんに絡まれ、ほとほと困り果てている清少納言の様子が想像できますね。作者自身もこの章段を書きながら、宮仕えの当初を思い出して思わず微笑んだのではないでしょうか。