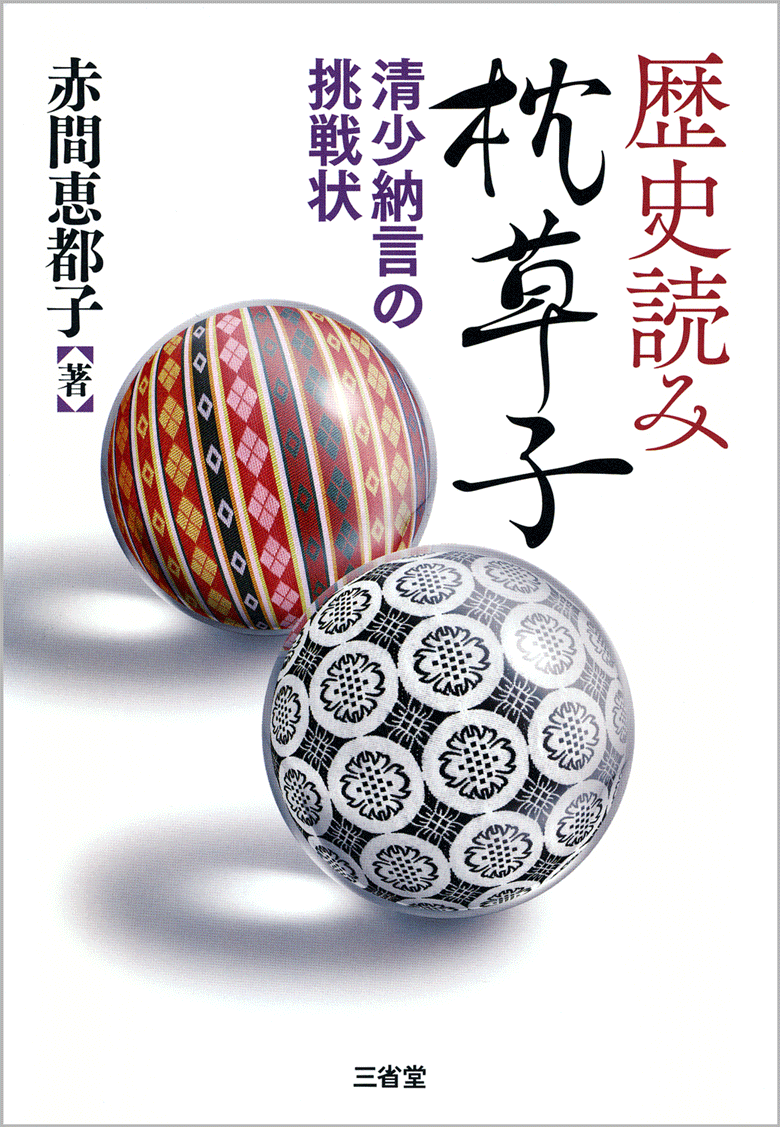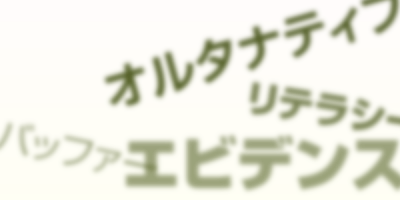清少納言が初めて出仕した年は、正暦(しょうりゃく)四年(993)だったと考えられています。『枕草子』には、それ以前の出来事を扱った章段もいくつかありますが、それはひとまず措(お)いて、まず、初出仕の日の事を記した章段から見ていきたいと思います。
宮にはじめてまゐりたるころ、物のはづかしき事の数知らず、涙も落ちぬべければ、夜々まゐりて、三尺の御几帳(みきちやう)のうしろに候ふに、絵など取り出でて見せさせたまふを、手にてもえさし出づまじうわりなし。
(中宮御所に初めて出仕したころ、何もかも恥ずかしいことだらけで、涙も落ちてしまいそうだったので、毎夜参上して、三尺のついたての後ろに控えていたところ、中宮様が絵などを取り出してお見せくださるのを、それに私は手さえも差し出すことが出来そうもない状態でどうしようもなくつらい。)
定子サロンの看板女房として上流貴紳と互角に渡り合うことになる清少納言も、初宮仕えの時の緊張は相当なものでした。それまで他人と顔を合わせる事に慣れていなかった彼女は、顔を人に見られることが恥ずかしくて、毎日、夜にしか参上できない有様でした。うだつの上がらない中流貴族の生活から、今を時めく関白家、さらに宮廷という雲の上の世界に足を踏み入れたのですから無理もありません。身分制度のない現代社会では考えられないくらいの緊張、と同時に未知の上流界への憧れが清少納言の感覚を麻痺させてしまうのです。
その清少納言を待ちかねていたのが中宮定子でした。有名な歌人清原元輔(きよはらのもとすけ)の娘という事で興味を持っていたのでしょう。自分から清少納言に近づき直に声をかけてきます。そこには、権勢家の娘として生まれ、天皇妃となった定子の積極的で好奇心旺盛な姿が描かれています。
この時、定子は17歳、清少納言はそれより10歳程年上だったと考えられます。しかし、極度の緊張のために定子の前では一言も発することができませんでした。顔も上げられない清少納言の目に止まったのは、定子が彼女の気を引こうとして絵を差し出した時に袖口からのぞいた手でした。
うっすらとピンク色を帯びてつやめいている美しい指先。上流貴族の娘として大切に育てられ、今、中宮として宮廷に君臨している若々しい女主人の手…それが、清少納言の印象に残った定子の最初の記憶でした。
定子の指先が色づいていたのは、その折の京都の寒さのせいだったとも考えられています。定子の前で数時間留められ、やっと退出を許されて緊張が解けた時、清少納言の目に映ったのは、庭に降り積もった白い物でした。ああ、雪が降っていたのかと気付き、そこで一時我に返ります。このあたりの描写はさすがです。
さて、翌日は昼間から度々のお召しがあり、同室の先輩女房の忠告を受けて再び定子のもとに向かうことになりますが、その時、清少納言の目に入ったのは、火焼き屋(ひたきや=警備のために火を燃やす小屋)の上にまで降り積もった雪でした。一晩でかなりの量の雪が降り積もった様子から、季節は冬ではないかと考えられます。
定子の前に出ると、依然として緊張で凝り固まっている清少納言。そこに登場したのが大納言伊周(これちか)、すなわち定子の兄でした。次回に続きます。