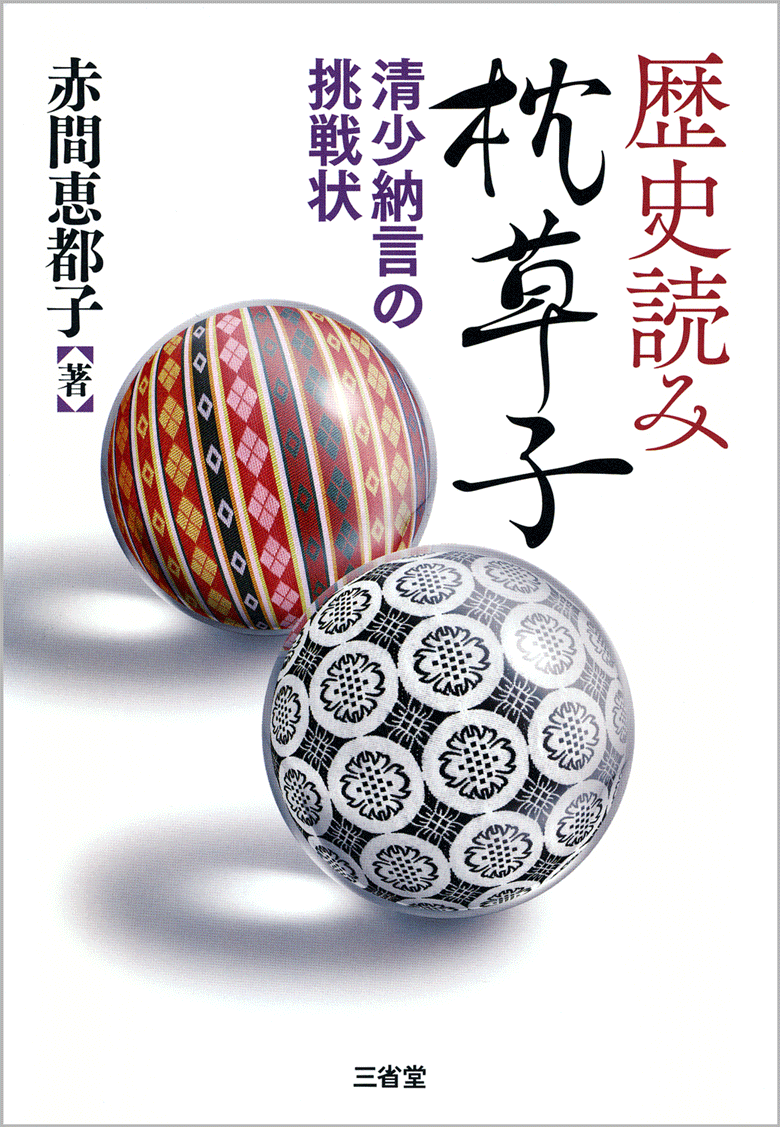今内裏を舞台とした章段で、天皇が可愛がっていた猫の紹介から始まる一風変わった話があります。その猫は宮中に伺候するために5位の位を得て、「命婦(みょうぶ)のおとど」という名を与えられ、人間の乳母が付けられ大切に世話されていたというのですから、やや尋常ではありません。『小右記』によれば長保元年9月19日に誕生し、猫付きの乳母が人々の笑いの種になっていたようです。
長保2年の春には生まれて半年程になるこの子猫が縁側に出て寝ていたところ、乳母が「まあ、はしたない、中に入りなさい」と人間扱いをして呼びます。しかし相手は猫、当然ぐっすり寝ています。そこで乳母は犬に命じて猫を脅し入れるという強硬手段に出ます。犬は猫に走りかかり、猫は怯えて簾の中に駆け込むのですが、それを天皇がご覧になっていたから大変です。犬は打たれて島流しに、乳母は更迭という厳罰が下されます。
この時、蔵人たちに打たれ追放された哀れな犬が、翁丸という名のこの章段の主人公です。翁丸は普段から今内裏に出入りして、女房たちにも顔なじみの犬だったようで、清少納言もその身の上を案じます。夕方、身体中を腫れあがらせた犬が震えながら歩いているのを見て、清少納言が「翁丸」と呼びますが、犬は返事をしません。食べ物を与えても食べないので、皆、確信が持てないままに、翁丸はもう死んだというから違う犬ではないかということになりました。
次の朝、定子の身繕いに奉仕していた清少納言が、柱の下にうずくまっている昨夜の犬を見て、「ああ、昨日は翁丸をひどくたたいて、死んでしまったのは可哀想だった。生まれ変わって今度は何の身になったのだろう。どんなに辛かっただろう」と言った途端でした。犬がぶるぶる震えて涙を落したのです。やはり翁丸だったのか、昨夜は正体を隠していたのかと納得して、「翁丸か」と呼ぶと、ひれ伏してひどく鳴きます。それを聞いた天皇もこちらに来て、犬にもそのような心があったのだとお笑いになります。天皇付きの女房たちも皆集まって来て翁丸を呼ぶと、今度は反応するのでした。その後、翁丸は罪を許されたということです。
この章段では定子の姿はほとんど描かれません。清少納言と共に翁丸の身の上を心配し、翁丸が正体を明かした時には安心して笑ったと書かれるのみです。犬を主人公にしたこんな不思議な話が、なぜ『枕草子』に書き留められたのでしょうか。この話は読者に何かを連想させます。翁丸は、乳母に命じられて何の考えもなく、天皇家の猫を脅したために、島流しの宣旨を受けてしまいました。女房たちは翁丸に同情して憐れむのですが、何一つできないまま事の成り行きを見守るしかありませんでした。そんな事態が歴史的なある事件と重なります。この章段の時点から4年前、定子の目前で伊周・隆家が左遷された長徳の変の出来事です。
しかし、中関白家の失墜を招いた不幸な事件を、当家に仕える作者が取り上げることなどできたのでしょうか。いろいろな見解が取り沙汰されています。これについて、次のように考えてみてはどうでしょう。事件から、さらに定子崩御からかなりの時間が経過した時、作者にはどうしても目撃した事を書き留めておきたいという思いが残っていた。しかし、作者の立場では、こんな形で触れるのが精一杯だったのだと。
奇特な動物譚として語り終えられるこの章段が、これまでと異なる作者の語りの位置を示しているように思われてなりません。それは後宮女房という役目の枠を越えた、歴史の生き証人としての位置だったというのは言い過ぎでしょうか。