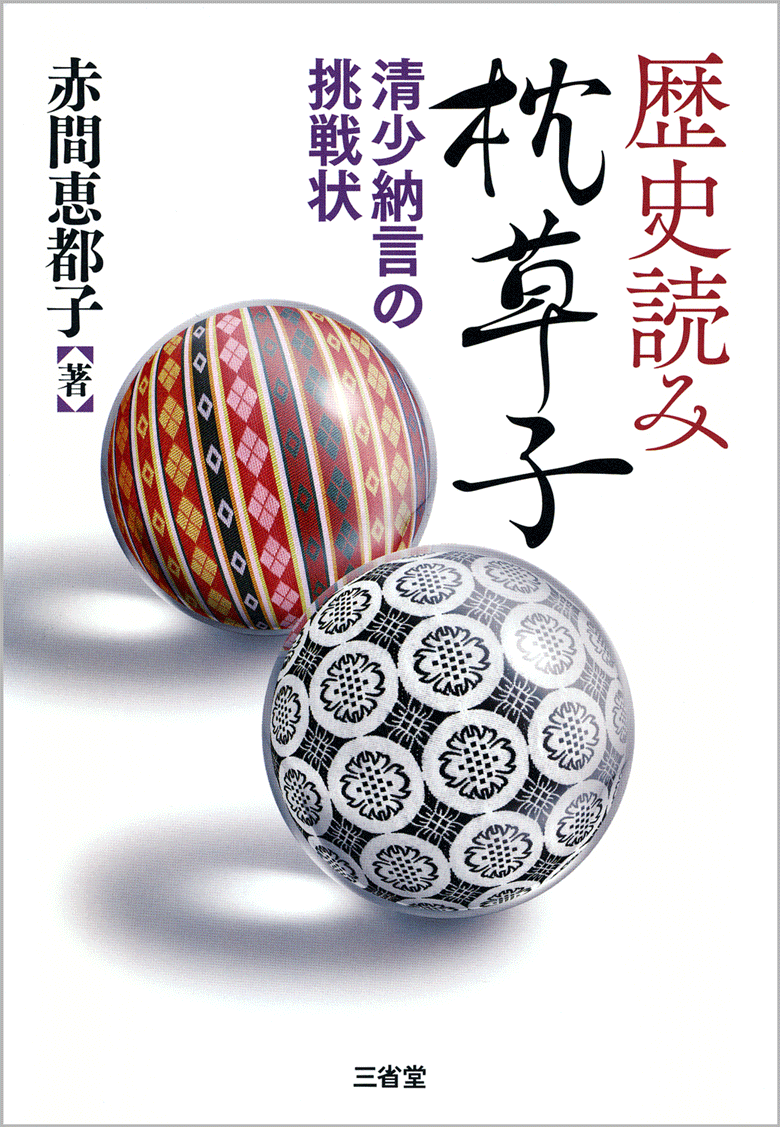『枕草子』の三巻本系の本が三条宮の段の次に語る、一つの短い章段を紹介しましょう。定子の傍に乳母として長年仕えてきた女房が、地方に下ることになった話です。これが、いつ、どこでの出来事なのかは示されていませんが、乳母が定子の元から去らねばならない状況を考えると、やはり中関白家没落後の話ではないかと推測されます。
大輔の命婦(たいふのみょうぶ)と呼ばれるその乳母との別れに際して、定子は扇を贈りました。扇の片面には、日がうららかに差している田舎の家々の風景が描かれており、反対側の面には、都の立派な御殿に雨がたくさん降っている風景に次の歌が書かれていました。
あかねさす日に向ひても思ひ出でよ都は晴れぬながめすらむと
(明るく輝く日に向かって旅立っても、思い出してください。都では晴れぬ長雨の中で物思いに沈んでいるであろうと)
大輔の命婦が旅立つ先は、現在の宮崎県に当たる日向(ひゅうが)の国でした。明るくのんびりとした南国へ行っても、都で物思いをしている私の事を忘れないでね、と最後に乳母に甘えた定子の気持ちが素直に歌われています。注目したいのはこの歌の後、章段末尾に記された作者の言葉です。
御手にて書かせたまへる、いみじうあはれなり。さる君を見おきたてまつりてこそ、え行くまじけれ。
(中宮様の御直筆でお書きになっているのは、本当にしみじみと悲しいことです。このような主人の様子を拝見して、そのままお置き申し上げて行くことなど、どうしてできるでしょうか)
『枕草子』の中で、清少納言が定子に対して「あはれ」という語を使った唯一の例です。先行き不安定な主人にこのまま仕えているより、地方官の役職が決まった夫と堅実な生活を送る方を選択するのは、当時の中下流階級の女性が生きていくために当然の判断だと思います。時勢の流れとはいえ、最も親しい乳母からも見捨てられた定子の悲しみを傍で感じ、清少納言は思わずこれまで抑えてきた思いを吐き出してしまったのでしょう。自分だけは最後まで定子の傍にいる、決して離れはしないという決意表明とも見られるところです。
かつて清少納言にも宮仕え継続を迷った時期がありました。長徳2年の事件に付随して清少納言の周辺に渦巻いていた不穏な空気に耐えきれず、長らく里居生活をしていた時です。そんな時、定子は彼女らしい気転の利いた方法で、直に清少納言に働きかけてきました。定子の気持ちに感動し、再出仕を決意してからの清少納言は、もう、迷うことなく自分の行くべき道を定めていたのでしょう。
ところで、この段で作者が漏らした言葉は、『枕草子』がこれまで描いてきた定子と作者の関係を崩しているようにも思われます。いかなる時にも悲しみを表面に出さず、女房たちを導いてきた主人を作者は描いてきたのではなかったでしょうか。しかし一方で、最後まで明るさを演出し続けた『枕草子』の底流に、定子の運命を悲しむ作者の真実の思いがあったことも確かでしょう。その思いは、育て親との別れを悲しむ定子の心情に作者の心が共鳴した際に思わず発動し、作品本来の意図を外れて筆が動いてしまったと推測することができます。
悲運な主人への忠誠を改めて誓った清少納言ですが、その後、間もなく訪れる定子との永遠の別れを、この時は予想もしていなかったに違いありません。