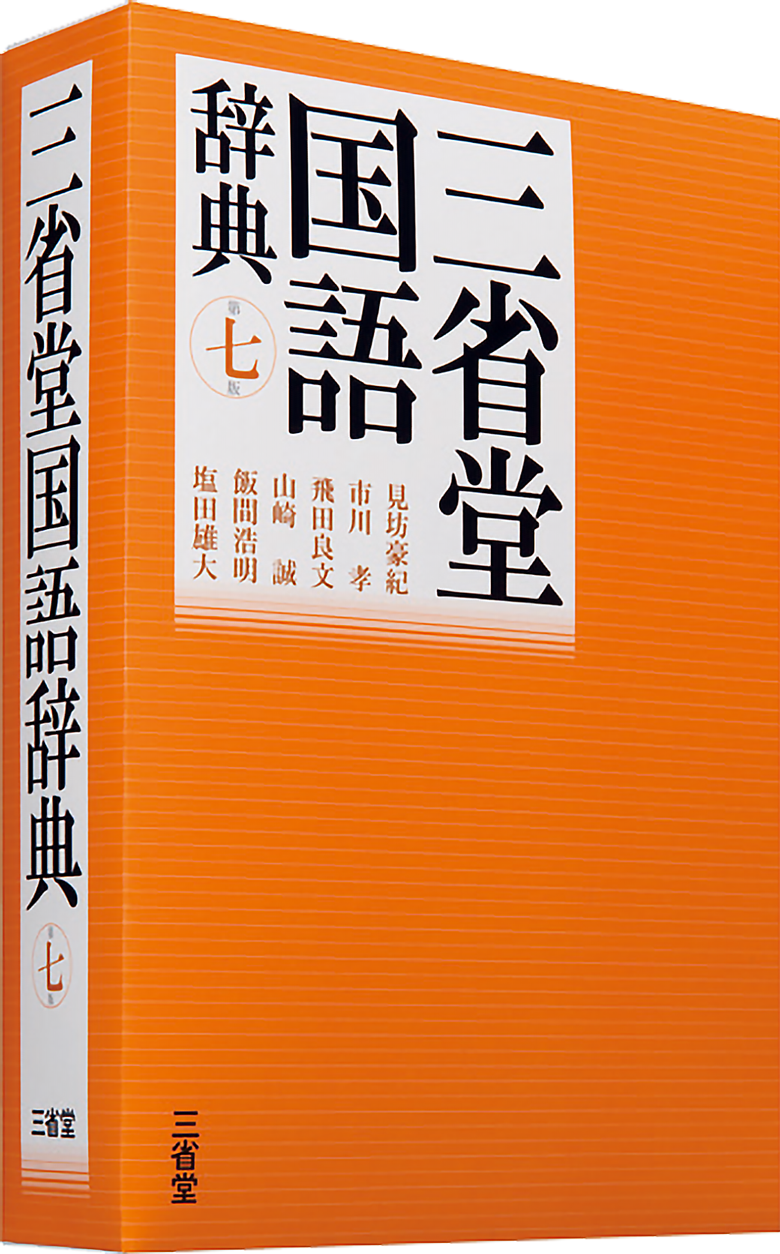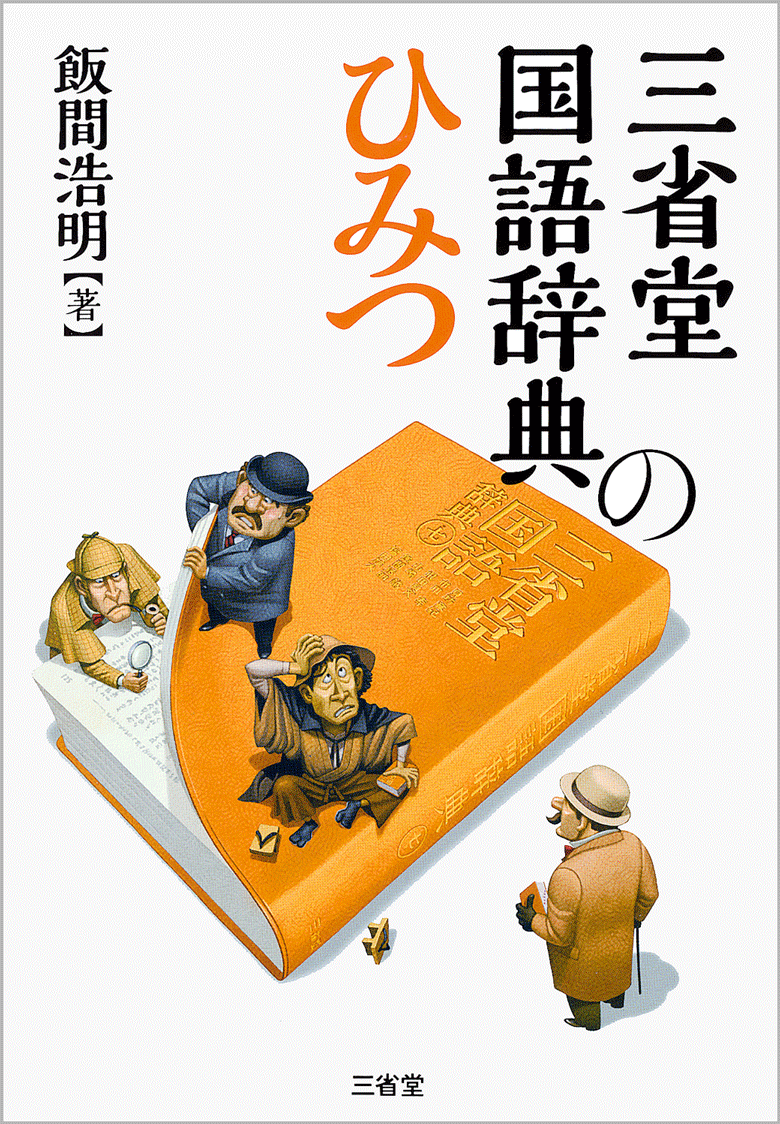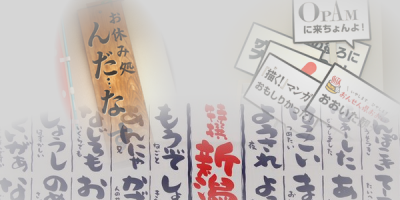辞書を引きたくなるときというのは、むずかしいことばを知りたいときばかりではありません。ごく簡単なことばの意味を知るために辞書が必要になることもあります。
いつぞや、「パソコンを利用して文章を作成する」と書きかけて、待てよ、「使用して」のほうがいいかな、と迷ったことがあります。『三省堂国語辞典』で確かめると、「使用」は単に〈使うこと。〉とあり、「利用」は〈役立たせて うまく使うこと。〉とあります。してみると、特に何の含みもない場合には「使用して」がよさそうです。辞書は、このように、だれでも知っているようなことばについても、手を抜かずに説明すべきです。
『三国』の主幹だった見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)は、ことばの説明をできるだけ簡潔に書くことを目指していました。子どもが読んでも、ぱっと分かるようにするためです。ただ、旧版の『三国』では、簡潔を期するあまり、そのことばの本質的な意味や、ほかの似たことばとの違いがよく分からない場合もありました。
たとえば、「せんべいがしける」という場合の「しける」の意味について、旧版では「しっける」の項目に〈水分をふくむようになる。〉と記しています。また、「湿(しめ)る」については〈水気(ミズケ)を おびる。〉としています。「しける」と「湿る」の違いがよく分かりません。さらには、「濡(ぬ)れる」との違いも分かりません。

今回の第六版では、「しける」を〈水分をふくんで、だめになる。〉と説明しました。水分を含んだ「しっとりクッキー」は、しけているわけではありません。「しける」は、いい場合には使いません。そのことを、〈だめになる〉という5文字で表現しました。
一方、「湿る」は、〈さわると わかるくらいの水気(ミズケ)を おびる。〉としました。「湿る」の場合、水滴がしたたり落ちたりすることはありません。洗濯物が湿ってるかどうかは、手で触って判断します。〈さわると わかるくらい〉という説明が必要です。

ちなみに、「濡れる」は〈水が かかったりして、水気(ミズケ)を持つ。〉で、これは旧版のとおりです。

ことばの意味の特徴をくわしく説明しようとすれば、だらだらと長くなりがちです。そうなってしまっては、『三国』らしくありません。『三国』では、似たことばの意味の違いをうまく説明し、しかも簡潔に書くという、二兎(にと)を同時に求めたいと考えます。