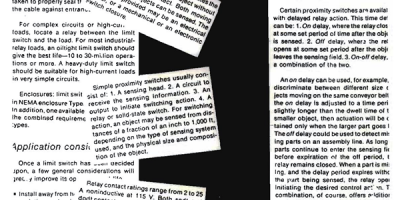パリからロンドンへの強行軍がたたったのか、住友は病に伏してしまいました。山下が、ロンドン在留中の帝国海軍軍医を紹介したところ、胃カタルとの診断で、数日の静養を要するとのことでした。1897年4月13日にドーリック(Doric)号で横浜を出帆して10週間、住友の疲れもピークに達していたのでしょう。その後も山下は、住友の部下である鈴木馬左也を通じて、住友の世話を何くれとなく焼く羽目になりました。セント・ジェームズ・パーク周辺にホテルを探したり、執務や面談のために帝国領事館の一室を準備したり、しかも住友は、そのままロンドンに長期滞在を決め込む様子でした。6月30日には有栖川宮が、7月3日には伊藤が、それぞれロンドンを出立しましたが、住友は8月18日までロンドンに滞在し、山下をはじめとする帝国領事館員とも顔なじみとなりました。
この時期のロンドンには、アメリカからどんどんタイプライターが輸入されていました。「Remington Standard Type-Writer No.2」「Caligraph No.2」「Densmore Typewriter」「Yost Typewriter」「Smith Premier No.2」「Williams」「National Typewriter」「Bar-Lock」「Crandall New Model」「Blickensderfer No.5」「Elliott & Hatch Book Typewriter」「Underwood Typewriter No.1」など、あらゆる種類のタイプライターが、リバプールを通ってロンドンに流れ込んでいました。これらに加え、イングランド国内でも、ロンドンでは「North’s Typewriter」や「Fitch Typewriter」が、ウエストブロムウイッチでは「Salter Typewriter」が製造されていました。「Fitch Typewriter」はブルックリンの会社ですが、ロンドンでもライセンス生産をおこなっていたのです。

ロンドンで製造された「Fitch Typewriter」
山下が勤める在倫敦帝国領事館でも、公式書類はまだまだ手書きだったものの、日々の伝票や手紙などは、タイプライターで打たれたものが増えていました。ただ、それらはあくまで英語やフランス語など、いわゆるアルファベットで書かれるものだけがタイプライターで打たれていて、日本語は手書きするしかなかったのです。欧米の言語に比肩すべく、日本語の書字をもっと「進化」させるべきではないか、という考えが山下の中に芽生えました。
(山下芳太郎(6)に続く)