前回まで増補として、明治末~大正にかけてのアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)、印刷局、東京築地活版製造所の3社とベントン彫刻機について見なおしてきた。今回からはふたたび、三省堂とベントン彫刻機の話に駒をもどしたい。
増補編にはいるまえ、第22回「震災からの復興とポイント制活字の導入」までで、三省堂が関東大震災から復興し、大正13年(1924)9月に蒲田工場が操業開始したところまで話をすすめた。今回からいよいよ、話は三省堂の書体研究にはいる。
三省堂・亀井寅雄は、ATFのリン・ボイド・ベントンを説得し、ベントン彫刻機をなんとか手にいれた。文字の印刷品質にこだわったからとはいえ、母型を新調するとなれば、各書体・サイズごとに数千字ずつをあらたに彫らなくてはならないというのに、彼はなぜ、そこまでベントン彫刻機をほしがったのだろうか。
その背景には、辞書ならではのつくられかたがあった。
辞書は、膨大な情報量をおさめる書物だ。だからといって、あまりにページ数がかさみ重くなっては、あつかいづらい本になる。できるかぎりページ数をおさえ、すこしでもコンパクトな辞書にするためには、ちいさな活字を誌面につめこまなくてはならない。
当時一般的な書籍の本文によくもちいられていた5号(=10.5ポイント=約3.67mm/※ポイントは以下「ポ」とする)や9ポ(=約3.16mm)のサイズでは、文字がおおきすぎた。しかし、活字母型のもととなる種字を職人が手彫りするのであれば、彫れるちいささにも限度がある。明朝漢字となれば、なおさらだ。

臼井翁という職人が種字を彫刻した新7号活字が使用された『新訳和英辞典』(三省堂、1916)
三省堂の書体開発をひきいた今井直一によれば、〈手彫りでは六ポイント以下の小さい文字は、ふりがな用のかなぐらいができるだけで、明朝漢字など到底思いも及ばぬところ〉[注1]だったという。しかしポケットサイズのコンサイス英和辞典などのシリーズ(167×96mm)では、5.1ポや4.9ポの本文が印刷されていた。

『最新コンサイス英和辞典』(三省堂、1929)誌面。
ポケット判のコンサイズシリーズの本文はちいさく、原寸・手彫りで種字を彫刻するのは不可能だった
いったいどうしたのかというと、いったんおおきめの8ポ(約2.81mm)の活字で組んだものを写真で縮小してフィルムを起こす。このフィルムで薬液を塗った亜鉛板を露光し、腐蝕させて亜鉛凸版をつくり、この亜鉛凸版をもちいて印刷していたのである。
その製造工程について、三省堂出版(当時)の阿部亨が『印刷雑誌』に寄せた文章がある。
(前略)大きく組んで鮮明に縮写する場合は、新鮮な活字で、特殊の上等な紙を用い、精巧な技術によって、美しく印刷したものを作る。これを清刷(筆者注:きよずり)というが、これを10枚20枚刷り、そのうちから良好なものを選び、これを写真で縮写して凸版を作る。だから清刷さえ良好に保存すれば、無限に凸版が作れるわけである。
阿部亨「辞書のできるまで(特殊出版物の作り方1)」昭和28年(1953)[注2]
つまり、活字組版から紙に一度印刷をし、それを版下として、製版時に実際の印刷サイズに縮小していたのだ。活字そのもの、組版そのものにうつくしさが求められるのも当然ながら、そこでは、いかにうつくしい清刷をとるかが重要になる。

辞書の活字組版(撮影:三省堂)
今井直一は、この製作工程でいかに細心の注意をはらわなくてはならないかを書きのこしている。コンサイス英和辞典(1130ページ)、新コンサイス和英辞典(1000ページ)、明解英和辞典(コンサイス型794ページ)、広辞林(四六判2000ページ)、小辞林(コンサイス型1000ページ)、明解漢和辞典(1000ページ)、国漢文辞典(四六判1140ページ)などの製版について述べた文章だ。
(前略)組版の持つ美しい正しい活字面を、そのままに正確に再現した立派な版下(清刷ともフート刷とも云う)を造らねば、優良な亜鉛凸版は勿論望むべくもない。数年を費し、十数校の校正を経た貴重な辞書の組版を、不覚にも最後の僅かな工程に於てスポイルする事がある。実に辞書類の製版ほど、細心の注意を要求するものはあるまい。例えば縮写の割合はどんなものか、原寸か三分ノ二か二分ノ一がよいか、版下に使う紙の紙質、光沢、純白がよいか淡クリームがよいか或は又、インキの選定等夫々の場合々々によって最も適当したものを研究する。(略)版下の修整から写真の撮影、焼付、腐蝕、仕上等各工程に、辞書独特の細心と熟練とを要求する。
今井直一「書物の印刷」昭和11年(1936)[注3]
三省堂は、亜鉛凸版をもちいての本文印刷にも、ふかい注意をもって取り組んだ。試し刷りをしては1文字1文字の印刷状態を調べ、印刷の圧が弱くて薄くなっているところ、あるいは利きすぎて濃くなっているところをチェックして、版胴に薄紙を貼って印刷ムラがなくなるよう、たんねんに「ムラ取り」をした。1台のムラ取りに3、4日費やすのがふつうだった時期もあるという。
兎に角印刷者の苦心は並大抵のものではない。何れの仕事にしても楽なものは無かろうが、よいものを印刷しようとするには、飽迄も最高の注意と長い経験、熟練、新たなる考案工夫を極端に要求されるものである。
今井直一「書物の印刷」昭和11年(1936)[注4]

三省堂印刷所 印刷部(三省堂百年記念事業委員会編『三省堂の百年』三省堂、1982)
これだけのこだわりをもってつくられた三省堂の辞書は、その印刷のうつくしさにも定評があった。しかしそれでも三省堂は、〈コンサイスものをはじめ、その他の辞書で小文字の印刷をするには、亜鉛凸版法によったのであるが、このように写真で縮めて製版するよりも、もし活字組版から直接印刷ができたら、さらに鮮鋭な美しいものになるだろう〉[注5]と、「もっとうつくしい印刷にしたい」という思いをもっていた。
それを実現できるのが、ベントン彫刻機だったのである。
ベントン彫刻機では、〈十二ポイント(筆者注:約4.2mm)の面に、一文字が〇・五ポイント即ち〇・一七五ミリメートルの大きさで聖書の主の祈り六十六語、二百七十一字を浮き彫り〉することができた。[注6]
辞書制作において、ひとが手で彫るのではむずかしい小活字の母型を彫刻することを可能にし、活字組版から直接印刷した、よりうつくしい誌面を実現させることができるツールが、ベントン彫刻機だったのだ。[注7]
だからこそ、「辞書は三省堂」とうたう同社にとって、ベントン彫刻機はどうしても手に入れたい機械だった。
(筆者注:わが社は)幸にベントン母型彫刻機によって、どんな小さな文字でも完全に彫刻ができるのである。
今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.19
どうしても必要だったという背景と、その熱意をかなえて入手した経緯からか、ベントン彫刻機について三省堂が語る口調は、どこか誇らしげだ。
さらにベントン彫刻機の導入は、書体デザインの手法としても、おおきな変革をもたらすことになる。
(つづく)
※出典のない写真は筆者撮影
[参考文献]
- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、今井直一「我が社の活字」(執筆は1950)
- 阿部亨「辞書のできるまで(特殊出版物の作り方1)」『印刷雑誌』昭和28年5月号(印刷雑誌社、1953)「築地活版移転の噂」『印刷雑誌』昭和12年10月号(印刷雑誌社、1937)
- 今井直一「書物の印刷」『書窓』第2巻第5号(アオイ書房、1936)
- 橘弘一郎「活字と共に三十五年――今井直一氏に聞く」『印刷雑誌』昭和32年40号(印刷雑誌社、1957)



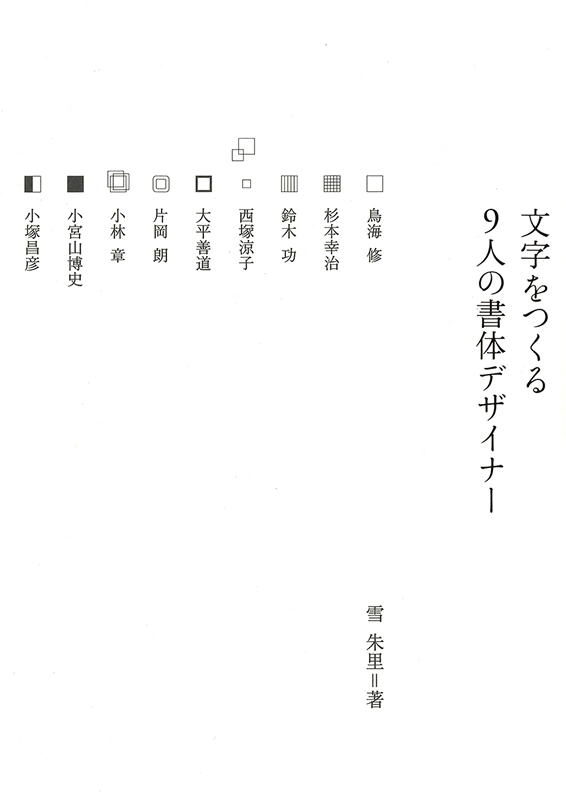




[注]