三省堂の亀井寅雄は大正11年(1922)、アメリカでリン・ボイド・ベントンと会い、直接交渉のすえにアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)からベントン彫刻機を買いつける契約をとりつけた。そして、今井直一をアメリカにのこし、ひとあしはやく日本にもどると、新工場の建設計画をすすめた。[注1]
ベントン彫刻機をむかえ、印刷事業をさらに拡張するための新工場計画だった。寅雄は経営にはあかるいが、印刷技師ではない。あたらしい工場には、それをまかせる技師が必要だとかんがえた。ひとりは、ベントン彫刻機をもちいた母型製造の技術をATFで学んでもらっている今井直一。そしてもうひとり、友人[注2]から紹介してもらったのが、早稲田大学理工科出身の桑田福太郎だった。
桑田は大学で機械を専修し、ひろい知識のあるひとだった。今井がATFでの研修をおえて帰国するのを待ち、桑田と今井は大正11年(1922)8月、三省堂に入社した。ふたりはともに、印刷や製本技術についての研究をかさねながら、新工場(蒲田工場)建設にかんするしごとをすすめていた。
工場建設計画をすすめる一方で、三省堂には急がなくてはならないしごとがあった。ATFからベントン彫刻機が到着したら、すぐに母型彫刻にとりかかりたい。そのためには、どんな文字を彫るのか、その前段階の「書体の研究」をしておく必要があったのだ。ましてやベントン彫刻機では、それまでの職人が手彫りした種字から母型をつくる方法とは、書体のつくりかたがまったくちがう。詳述はまた後の回におこなうが、ベントン彫刻機の導入によってはじめて、“紙と鉛筆、筆などをもちい、活字原寸ではなくおおきなサイズで、左右逆字ではなく正しい向きに文字を書く”という、現代のデジタルフォントでも(すべてではないが)おこなわれている「書体デザイン」の方法がとられることになったのである。これは書体デザイン史における大事件だ。
種字彫刻師がおこなっていたように、黄楊の木や金属の活字材に活字サイズ原寸で左右逆字を直刻し、統一したデザインの種字を一書体分彫り上げるというのは、そうとうの才能を要する技術だった。だから一書体すべてを任されるような種字彫刻師は、ひとにぎりの天才にかぎられていた。[注3] 紙に拡大原字を書く「書体デザイン」とて特殊な技術と才能が必要なことはかわらないが、種字彫刻にくらべると、その門戸はひろがったのではないだろうか。
しかし今井と桑田が直面したのは、「紙に原字を書く」ことがあたらしい手法だった時代である。だからこそ、念入りな「書体研究」が必要だった。
桑田は機械技師ではあるが、書道を趣味にもっていた。「文字の専門家にならないか」と亀井寅雄に口説き落とされた今井とともに、「三省堂の新書体をつくる」ことにおおきな熱意を燃やした。
翌大正12年(1923)8月には、書体研究に取り組む桑田の助手として、松橋勝二が入社し、文字を書くことになった。ところがその直後である同年9月1日、関東大震災がおき、書体研究はいっとき頓挫してしまった。
これが再開したのは大正13年(1924)5月のこと。
関東大震災当時、三省堂の本社は大手町にあった[注4]。関東大震災によって引き起こされた火災で焼けてしまったが、三省堂は復興を急ぎ、翌年5月までに3階建て420坪余の仮建築をおこなった。[注5]
大手町本社が復興するや、三省堂の書体研究は本格的にはじまった。
事務所には四つ切製版用カメラ1台と暗室、そのほかの写真設備をひととおりそろえた。
これ(筆者注:写真設備)は文字の拡大写真を作り、あるいはデザインした文字を活字大に縮小してその適否を検するなど重要な役割をもった施設であった。
今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.32[注6]
設備をととのえると、新聞や雑誌などから文字の収集にはげんだ。秀英舎や築地活版などの活字で印刷された文字を、まずはひらがな、カタカナ、明朝漢字、数字ごとに分け、それぞれの拡大写真をつくって比較研究した。さらに研究がすすむと、明朝活字のなかでも画数のおおい文字、すくない文字、ひらたい文字、ほそながい文字、おおきく見える文字、ちいさく見える文字……というふうに、次第にこまかい観点からの比較研究がおこなわれるようになっていった。

彫刻した活字を拡大し、細部を見るための活字投影機[注7]
(つづく)
[参考文献]
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、今井直一「我が社の活字」(執筆は1950)
- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)



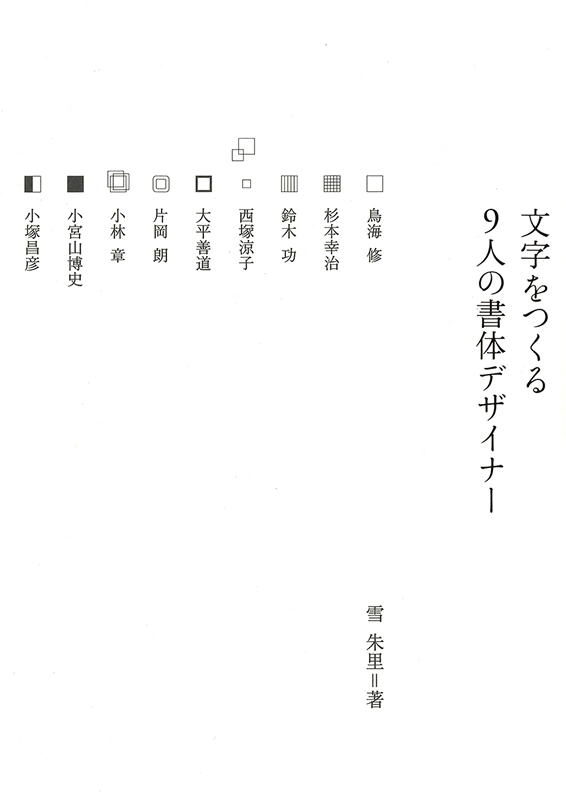




[注]