連載スタート当初から何度も登場している「種字彫刻師」という言葉。種字彫刻師は、文字どおり「種字」を彫るひとだ。かつて活版印刷にもちいる金属活字のおおもとは、ひとの手で彫られていた。彫刻師は、「種字」と呼ばれる凸型の文字を原寸・左右逆字(鏡文字)で彫った。この種字を父型にして型をとり、凹型の母型がつくられたのだ(さらにそれを型にして、金属活字がつくられた)。メッキの技術を応用してつくる「電胎母型」といわれるものだ。
種字には黄楊の木をもちいる場合と、地金(鉛・錫・アンチモンの合金)をもちいる場合があり、地金種字は木の場合に比べ、後の工程がすくなくなった。彫刻師には、どちらも手がけるひともいれば、どちらかのみを手がけるひともいた。たとえば東京築地活版製造所の種字彫刻師・安藤末松は木彫、岩田母型製造所の種字を彫っていた馬場政吉は地金彫りの名人といわれた。

地金の種字。馬場政吉の弟子・清水金之助(1922-2011)彫刻
活字は、デジタルフォントや写植のように使用時に拡大縮小することができない。使用サイズすべての文字を「金属活字」というモノとしてつくる必要があり、そのためには、種字もすべて使用サイズの原寸で彫らなくてはならなかった。
「原寸で」といってもピンとこないかもしれない。
たとえば、亀井忠一が臼井翁に彫らせた「七号活字」は約5.25ポイント=約1.84mmだ。2mm角にも満たない四角柱状の活字材に、左右逆字で、画数の多い漢字なども彫りあげたといえば、そのすさまじさが伝わるだろうか。
ハンコと活字の違うところは、活字は文章を組んで使われるということだ。ゆえに種字は単独で美しければよいわけではなく、どんな文字との組み合わせでも読みやすくなるようにしなくてはならない。すべての文字において、スタイルや幅、高さなどに統一感をもたせなくてはならないのはいうまでもない。
むずかしい仕事であるから、修行にも時間がかかった。多くの彫刻師は、まだ十代のころから小僧として師匠のもとに住み込みして雑用からはじめ、徐々に重要な部分をまかせてもらえるようになっていく。一人前になるまでには10~15年かかるといわれた。
だからこそ、書体ひとそろえの彫刻を注文されるような種字彫刻師は、ひとにぎりの天才――特別な才能と技術の持ち主に限られ、だれもがなれる職業ではなかった。新聞社や出版社、母型屋といった母型の注文者にとって、いかにして腕のよい彫刻師に仕事をしてもらうかは重大事で、あの手この手で抱えこもうとしたという。
彫り師仲間で“名人”と呼ばれる彫師には、決まってパトロンがついていた。雇い主は、彼(彫り師)が企業にとって必要なときには、すすんで金を貸し、酒と博打と女で自縄自縛の破目に追いこみ、彼の才能と生活を資本の虜にしてしまうのが常だった。彼、彫り師によって一つの活字が完成してしまえば、雇い主には、もはや彼が不用(ママ)なのだ。
これは作家や愛書家にファンの多い精興社書体[注1]を彫った種字彫刻師・君塚樹石のインタビュー記事に書かれた一節である。[注2]樹石は明治33年(1900)9月、東京・牛込で生まれ、尋常小学校を卒業した14歳で石渡栄太郎に弟子入りして、種字彫刻師の世界に入った。大正2年(1913)のことだ。

種字彫刻師・君塚樹石(1900-1970)
(『デザインジャーナル』1969年4月15日号、現代企画社)
はやくから頭角をあらわし〈あたしの親方が、お前は、三〇過ぎたらもうお前の右に出る者はないだろうって親方がそう言っていました。あたしはまたうぬぼれが強くて、きかない気だったから、なあに、そのときは二〇ちょっとだったけれども、いまだってだれにも負けやしねえ、こう思っていましたよ〉[注3]という勢い。事実、20代で読売新聞や東京日日新聞(後の毎日新聞)の種字を彫ったという。昭和3年(1928)ごろから精興社の仕事を手がけるようになり、その書体とともに名人として名を残した。
樹石のような腕のよい種字彫刻師は限られた存在で、〈活版印刷会社にとって“社の興亡”にかかわる存在〉[注2]だった。だからこそ、種字を必要としていた会社は、仮にどんなに気むずかしくわがままな職人だったとしても、自社の仕事をやってもらおうと必死に抱えこんだのだ。

最後の種字彫刻師といわれた清水金之助の彫刻風景(2010年ごろ)。マッチ棒ほどの地金の軸をルーペでのぞき、くるくると回しながら原寸・逆字でまたたくまに種字を彫り上げた
※出典のない写真はすべて筆者撮影
[参考文献]
- 「『心で書く』彫り師 名人・君塚樹石一刀彫りの周辺」『デザインジャーナル』(現代企画社、1969.4.15)
- 矢作勝美「活字書体設計の苦心 君塚樹石・青木勇氏にきく 精興社タイプの完成とその背景」『印刷界』148号(日本印刷新聞社、1966)



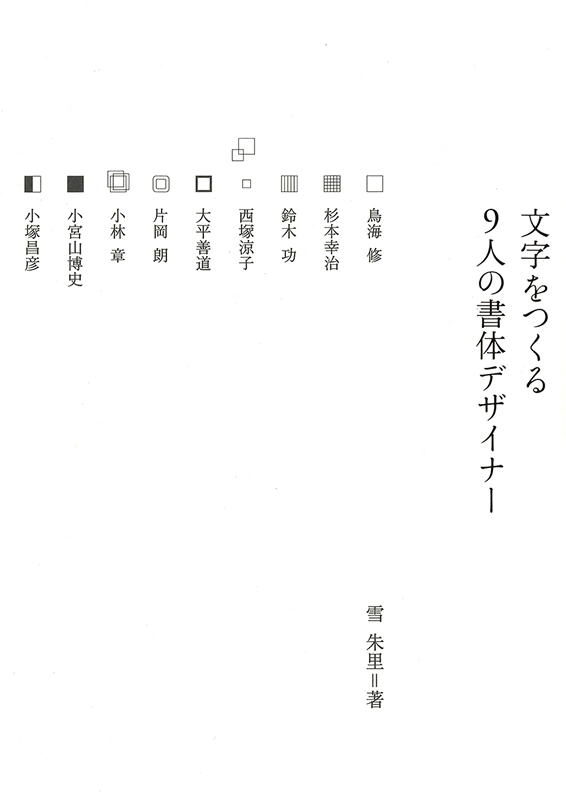





[注]