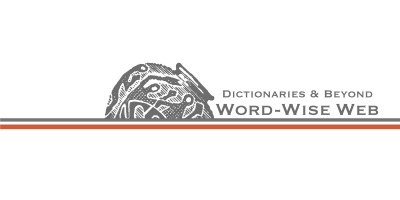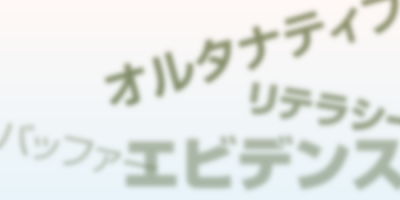近ごろ、あまり夢を見なくなった。
いや、見てはいるのだ。ただ、ほとんど記憶に残っていない。夜中にふと目ざめて、あ、いま、夢を見ていたな、と思う。その瞬間には、どんな夢だったか、確かな記憶があるような気がする。でも、朝になってみると、夢を見ていたという感触があるだけで、どんな夢だったかは、皆目、忘れてしまっている。
夢の残り香。そんなふうに呼びたくなるようなものだけが、心の底に残っている。
かと思うと、真っ昼間に突然、夢を感じることがある。たとえば、確かに交わしたはずのだれかとの会話。それをなんとなく思い出しているときに、急に「あれは夢だったのではないか」と思えてくるのだ。あのひとがあんなところにいるわけはない。あんなことをしゃべるはずがない。そう考え出すと、それまで鮮明な記憶だったものが、あっという間にぼやけてきて、リアリティのない、頼りなくふやけたものと化してしまう。
夢は知らないうちに、ぼくの人生の中に入り込んでいるのかもしれない。ひょっとすると、ぼくがとても大切にしている思い出のいくつかだって、夢の記憶なのかもしれない。そんなことを思ったりもする。
*
『フォスフォレッセンス』は、太宰が自殺する1年ほど前に発表された、短編小説である。主人公の「私」は、自分のことを「夢想家」だという。
「私は、一日八時間ずつ眠って夢の中で成長し、老いて来たのだ。つまり私は、所謂この世の現実で無い、別の世界の現実の中でも育って来た男なのである。」
夢の中には別の生活があり、そこには「この世の中の、どこにもいない親友」もいれば、「この世のどこにもいない妻」もいる。そうして、「夢の国で流した涙」は、この世にまでつながっている。「この二つの生活の体験の錯雑し、混迷しているところに、謂わば全人生とでもいったものがあるのではあるまいか」。
そんな「私」は、ある日、ふとしたことから、現実の世界で「あのひと」が暮らしている家を訪ねることになる……
文庫本にしてわずか10ページ足らず、けっして太宰の代表作というわけではない。が、夢の中から出てきて夢の中へと帰って行くような、この小品の読後感は、忘れられない。一番好きな太宰作品を挙げろと言われたら、『フォスフォレッセンス』と答えるかもしれない、とさえ思う。
*
だから、『太宰治の四字熟語辞典』でも、この作品をぜひとも紹介したかった。しかし、それはできない相談だった。なぜなら、この小品には、四字熟語が登場しないからだ。漢字4文字の連なりを探しても、せいぜい「襲名披露」とか「自粛休業」が出てくるくらい。これでは、さすがに、お手上げである。
でも、それでよかったのだ。四字熟語という刃をふるって太宰に斬り込もうというのは、1つの方法でしかない。太宰に限らず、文学という広大な広がりを持つ世界が、ある1つの方法で覆いきれるはずはないだろう。『フォスフォレッセンス』の存在は、そのことをやわらかに示しているのではないだろうか。
近ごろ、夢をあまり覚えていないぼくにとって、それは夢の実在の証であるのかもしれない。夢が残っている限り、ひとは、物語をつむぐことができるのだろう。