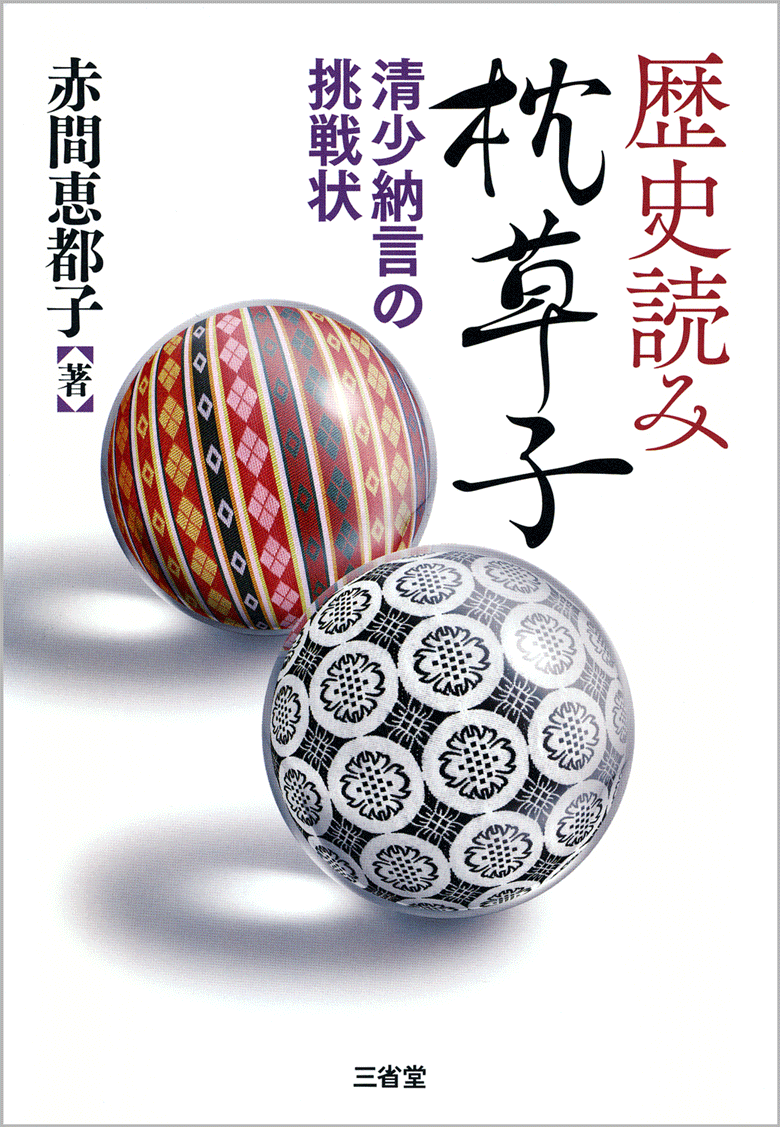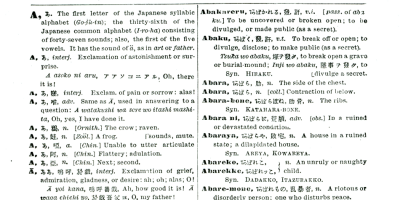前回、『枕草子』は後宮文化の中で生まれた作品だということをお話しました。跋文(ばつぶん)と呼ばれる後書きには、『枕草子』が書かれることになったきっかけが記されています。ある時、中宮定子の兄の内大臣藤原伊周(ふじわら これちか)が一条天皇と中宮に大量の紙を献上しました。天皇はそれに中国の歴史書である『史記』を書写させたのですが、中宮の方では何を書いたらいいだろうかと問いかけたところ、清少納言が「まくらでしょう」と答えたために、自らが筆を執ることになったという事情です。
当時、紙は貴重品で、上質の紙はなかなか手に入らないものでした。定子が時の関白の娘だったからこそ、兄伊周を通じて大量の紙が手元に入ったのです。それが、一人の後宮女房の手に渡ったとなれば、おのずから紙に書くべき内容も決まってきます。清少納言が答えた「まくら(=『枕草子』?)」がどういうものを意味しているか、未だに定説はありませんが、成り行きから考えれば、それが定子後宮の素晴らしさをアピールする役目を担っていたことは間違いありません。
さて、定子の母の高階貴子は漢詩の作文が大変得意な女性でした。平安時代、漢字は男手とも言われ、女性がそれを使って漢詩を作ると世間から非難されるような社会でした。それでも貴子の作った漢詩は、並みの男性貴族の水準を超えており、しばしば朝廷から作文を命じられたと『大鏡』に記されています。
そんな母親の血を引いた中関白家の姫君たちは、女性が漢字を使うことに引け目を感じることなく、存分に男性並みの教養を身につけていったものと考えられます。一方、軽妙な専門歌人であった清原元輔の末娘として生まれ、父親から和漢の教養を十二分に受け継いだのが清少納言でした。つまり、中宮定子と清少納言は文学的素養の面からもぴったりの相性だったと言えるでしょう。だからこそ、定子と出会った清少納言は、水を得た魚のように後宮文化の中でその才能を発揮していったのです。
『枕草子』には、定子を中心に様々な宮廷生活の様子が書き留められています。主人周辺の出来事を記録するのは女房の役目の一つであり、前例を重んじる時代の公的記録として書かれていたのが女房日記でした。『枕草子』もそのような女房日記であると考える見方があります。主人定子の動向を女房の立場から書き留めたという点では、『枕草子』は女房日記の一種だと言えるかもしれません。
ところが、『枕草子』と女房日記には決定的に違う点があります。それは、作品の形態です。日記であれば、その記録的性格から、時間を追って記されるものでしょう。しかし『枕草子』の場合、清少納言が宮仕えする以前から、定子と過ごした最期の年に至るまでの出来事を扱った文章が、時間的な順序も関係なく作品内に偏在しています。さらにそれらの文章が、「春はあけぼの」や「うつくしきもの」など様々な内容形態の文章の間に不規則に入り込んでいるのです。
『枕草子』は定子後宮の記録ですが、時間の流れに沿って記される一般的な女房日記とは異なった形態を持った作品であり、そのことは女房日記とは異なる『枕草子』の文学としての性格を表していると思われます。
それが、『枕草子』を女房日記と単純に呼べない理由なのです。
さて、『枕草子』全体の形態について少し触れることになりましたので、次回は、それについてお話しましょう。