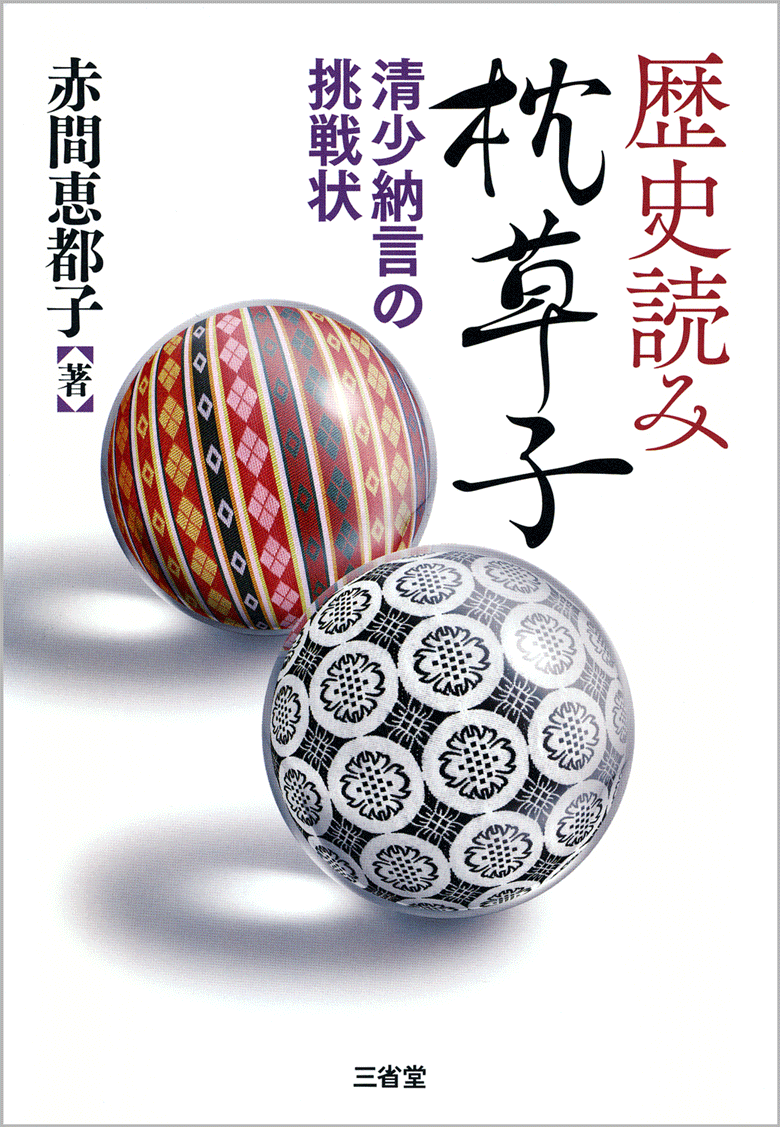中学校や高校で『枕草子』を初めて読んだ方は多いと思います。読んだことがない方でも、「春はあけぼの」の印象的なフレーズは聞いたことがあるのではないでしょうか。昨今は受験科目に古典文学を設定している大学は少なくなりましたが、『枕草子』は古文教材の定番でした。では、文学史ではどのような作品として位置付けられているのでしょうか。答えは、随筆あるいは随筆文学です。
随筆とは、「見聞したことや心に浮かんだことなどを、気ままに自由な形式で書いた文章。また、その作品。」(三省堂『大辞林』第三版)とされています。
『枕草子』には様々な文章が綴られています。四季の代表的な時間帯を選んで描写した冒頭の「春はあけぼの」、初夏の散策の体験を記した「五月ばかりなどに山里にありく」のような文章があります。また、「よろづのことよりも、なさけあるこそ、おとこはさらなり、女もめでたくおぼゆれ(他のどんなことよりも思いやりのあることが、男はもちろん、女もすばらしいと思います)」のように人間関係について批評した文章もあります。さらに、「うれしきもの」「にくきもの」などの人間心理をテーマに取り上げた文章では、作者の感じたこと、考えたことが現代の私たちにも直に伝わってきます。
同様な形式を持った有名な古典として、鎌倉時代に書かれた『徒然草』を思い浮かべる方もいると思います。それもそのはず、『徒然草』には、作者の兼好が『枕草子』をお手本として読んでいることがちゃんと明示されているのです。つまり、中世には『枕草子』は模倣すべき古典としてとらえられていたということですね。
では、平安時代はどうだったのでしょうか。中国から伝来した漢字をアレンジして平仮名が発明されたのは平安時代の始めでした。その平仮名を使って和歌や物語が急速に作られていったのですが、『枕草子』以外に随筆と見なされる作品は一つも現存していません。このような状況について、国文学者の五十嵐力氏は、著書『平安朝文学史』(1937年刊)に“大空に孤高を持したる『枕草子』” と書きました。『枕草子』は文学史上に孤立している特異な作品だという意味です。『源氏物語』が書かれる前に、竹取物語や伊勢物語という同じ種類の文学があった事情とは異なっているのです。
それでは、『枕草子』は中世以降に登場してくる随筆文学とみなされる作品群の先駆けだったのかというと、実はそうとも言い切れません。それは、『枕草子』が随筆とは異なる世界を作品内部に持っているからです。「山は」「河は」といった表題で歌枕(和歌に詠まれる地名)を収集した形の文章は、女房として必須の教養だった和歌の知識を基に書かれています。また、定子後宮での出来事を記録した文章は、主家を称讃する視点でとらえられています。そのような記事が『枕草子』本文の半分以上を占めているのは『徒然草』との大きな違いです。
この違いは何に由来するのでしょうか。一人の作者の意図によって書かれた『徒然草』と違って『枕草子』には、宮廷女房としての作者の立場が作品に大きく影響しています。『枕草子』は清少納言という女性がまったくの個人として書いた作品ではなく、作者が仕えた定子の後宮文化の中で生み出された作品なのです。
作者が後宮文化を代表する女房であれば、その著作が後宮文化を代表する作品となるのは必然的なことであり、それは『枕草子』という作品を規定する重要な要素です。その点から考えると、『枕草子』は当時の文学の中で決して孤立していたとは言えなくなります。むしろ後宮文化の先導的な作品として見なされていたと言えるのではないでしょうか。紫式部が標的として狙ったのも頷けるはずです。
では結局、『枕草子』はどんな作品なのか、これが拙著『枕草子日記的章段の研究』の大きなテーマになりました。次回に続きます。