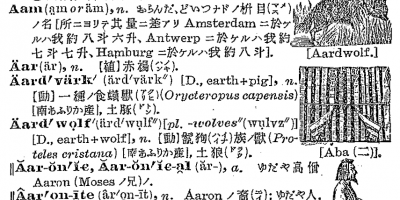表現キャラクタについて話を進めているさなか,前回は唐突に「動物のキャラづけ」を取り上げてしまった。これは言い訳をすれば,表現キャラクタが言うまでもなく他者の行動の記述に関する概念であって,他者の行動の記述に関してこのところ私が,自己投影主義,というよりむしろ反・自己投影主義に対して,一種の疑問を感じているからである。
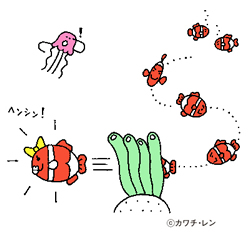
「動物の行動を科学的に記述しようとする際,動物の行動を人間の行動のように記述してはならない」という考えは,一見,疑いを差し挟む余地がないほど正しく思える。「やれ打つな 蠅が手をすり 足をする」のような蠅の「命乞い」は,俳諧の世界では興ある見立てではあっても,ハエの行動を研究しようとする際には認められないということを我々は知っている。「動物の行動を人間の行動のように,動物を人間のように記述してよい」という考えを擬人主義と呼ぶとすると,擬人主義は動物行動の科学的な研究では受け入れる余地がないように見える。
同様のことは,異文化圏の人間およびその行動を記述する場合についても言える。社会言語学者のジョン・ガンパーツ (John Gumperz)によると,イギリスの空港でインド・パキスタン系の職員が「無愛想で非協調的」と誤解されたのは,下降イントネーションの意味がイギリス英語と彼らの英語とでズレていたせいだったという。異文化圏の人間を自身の文化に当てはめてこのように誤解してしまわないよう,研究者は注意しなければならないという警句は,文句なしに正しく響く。
先の擬人主義も含めて,「他者の行動を自己の行動のように,他者を自己のように記述してよい」という考えを自己投影主義と呼ぶなら,行動研究は自己投影主義を完全に否定した上でなければ始められないように見える。
しかし果たして,本当にそうだろうか? 本当にコトはそう簡単に運ぶのか?――私が抱いている疑問は,概ねこういうものである。
こうした疑問を根底に置いて前回述べたのは「「動物のキャラづけ」という一種の自己投影には,その動物に対する理解をゆがめかねない危険な一面が確かにあること」,そして「だがそれでも,キャラづけなしには動物の行動はしばしば記述できないこと」である。
さらに人間の例を付け加えるなら,自己投影が許容されているどころか,それが積極的に求められさえする現場がある。我々はその一端を,「外国人」を日本の病院や介護施設などで就労・研修させ,看護師や介護福祉士の国家試験に合格させるためのサポートや,合格後の勤務のサポートに携わっている方々の調査を通して知ることができる。何を言っているのかというと,日本が2008年度以降,経済連携協定(EPA)に基づいて「外国人」を看護師や介護福祉士の候補者として受け入れているということを言っているのであって,ここで言う「外国人」とは,具体的にはインドネシア人(2008年度以降),フィリピン人(2009年度以降)を指し,将来的にはベトナム人(2014年度以降)をも含むことになる。当然ながらそこにはさまざまな言語的・コミュニケーション的・文化的問題が生じており,それらは日本語教育関係者の調査を通して知ることができる。
たとえば,丸山真貴子氏と三橋麻子氏の調査「外国人介護福祉士にとっての次なる課題――アンケート・インタビュー調査結果からの教材作成の試みと学習法」(『2013年度日本語教育学会秋季大会予稿集』所収)を見てみよう。この調査では,介護福祉士の国家試験に合格して介護施設で半年以上働いた外国人介護福祉士にとって,介助時の状況や被介護者の様子を詳細に伝え引き継いでいく「業務日誌の読み書き」が大きな課題となっていると論じられている。そしてその際,外国人介護福祉士にとっては難しいが必要だとされているのが,被介護者の表情を「ぼんやりした表情」「すっきりした表情」「かたい表情」のように,踏み込んで表現することである。これらの表情表現は,顔の外見に留まらず,内面にまで踏み込んだ表現であり,その内面は自己を投影しなければ推察できない。つまり,介護士には被介護者への自己投影が求められている。
もちろん,看護や介護の現場と行動研究の現場は,さまざまな点で違っている。だが,「記述の正確さが重んじられねばならない」という一点では,両者は共通しているはずである。その現場の一方で積極的に求められている自己投影主義が,他方において厳しく戒められるというのは,おかしなことではないだろうか?
前回述べたように,動物の行動記述において,自己投影主義への戒めは厳密には守れない。そして上で述べたように,異文化の人間の行動記述においても,自己投影主義はそもそも常に厳密に守るべきものではないのだろう。