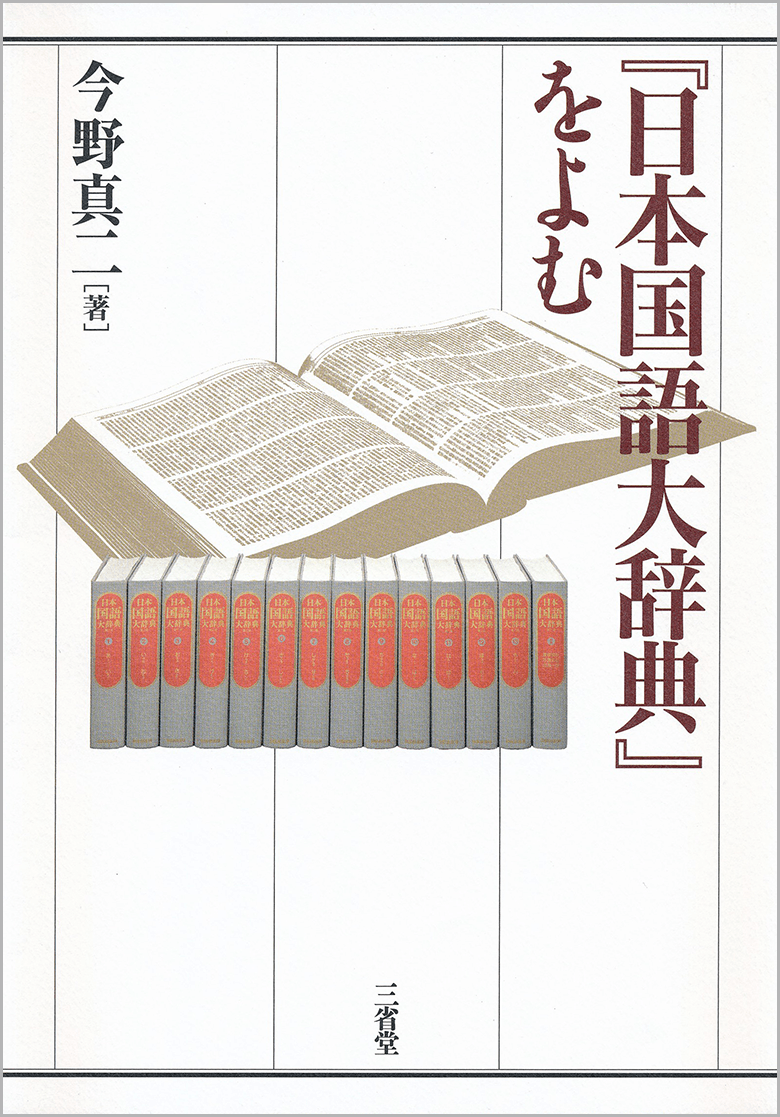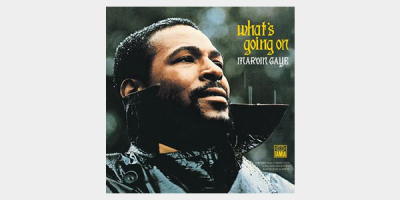『日本国語大辞典』は見出し「あられ」の語義をまず「空中の雪に過冷却の水滴が付着した、白色不透明な、小さな粒状のもの。冬期に限るが、古くは、夏に降る雹(ひょう)を含めてもいう」と説明しています。最近は東京23区では雪が降ることもあまり多くはないように思います。雪が降らないのですから、あられを見ることも少なくなってきているかもしれません。また「さいの目に小さく切って干した餠。いためるか、油で揚げるかして食べる」あられもちを食べる機会も減ってきているように感じます。
そうなると、「あられに切る・あられに刻む」ということもわからなくなるかもしれません。『日本国語大辞典』は「あられに切る・あられに刻む」を次のように説明しています。
あられ に=切(き)る[=刻(きざ)む]餠などを細かく、さいの目に切る。*西洋道中膝栗毛〔1870~76〕〈仮名垣魯文〉一一・下「のし餠をあられに刻むやうに」*児童のお弁当百種〔1931〕〈小林完〉五・一九「玉葱は細かくアラレに刻み」
「あられに切る・あられに刻む」がわからなくなってくると、次のような語もわからなくなる可能性があります。そもそもこれらの食べ物はあまり見かけなくなっているように思います。
あられ‐かん【霰羹】〔名〕あられに切ったヤマノイモを混ぜて作ったようかん。
あられ‐しょうが[‥シャウガ] 【霰生姜・霰生薑】〔名〕ショウガをあられに切って酢に漬けたもの。浸し物や、なますなどの上にかけて薬味にする。
あられ‐どうふ 【霰豆腐】〔名〕さいの目に切った豆腐。また、そのような豆腐を油でさっと揚げたもの。
見出し「あられどうふ」の説明では「さいの目に切った」という表現が使われていますが、「あられどうふ」の「あられ性」(=あられが表象するもの)を説明するのであれば、「あられに切った」と説明すべきではないでしょうか。辞書の語義記述を辞書全体として統一することは難しいことと思いますが、それでも、辞書が「ことばの宇宙」をバランスよく、筋が通ったかたちで具現するためには、必要なことともいえるでしょう。いろいろな「方向」から検索をかけていくことによって、相当程度まで記述を統一することはできると思います。
あられは模様としても早くから使われていたと思われます。
あられ‐じ[‥ヂ]【霰地】〔名〕織り紋の名。あられ小紋を織り出した織物。あられ。あられのて。*堺本枕草子〔10C終〕六〇・あやのもんは「あやのもんは、あふひ。あられ地」*源氏物語〔1001~14頃〕行幸「むらさきのしらきり見ゆる、あられぢの御小袿(こうちぎ)」*久安百首〔1153〕「衣手ぞさえわたりけるあられぢは我が裳(も)のきしに着ればなりけり〈安芸〉」
あられ‐こもん【霰小紋】〔名〕(「あられごもん」とも)織物や、染め物の模様の名称。あられの模様の小紋。石畳の総紋の細小なものをいうが、近世では鮫(さめ)小紋などの規則正しく配列したものをいい、裃(かみしも)などに多く用いた。あられの方(ほう)。*咄本・当世手打笑〔1681〕一・七「色は花色にして、あられごもんをつけたといへ」*雑俳・柳多留‐一一三〔1831〕「霰小紋に染むらの天の川」*慶応再版英和対訳辞書〔1867〕「Engrail 刻目ヲツケル。霰小紋ヲツケル」
『日本国語大辞典』で「あられ」から始まる語を探していて、次の語に遭遇しました。
あられ‐がゆ 【霰粥】〔名〕(魚肉をあられに見立てて)タイ、スズキなどの魚肉を細かく刻んで作ったかゆ。*風俗画報‐二六一号〔1902〕飲食門「霰(アラレ)粥 鯛又は鱧の類の正肉(しゃうみ)を取り之を摺肉(すりみ)にし」
あられ‐そば 【霰蕎麦】〔名〕かけそばの上に、煮た貝柱をのせ、あぶったのりをふりかけたもの。あられ。*風俗画報‐九三号〔1895〕人事門「玉子とじは蕎麦を鶏卵にてとじる。あられ蕎麦は貝の柱を入」
「あられがゆ」は「魚肉をあられに見立てて」と説明されていますが、「魚肉を細かく刻んで」がつまりは「あられに刻んで」ということで、〈あられに刻んだ魚肉で作ったかゆ〉という説明がいいのではないでしょうか。筆者はおそばが好きなので、「あられそば」はおいしそうだなと思いましたが、「あられそば」の「あられ性」はどこに見出せばいいのでしょうか。「煮た貝柱」が「小柱」であれば、それが「あられ」なのだろうかなどと、あれこれ考えてしまいます。
あられが降らなくなると「あられそば」がわからなくなる、というと「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいですが、人々の具体的な日常生活とことばが結びついていることは言うまでもなく、ことばの歴史は人々の歴史そのものと言ってもいいのかもしれません。