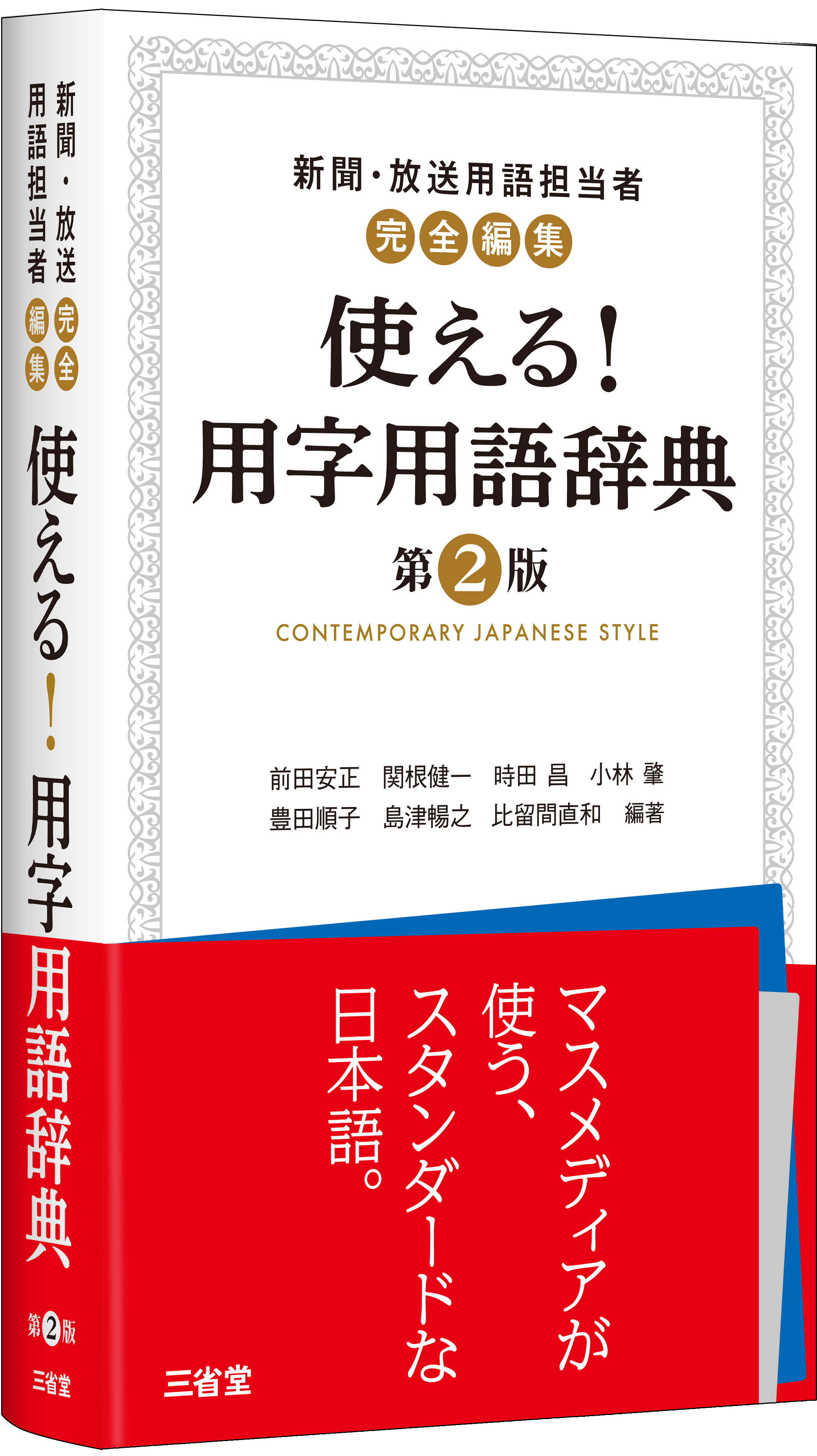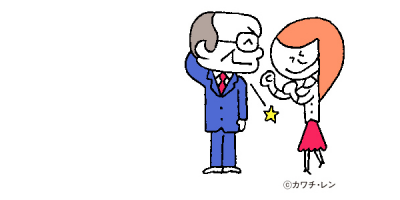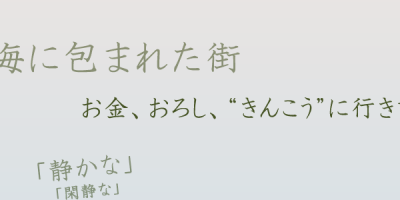『使える!用字用語辞典』の編著者の中で、私は唯一、放送、特にアナウンサーの立場から関わらせていただきました。新聞の言葉を「(紙面に残る)文字の言葉」とするなら、放送は「(その場で消えてゆく)音声の言葉」とも言えるでしょう。特に、放送局に入社してから35年間、一貫して情報・スポーツ・報道の生放送番組において現場で取材したことを声で伝え続け、アナログからデジタルの技術革新による変化を目の当たりにして若手アナウンサーの育成にも取り組んできたことは、本書を執筆する上での基本となりました。
さらにその後、子会社に出向してカルチャースクールの経営を担いながら、就職活動に臨む学生や、電話やメールで顧客対応をするカスタマーセンターの社員、専門知識の資格取得を目指してプレゼン試験に備える主婦、職務質問を苦手とする若い警察官……といった、世代や立場の違う方々に直接レッスンを行ってきました。これが、正誤だけでは判断しきれない言葉の使い方のグレーゾーンを意識する視野を広げることにつながり、改訂作業を行う一助になったと考えています。
話し言葉も、昭和・平成・令和と大きく変化しています。放送における「音声スピード」も速くなり、情報量も多くなって、理解を補うために画面上のテロップ(文字表記)もにぎやかになりました。一方でインターネット上の動画がテレビというメディアを席巻する中、突如として新型コロナ感染症が世界を襲い、誰もが行動を制限され、マスクの着用を余儀なくされてSNSが普及、短文の文字でのコミュニケーションが加速度的に広まりました。まさにそんな中で高校時代を過ごし、戸惑いながら恐る恐る大学生活に入り、社会に出ていく覚悟がまだ定まらない中で就職活動に対応しようとする学生たちを相手に「自己PR」や「面接試験対策」の授業を手掛けてきたことは、私自身が多くの発見を得ることにつながりました。驚くほど大量の情報を浴びる現代の日常生活は、言葉の一つ一つを深く理解し、味わって使ってみようとする機会を若者たちから奪っているようにも感じます。
リアルな若者に接して印象に残ったことをいくつか記してみましょう。
- パソコンやスマートフォンの画面を見るよりも、本や新聞を読む習慣が少ない。
- 文章は「ペンを持って書く」よりも「スマホやPCのキーを打つ」ことの方が多い。そのためにじっくり腰を据えて「書く」ことへの苦手意識が非常に強くなっている。
- 日常会話での言葉遣いを正してくれる、(私のような?)おせっかいな大人が身近にいない。(大人はみんな忙しいし、ハラスメントに感じられたくもない。)
- 社会における常識やマナーは、ネットで検索。(だから見知らぬ相手への対応の仕方がわからないし、自信が持てない。)
- AIによる手軽な回答やフィルターバブルによって、蓄積する知識のバランスが偏りやすい。
そんな時代に私が今一番感じるのは、口語と文語の言葉遣いの境目が曖昧な時代に入ってきた、ということです。SNSで目にする若者同士の会話や造語がスマホの画面を覆うようになり、自分より年上の人の言葉遣いから慣用句の知識を学ぶことが減り、紙の辞書を引いて言葉の意味を確認するという勉強方法がレトロ扱いされてしまうほどです(実際、辞書を手渡すと目的の言葉にたどり着くまで何分もかかる学生は多い)。例えば志望企業に提出するES(エントリーシート)を書くよう宿題を課してみると、書き言葉なのに「なので」という接続詞が多用されていたり、「高校生ぶりに対面で話ができるようになり」といった表現を使う学生が多かったり、それを直接口頭で指摘すると「私が言いたいのは違くて……」という反応が返ってきたりします。ですから第2版の改訂にあたっては、若者が「本来の日本語」にきちんと向き合う気持ちになった瞬間に、すぐに役立つ親切な辞書であって欲しいと考え、躊躇なく新たな項目や説明を加えたりしました。(本書「なので」「~ぶり」「ちがう」参照)
何事も、「基本」は大切。日本語としての本来のルールさえしっかり身につけておけば、たとえ運用の仕方に時代の変化があったとしても、状況に合わせて自分の判断で「言葉の安全運転」ができるものです。本書を一冊、手に取りやすい場所に置いてみてください。こんな時代だからこそ、日常生活で流れていく大量の言葉を観察する意識を持ってみませんか? 「ん?」と心に引っ掛かる言葉遣いを目にしたり耳にしたりした時、すぐに確認するツールとして本書を使っていただければ、皆さんが使う日本語の精度は間違いなく上がります。
若い読者には特に次の3点をお勧めします。
- 同音異義語の文字(漢字)を確認すること
- 「漢語・和語・外来語のどれを使うことで自分が伝えたい表現(ニュアンス)に近づくか」をもっと考える——あなたが言いたい言葉の選択肢は他にもある可能性がある。
- いつも使っている言葉が本当に正しいか(仲間内でない人に伝わるか)——自分で自分を疑って本書の「×」表記の内容を確認するだけでも、日本語のブラッシュアップができるはずです(これ、私の習慣でもあります)。
新聞やテレビを“オールド・メディア”と言うなかれ。“トラディショナル・メディア”が使ってきた日本語を知ることは、様々な世代とのコミュニケーション上の礎となりますし、また自分の思考をしっかり確認・整理すること、ひいては日本の文化を守ることにもつながります。「自分が話し、書く言葉を大切にすること」で、“伝わる”日本語を実感してください。日常生活がとても楽しくなるはずです。ぜひ一緒に楽しみましょう!