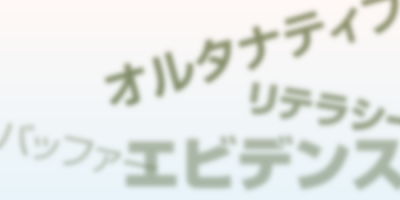日本が、欧米の文化を本格的に導入しようと動き始めた幕末から明治期にかけて、現在私たちが馴染んでいる各種学術領域やそのための言葉も移入・翻訳されました。大学における学部学科やその分類などの基礎が模索され、据えられたのもこの時期です。
これは想像してみるしかありませんが、これまで自分たちが使う言語のなかになかったような(あるいはあっても意識していなかったような)、未知の発想、未知の概念を、しかも異語で書かれたものを、なんとかして日本語に移し入れるというのは、いったい全体どういうことだったのでしょうか。
現在、私たちは先達がつくってくれた、そして目下もつくられつつある、さまざまな辞書や事典を使うことができます。身の回りに当たり前のようにあるために、ついそのありがたみを忘れそうになりますが、もし辞書がなかったらと想像してみると、その便利さが身に沁みてきます。
例えば、英和辞典のように、異語と母語を対応してみせてくれる辞書が手元(手元どころか世の中)になかったら、誰かが「英語のこの言葉は、日本語ではこの言葉と対応する」と調べ上げておいてくれなかったら、異語で書かれた本を前にして、どうすることができるでしょうか。幕末から明治期にかけて欧米文化に遭遇し、咀嚼しようとした人びとは、まさにそうした助けが乏しい状況で、学術なら学術に向き合ったわけです(中国語と英語を対応させた華英などを利用できたとしても)。
今回、本連載で読んできた「百学連環」講義は、そうした文化の大転換期を生き、大きな役割を果たした人物の一人、西周が私塾で門下生に向けて欧米学術の全貌を示さんとして行った講義でした。
西先生は、欧米の学術を文字通り身をもって受けとめ、従来の漢籍の教養をフル活用しながら、しかしそこには収まりきらない知識や発想に対して、新たな日本語を創造し、ときに工夫を重ね、現代にいたるまで使われ続けることになる言葉の礎を築いたのでした。この「百学連環」のとりわけ「総論」は、そうした営みのエッセンスが煮詰められた稀有な記録と言ってよいと思います。
弟子の永見裕が筆録した「百学連環」講義の全体を読んでいると、「ともかく、彼の地で行われている学術なるものの全体を見渡してやるぞ」という意気込みが伝わってくるようです。これは、生半可な興味や好奇心では、とてもそこまでできるようなことではないとも思います。
もちろん、未知のものごとに接するにあたり、その全容を確認することは、学術に限らず重要な取り組み方です。全体を見ずに部分だけで物事に取り組むのは、言うなれば自分の手しか見ずに麻雀を打ったり、自分の手しか気にせず将棋やチェスを指すようなものです。あるいは、もう少し学術寄りの譬えをするなら、ある単語の意味を、その単語だけから理解しようとするようなものといってもよいかもしれません。
百学を見渡してみるということは、上の譬えに乗っていえば、麻雀の場を見ること、将棋やチェスで相手の指し手や盤面を見ること、ある単語を他の単語との関係の中で見ようとすることに相当します。ある学術の位置や価値を知るには、学術全体の様子、他の諸学術との違いを確認してみるに越したことはない、というわけです。
これは考えてみれば当たり前のことのようです。しかし、実際にどうかといえば、とても自明視できる状況ではないとも思うのです。そもそも私たちは、小中高あるいは大学や専門学校などでなにかを学ぶ際、学術が複数の科目に分かれていることについて、「なぜそうなっているのか」と、考える機会は存外少ないのではないでしょうか。
例えば、国語と数学が別の科目であることは当たり前のことであり、どうかすれば両者はまるきり関係のないものだ、という理解(勘違い)がまかり通っているように思います。
他方、本連載で「エンサイクロペディア(Encyclopedia)」や「エンチクロペディー(Enzyklopädie)」について検討した際、こうした名前を冠した講義では、学術全体や当該学術領域全体に関して広く見渡すことが目指されているという様子を見ました。法律を解説する講義の冒頭で、学問論が展開されている例などもありましたね。
そして、西先生が「エンサイクロペディア」を「百学連環」と見事な言葉で受けとめてみせたことに現れているように、諸学がどのように「連環」しているのか/いないのか、という問題意識がそこにはありました。
学術史を追跡していると、ある時期まではこうした学術全体を見渡そうとする仕事が少なからず存在していたことが分かります。しかし、諸領域の専門分化が進めば進むほど、そのような試みは稀になってきました。
そのなれの果てが、私たち自身の受けた教育に現れた諸学術の姿にあったと言えるでしょう。それぞれの学術領域が分かれてあることは、はなから当然のことに過ぎず、なぜそのように分かれているのか、それぞれの学術はどのように連環しあっているのかという視点や問題意識はほとんど失われているように思われます。
果たしてそれでよいだろうか。大丈夫だろうか。いや、むしろ細分化が進めば進むほど、知識が増えれば増えるほど、その全体を見渡すための地図が必要なのではないだろうか。一つにはそんな関心から、「百学連環」をじっくり読んでみるということに取り組み始めました。そこには、新たな地図をつくるための手がかりがあるのではないかと思ってのことです。
首尾のほどは、ここまでの道のりをご覧いただいた読者諸賢に判断を委ねるほかはありません。私自身はといえば、西先生がやってみせたような「百学連環」という観点に立った学術論というものは、やはり必要だという思いを改めて強くしたところです。
それも、できれば学術に携わる人びとの間だけでなく、それこそ義務教育の課程も含めて、すべての人が一応は「こういうことだ」と理解できるような、必要になるつど開いて見られるような、そんな形であらわされた学術の地図があればいいのにと思います。仮にそうした地図をつくる場合には、「百学連環」講義で整理されたことも解かれずに終わった問題も含めて、重要な手がかりを示してくれるはずです。
そのような底意地に加えて、本連載にはもう少し地に足のついた目的もありました。それは、「百学連環」のテキストを、手軽に読める形にすることです。これは学術に携わる人であれば、一度は眼を通しておきたいテキストだと思うからです。
いえ、「百学連環」は、『西周全集』第四巻に収められていますから、その気になれば図書館などで読めます(ついでに申せば、この第四巻は、古本でなかなか手に入らない本の一つです)。
しかし、注釈なしにそのまますんなり読めるかというと、そうもゆかないものです。できれば、この文章を手にしやすくすると同時に、現代の読者にも読みやすい形にしたいと考えた次第です。埋もれかかった古典をもう一度手に取り直し、埃を吹き払って現在の眼で見直してみること。少し格好をつけて言うなら、これはそんな人文学の試みでもあったわけです。
もっとよい適任者がいらっしゃるはずであるところを、私のような者がしゃしゃり出ることになったのは、巡り合わせの悪戯でありました。
さて、最後になりましたが、このような連載に快く場所を提供していただいた三省堂のみなさまにこの場をお借りして篤く御礼申し上げます。
編集部の荻野真友子さんにこの企画のお声かけいただいた折りには、よもや足かけ3年も続くとは思っておりませんでした。なにしろ「百学連環」の「総論」は短い文章ですし、もう少しさっさと読み進んで、せいぜい1年もあれば終わるだろうという見込みでした。ところが、読めば読むほど調べることが出てきて、気づけばこのような長期連載となったのは、まったく見通しが甘かったというしかありませぬ。とんだ遅読であります。毎週の連載にあたっては、荻野さんをはじめ、木宮志野さん、山本康一さんのお世話になりました。ありがとうございます。
また、ここまでお付き合いくださった読者のみなさまにも、心から感謝いたします。twitterその他を通じて、「読んでいますよ」とお声かけいただいたことは、どれほど励みになったことでしょう。ありがとうございました。
というわけで、これにておしまいです。機会がありましたら、またどこかでお目にかかりましょう。ご機嫌よう、さようなら。