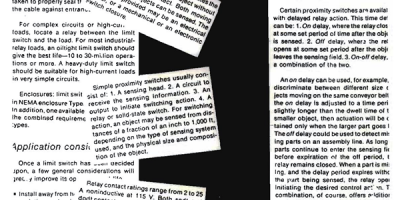前回は、ウィリアム・ハミルトン卿による学問の定義が引用されたくだりを読みました。そこでは、学問とは「物事の根源・由来から押さえて、その真理を知ること」だと述べられていたのでした。
このハミルトン卿による定義を見て思い出されるのは、古典ギリシアにおける学問観です。西洋哲学の歴史を繙くと、多くの場合冒頭に古典ギリシアの話が出てきます。それも、いわゆる「ソクラテス以前」と言われる人々、タレスは万物の源を水と言い、アナクシメネスは空気だと言い、云々という話です。
この人たちは、ときに哲学を始めた人々であると説明されます。ここで「哲学」とは、森羅万象、あるいは宇宙(世界)について知ろうとする営みのこと。いまで言うところの科学も含まれています。
タレスを筆頭として、アナクシメネス、ヘラクレイトス、エンペドクレス、アナクサゴラス、パルメニデスといった人々は、それまでのように神話によって自然現象を擬人的に説明しようとする態度から一線を画して、それとは別のところに説明を求めたのでした。タレスが言ったとされる万物の原理は水であるという説明の仕方はその例です。
実は、こうした見立ては、アリストテレスによるものです。彼は『形而上学(τα μετα τα φυσικα)』の冒頭で、自分以前の思索家たちが、宇宙や自然の成り立ちをどのように説明してきたかということを整理してみせています。それは一種の哲学史であり、後の哲学史がタレスから始まるのも、言ってみればアリストテレス先生の見立てをそのままなぞっているからです。
それはさておき、そのアリストテレスは、万学の祖とも呼ばれるほどの人で、あらゆる学術領域について思索を巡らせています。その彼が、なにかが存在しているとはいったいぜんたいどういうことだろうかという問題に取り組んだのが、先に名を挙げた『形而上学』なのです。
この書物の中で、アリストテレスは、事物について驚きを感じることから、人は何かを知りたいと欲するようになると述べています。「これはなんだろう?」と不可思議に思うからこそ、そのことについて知りたくなるというわけです。
このとき、「なんだろう?」と感じた対象について、その原理・原因を見極めることこそが、その対象を真に知ることであり、それを彼は学問と呼ぶのです。詳しく見てゆけば、アリストテレスはいろいろ面白いことを言っているのですが、ここではこのくらいの掴み方でよいでしょう(さらに知りたい方は、『形而上学』第1巻や『ニコマコス倫理学』第6巻をご参照あれ)。
ハミルトン卿は、アリストテレスをよく読んでおり、前回ご紹介した『論理学講義(Lectures on Logic)』でも、かなりの頻度でアリストテレスの著作を引き合いに出して議論を展開しています。おそらく彼の学問の定義もまた、アリストテレスの定義を下敷きにしていると思われます。
西先生が、そうした気配をどこまで感じていたかは分かりません。ただ、もし西先生が、ハミルトン卿による学問の定義を、『論理学講義』から直接引用したのだとしたら、嫌でもアリストテレスの名を目にしたと思われます。しかし、少なくともいま読んでいるくだりでは、直接アリストテレスの名は見えません(西先生がアリストテレスの名前を記すのは、いま読んでいる「総論」の後、各論で致知学〔論理学〕を解説する段になってからです)。このことは、なにを示唆しているのか。「百學連環」を読み進めてゆくなかではっきり見て取れたら、と念じております。