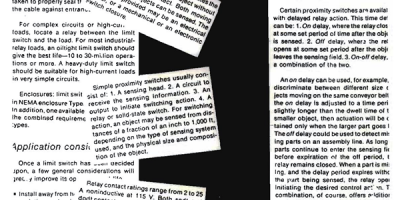学術とはなにか。おおまかには、前回まで見てきたような来歴があるということでした。続いて以下では、学術についてさらに詳しい検討がなされます。例によって、まずは大きく掴んでおいて、だんだんと細部に入ってゆくわけですね。
では見てみましょう。まずは「学問」の検討から。
古昔英人Sir William Hamiltonなる者學問と云ふを區別して云へる語にScience is a complement of cognitions, having, in point of form, the character of logical perfection, and in point of matters, the character of real truth. の如く知ることの積ミ重りの意味なりと雖も、徒らに多くを知るのみを以ては學問とはせさるなり。其源由よりして其眞理を知るを學問と爲すなり。
(「百學連環」第2段落第13~14文)
訳す前に少し補足します。ここに引かれている英文には、いくつかの語に対して英文の左側(原本は縦書き)に日本語が添えられています。どの語にどんな日本語が添えられているか別途記しておきます。
complement 積重り
cognitions 知るコト
in point 目的
logical 致知上ノ
perfection 充分ナルコト
matters ケ條
real truth 眞理
(ただし、原文で「コト」は合字表記=「ヿ」U+30FF)
また、「乙本」の同じ箇所を見ると、上記「甲本」とは違った日本語が添えられています。
cognition 知識
haibing 慣習
character 性質
haibingというのは、引用文(甲本)中のhavingに当たる語で、「乙本」では、このように転写されたようです。
さて、それでは上のくだりを、英語も含めて訳してみます。
昔、ウィリアム・ハミルトン卿というイギリスの人が、学問を定義して次のように言った。「学問とは、認識〔知識〕を補って完全にするためのものであり、形式の観点からは論理が完全であるという性質を、内容の観点からは真理という性質を備えている」と。このように、知ることが積み重なるという意味ではあるが、ただ知識ばかり多くても学問とは言わない。物事の根源・由来から押さえて、その真理を知ることを学問というのだ。
内容を検討をする前に、関連する事柄を確認しておきましょう。
ここで引用されているウィリアム・ハミルトン卿(Sir William Hamilton, 1788-1856)は、グラスゴー生まれのスコットランドの哲学者。しばしば「スコットランド常識学派」と分類されています。
引用文は、ハミルトン卿による『論理学講義(Lectures on Logic)』に見えます。
西先生が引用している箇所を改めて『論理学講義』から引用しなおしてみましょう。なぜそんなことをするのか。理由はすぐ後で述べます。
A Science is a complement of cognitions, having, in point of Form, the character of Logical Perfection; in point of Matter, the character of Real Truth.
(Sir William Hamilton, Lectures on Logic, p.335、ただし太字強調は引用者による)
これはハミルトン卿が没した後に編集された『形而上学・論理学講義(Lectures on metaphysics and logic)』の第2巻として刊行された書物です。この講義集は、第1巻が『形而上学講義』で、当初は全2巻で構想されていたようです。後に全4巻になっています。
ここで参照したのは1860年版です。どこまでが編者たちの手によるものかは分かりませんが、ご覧のように「百学連環」での引用とは若干違っていることが分かります。太字にしたのが該当箇所です。
違いを具体的に整理しておきましょう。「百学連環」におけるハミルトン卿からの引用文が、『論理学講義』と(印刷の上で)違っている点を並べてみます。
a) 文頭のScienceに対する不定冠詞がない。
b) Form, Logical Perfection, Matter, Real Truthの語頭が小文字。
c) セミコロン(;)がカンマ(,)になっている。
d) Matter(単数形)がmatters(複数形)になっている。
「百学連環」が講義録であることを思い出す必要があるかもしれません。西先生が口頭で語り、それを永見裕が筆記したのが、ここで読んでいる「百学連環」でした。
そう思うと、bとcは、話し言葉では見えなくなってしまう要素ですから、引用元と違っていても無理はありません。aは、西先生が読み落としたのか、永見氏が聞き落としたのか。dの単数形/複数形は、口にしてみれば分かりますが、耳から聞いて取り違える可能性は低そうです。つまり、西先生が複数形で読んだのだろうと推測できます。
実際のところどうなのか。「百学連環」が収められた『西周全集』第4巻には、講義をするにあたって先生が書きおいた「覚書」が、筆跡もそのままに収録されています。その「覚書」にも、ハミルトン卿の引用がありました(313ページ)。これを見ると、永見氏が筆写しているのとそのまま同じ文章が書かれています。
ということは、西先生自身が、このハミルトン卿の文章をどこかから「覚書」に写す際、こうした原文との違いが生じたということになりそうです。
なんだか重箱の隅をつつくようで恐縮ですが、引用元と違っていてけしからんといった話ではありません。前回のScioとars artisの件と同様、こうした書きぶりの一見些細に思える違いに、思わぬ手がかりが潜んでいるかもしれません。ひょっとしたら、西先生がどんな文献を参照しながら講義をしているのかといった様子を垣間見ることもできるのではないか。そう思って立ち止まってみたのでした。
*
者=者(U+FA5B)
*