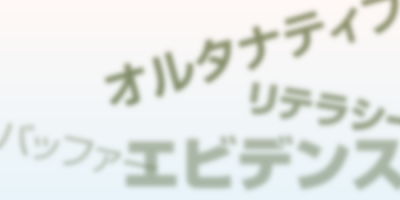前回、「不立文字」に話が及び、今回はそれが敷延されます。
併シ全く不立文字と達磨の説も既往將來の工夫もなく、餘りに過きたる語にして、適宜とも爲しかたし。然れとも達磨以來儘眞理を講究する人の出て來り、其後チ随王通、文仲子なとの如きは聊か眞理ヲ知るものといひつへし。
(「百學連環」第36段落第4文~第5文)
この段落はまだ続きますが、ここで一旦区切ります。「儘」には、「マヽ」とルビが添えられています。訳してみましょう。
しかし、不立文字と達磨の説は、過去や未来への工夫があるわけでもなく、あまりにも行きすぎた語であって、適切とは言い難い。とはいえ、達磨の後に、真理を探究する人がまま現れて、後には随の王通(文中子)などは、いくぶん真理を知っているといえるだろう。
前回見た達磨のものとされる「不立文字」の論について、西先生は評価を与えています。「不立文字」とは、物事を認識する際、文字に立てないという考え方でした。しかし、それはそうかもしれないが、これでは後にも先にもしようがないではないか、という次第。
では、達磨の後はどうかというので、話は中国の文人たちに及んでゆきます。まずここで言及されているのは、文中子。これは随の時代の人で、名は王通(584-617)。彼の言行録『中説』が知られています。
西先生は、文中子は、いくらか真理を知っているだろうと評していますが、この説明だけではその真意は分かりません。続きを見てみることにしましょう。
其餘以前の儒者たる唯徒らに書籍上の論にして、更に眞理に就くもの鮮なしとす。蘇長公及ひ周茂叔の如きは全く佛にして、卽ち語録の學派なり。{語録なるものは不立文字の意より來りて文章に就て論することなく、眞理を講究せし語を録せしものなり。}宋の程子等の如きに至りては、語録なるものを大に制せり。後チ明の薛瑄、陽明の如きも亦其流派とす。
(「百學連環」第36段落第6文~第9文)
{}に入れた語は、割り注として印刷されているものです。現代語にしてみます。
その他、それ以前の儒者はどうかといえば、ただいたずらに書籍の上での議論をしており、真理に関するものは少ない。蘇長公や周茂叔などは、まったくもって仏教である。つまり、語録の学派だ。{語録というのは、不立文字の意から来るもので、文章について論ずるのではなく、真理を探究する語を採録したものである。}宋の程子に至っては、語録をよくものにした。後の薛瑄や陽明などもまた、その流派である。
では、他はどうか。ここで西先生が「儒者」、儒教に関わる人びとについて検討しようとしていることが分かります。そして、言ってしまえば机上の空論が多いと批判しているわけです。これは、もちろんここしばらく読んでいる実験や実証の話を念頭に置いてのこと。それを踏まえて言い直せば、実験や実証とは関係なく、儒者は本の上だけで話をしているという指摘になりましょうか。
そこで何人かの名前が並べられています。まず、蘇長公と周茂叔です。蘇長公は、宋の文人、蘇軾(1036-1101)、号を東坡居士と言いました。また、周茂叔は、周敦頤(1017-1073)で号は周濂渓。北宋時代の思想家です。『太極図説』などで知られています。これは、一種の宇宙論で、後に朱子学にも大きな影響を与えることになります。
そういえば、西先生が Philosophy に対して、「哲学」という訳語を造る際、参照していたのはこの周濂渓の『通書』に見える「士希賢」、つまり「士は賢を希う」でした。そこで、「賢哲たることを希う」、つまり「希哲学」と訳し、やがて頭の「希」が取れて「哲学」となった顛末はよく知られているかもしれません。
元の意味を保存するという点では、この「希(こいねがう)」という動詞的な語が落ちてしまったのは、思うに痛恨事であります。なぜなら、この「希」は、原語の philo-(Φιλο-)、つまり「愛する」「好む」という部分に該当するわけですから。「哲学」では単に sophia(σοφια)、「知」の学という話にもなりかねません。プラトンの描いたソクラテスは、知ることを希って、そうした知を持っていると称する人びととの対話を求めたのでした。この動詞の欠落はけっして軽い話ではないのです。
加えて言えば、知識人の間に漢文の素養があったうちはまだしも、やがて「哲学」という字面が、それだけでは十全な意味を喚起しなくなり果てたいまでは、「哲」の字が漢籍において担っていた意味が連想されることは少なく、意味の分かりづらい語になってしまったようにも思います。
話を戻せば、西先生は、蘇長公と周茂叔というのは、語録の学派だと言っています。「語録」と言えば、『毛沢東語録』や『松下幸之助語録』など、人によっていろいろなものを連想するかもしれません。いずれにしても、これらの用法は、つまるところ、ある人物が語ったことを集めた書物という意味です。
しかし、西先生がこれを「佛(仏教)」だといささか非難がましく(と、私には見えるのですがいかがでしょう)述べていることに目を留めなければなりません。
実は「語録」というのは、もともと禅僧の言葉を書き留めた書物を指しています。これが後に、人物の発言集のような一般的な意味になってゆくわけです。そして、禅僧といえば、そう、前回登場した達磨に関わる話でもありました。つまり、インドから中国へ禅を持ち込んだのがこの達磨でした。だから、西先生はここで語録の学派をまるきり「佛」じゃないか、と言うのです。
そして、程子、つまり程顥(1032-1085)と程頤(1033-1107)の兄弟に至って、語録が大いに活用されたと話は続きます。この兄弟は、先に名前の挙がった周茂叔に学んだ人たちでもあります。後の朱子学の基礎を築いた彼らの著作は『二程全書』にまとめられており、そこには語録も入っています。彼らが提起した「理気」の区別や「窮理」については、後に「物理」や「心理」が論じられるところで、詳しく触れたいと思います。
西先生は、さらに薛瑄(1389-1464)と王陽明(1472-1528)という具合に、時代を下りながら、語録という形式を使った文人を想起しています。
いずれにしても、文脈から推し量るに、ここに挙げられた人びとは、まとめてしまえば机上論派、非実証的な文人たちだ、ということになりそうです。ただし、私たちとして忘れてならないことは、西先生自身が、かつてそうした儒学の伝統にどっぷりと浸かり、漢籍の素養を身につけているということです。そうであればこそ、儒学的発想とは異なる西洋諸学の骨法が、いっそう身に沁みていたはずです。それは、初めから確立されたものとして、「そういうものだ」という具合に当然視され、受容されるのとは、まるで次元の違うことです。