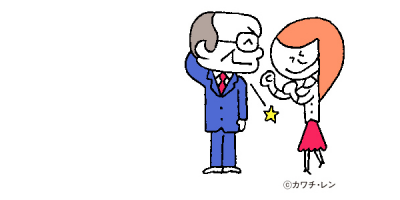「ははっ」と「あはっ」,毛むくじゃらでヒゲもじゃの古強者が豪快に笑うなら,どちらかといえば「ははっ」であって,「あはっ」だとちょっと『女』っぽさが感じられてしまう。
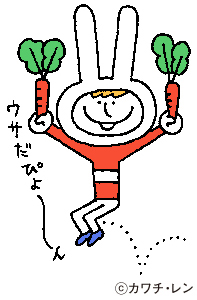
「ふふふ」と「うふふ」,『男』の笑いとしてまだマシなのは「ふふふ,馬鹿め,とうとう罠にかかったな」のような「ふふふ」であって,「うふふ」だと『男』の不自然さはよりはっきりする。
「へへへ」と「えへへ」,上品な子供が失敗して照れ笑いをするなら,「えへへ」の方がいいだろう。
「ほほほ」と「おほほ」はともに『女』に偏るが,男性でも徳の高い上人様が静かにお笑いになるなら,ありそうなのは「ほほほ」であって,「おほほ」では上人様が『オカマ』っぽくなってしまう。
「ひひひ」と「いひひ」は気味が悪くて差がよくわからないが,以上のことからすれば,笑い声は冒頭部に子音が無い方が品がよくなりがち(したがって『男』より『女』が自然になりがち)と言えそうである。
その逆に,冒頭の子音(気流を妨げる発音)を,hという摩擦音(気流の通路を狭める発音)から,より子音らしい破裂音(気流をいったん完全にせき止める発音)に変えると,品は落ちがちである。
具体的に言えば,「ははは」「ははっ」と笑ったり驚いたりする際の冒頭の摩擦音hを,より子音らしい破裂音tやdやgに変えて「たはは」「だはは」「がはは」「たはっ」にすると,品が落ちる。「ほほほ」の冒頭の摩擦音hを,より子音らしい破裂音tに変えた泣き笑いの「とほほ」には,もはや『女』への偏りは見られない。「へへへ」は上品でない子供ならあり得るが,冒頭の摩擦音hを破裂音のtやdに変えた「てへへ」「でへへ」は,子供の笑いではなく,下品な『男』の笑いである。
もっともらしげな講釈を長々と垂れたが,そんな理屈をこねなくても,最後に挙げた「てへへ」は母語話者の直観では下品な『男』の笑いである。
また,ペロリと舌を出すことも,自身の頭を叩くことも,本来は品があまりよろしくない振る舞いだろう。
いったい何を言っているのかというと,どうも最近,『娘』たちの間では(1)のように,「てへぺろ」というのが流行っているらしいのである。「てへっ」と照れ笑いをしてペロリと舌を出す様子を表したものだという。
(1) 「てへぺろ(・ω<)とは,日笠陽子さんが編み出した持ちネタである。事務所に所属した2007年頃から使い始めている。何か失敗してしまった時に,『てへ』と笑い,『ぺろ』と舌を出してごまかす様子を組み合わせることで誕生した」と「声優・日笠陽子ファンサイト Hikasa Yoko .info」には書いてあり,2009年には声優界で流行して「声グラwebが勝手に選ぶ流行語2009(第1回)」を受賞,さらにそこからどんどん広がってしまい,ある意味,定着してしまった用語の一つ。 [//gigazine.net/news/20120302-tehepero/, 最終確認日: 2013年7月21日]
さらに(2)のように,「てへっ」と照れ笑いをした後,自戒の意で自分の頭をコツンと叩く「てへこつ」というのもあるらしい。
(2) 最近バイト先では失敗するとテヘコツってやつだぁ!とぶりっこして遊んでます。しいちゃんと! [//10255849.blog.decoo.jp/article?blog_article_id=32, 最終確認日: 2013年7月21日]
上に述べてきたように,「てへぺろ」「てへこつ」には,『男』っぽい下品な要素はあっても,『女』っぽい上品な要素はないはずである。にもかかわらず,現実には上のとおり『娘』たちが喜んで「てへぺろ」「てへこつ」と言っている。なぜか?
「1厘(いちりん)事件」という事件をご存じだろうか。今から約100年前,或るタバコ生産者が,専売局に納入すべき葉タバコのうち,3グラム弱を自分で吸って起訴された。被害額は1厘,現代の貨幣価値に換算すると1円未満である。さあどうなるか。大審院の判決は,「微罪につき赦してつかわす。無罪じゃ」というものだった。
「てへぺろ」「てへこつ」も1厘事件と同様である。いやもちろん,「聖」属性を持つキャラクタにとっては,正のキャラクタにせよ(『神』『精霊』『聖人』),悪のキャラクタにせよ(『魔王』),「てへぺろ」「てへこつ」あるいは「飲み物は別料金」のような俗な発言は致命傷になる。また,「聖」属性とは無縁の『娘』にしたところで,道端にツバを吐くような下品なまねをすれば『はすっぱ』のカドで2,3日拘留されるか,いずれにせよ無傷では済まない。だが,「てへぺろ」「てへこつ」程度の俗っぽい発言なら,「ま,リアルならそういうのもありだよね」という文脈がたちまち活性化して許容され,それどころか,かえってその『娘』に親近感すら沸く。私はこの文脈を「リアル文脈」と呼び,この効果を「リアル文脈における微罪の親近感効果」と呼んでいる。
いま取り上げた「てへぺろ」「てへこつ」の話は,発話キャラクタ(発話を行うキャラクタ)の話だったが,これは発話にかぎらず行動全般について観察できる。つまり,「聖」属性を持たず,上品さが期待される(たいていは『女』の)キャラクタの,僅かに下品な俗な行動が「リアル文脈」のもとで赦され,どころか親近感を持たれるということが,広く観察できる。
たとえば,「寝坊して学校に遅刻しそうになり,パンをくわえたまま道を走る」という行動を考えてみよう。こんなことはたとえば山本鈴美香『エースをねらえ!』(集英社, 1973-1975, 1978-1980)の通称「お蝶夫人」こと竜崎麗香には絶対にできない。なにしろ「お蝶夫人」は,近寄りがたい高貴な気品という「聖」属性を持った『娘』キャラだからである。(まったく,おそろしい高校生もあったもんだ。) この行動が相原コージ・竹熊健太郎『サルでも描けるマンガ教室 1』(小学館, 1990)で「少女マンガの受けるストーリー展開」における主人公の行動と位置づけられているのは,伝統的な少女マンガの主人公が「聖」属性とは無縁の「ちょっとドジ」なキャラクタであればこその話だろう。(実際にはこの行動をズバリ描いている少女マンガはなかなか見つからないそうだが。) そういう「ちょっとドジ」なキャラクタなら,こんなことをやってもおかしくはなく,かえって読者に親近感を持たれることになる。そして,そのコマでは他のコマとは違って,たとえば片目または両目が「+」のような十字状に描かれるなど,「マンガ内のマンガ」らしく描画が単純化されて戯画化されることになるのかもしれない。といっても,いくら「マンガ内のマンガ」らしく戯画化されても,主人公は道端にツバを吐くことはできないだろうが。
すでに行動キャラクタの話というより,表現キャラクタ(表現される側のキャラクタ)の話に移っているが,前々回取り上げた壺井栄『二十四の瞳』(1952)における謎の女客(実はヒロイン)の「にやり」事件も,内実は以上と変わらない。もしもライバルの死を知って「にやり」と笑ったのなら,これはもうヒロイン失格だが,自分の年齢を若く見られて思わず「にやり」ぐらいの,ちょっと「俗」っぽいことなら,「リアルならそういうのもありだよね」というリアル文脈が活性化されて赦され,かえって親近感が沸く。
ところで,なぜ「てへぺろ」「てへこつ」は微罪なのだろうか?(続)