前々回・前回と見てきたように、夏目漱石の『行人』では弟が兄に「~ですぜ」「~でさあ」と言う。坂口安吾の『不連続殺人事件』では名探偵がやはり「~でさあ」「~ませんぜ」と言い、女中が「奥様、お嬢様はゲロはいて、~」と言うのであった。壺井栄の『二十四の瞳』では、ヒロインが「~ますな」と言い、にやりと笑ったりするのであった。いくら権威ある有名どころの文章とはいえ、このような不自然な表現を含んだものを取り上げていくことは、日本語とキャラクタの関わりを見る目をかえって曇らせ、両者の関係を歪ませることになりはしないか?
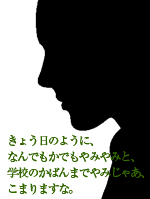
たしかに、そういうことはあるかもしれない。だが、そんなことはあまり心配しなくていい。なにしろここで私たちが問題にしているのは、現代日本語という、私たちがそれなりに直感を利かせることのできることばの世界なのだから。
『行人』の弟や『不連続殺人事件』の名探偵が「~ですぜ」「~ませんぜ」「~でさあ」と言うこと、『二十四の瞳』のヒロインが「~ますな」と言うことは、たしかに現在のことばとしては不自然である。だが、それは私たちが直感でわかることである。これらは現在の日本語の例としては認めなければいい。それだけの話である。
他方、『不連続殺人事件』における女中の発言「奥様、お嬢様はゲロはいて、苦しみなすっていますが」は、「奥様」「お嬢様」ということばの上品さや「ゲロはいて」ということばの下品さに対して鈍感な、或る種の『田舎者』キャラの言動として、現在でもそれなりに理解できる。
また、『二十四の瞳』のヒロインが「にやり」と笑うのは、これが直前の章から八年後の場面冒頭であって、このヒロインがヒロインとしてではなく、正体不明の女として登場しているということからすれば、現在の感覚からしても、もっともなことだろう。
だから、「お嬢様はゲロはいて」や「にやり」は、現在ではもう古すぎて通用しないとして片付けるわけにはいかない。現在でも通用する日本語、但し話し手や場面に一ひねりある例として認めればいい。
こういうことは、私たちは直感的にわかるから、話はかんたんである。直感を使うべきところで、使わない手はない。
言語コミュニケーションの根本問題、つまり私たちが集まってことばで何をしているのかという問題に対する私たちの理解は、残念ながらごく部分的なものにとどまっている。或る特定の言動が、言語コミュニケーションの世界全体の中でどのような位置を占めているのか、それを知ることさえ、私たちにはまだまだ難しい。位置を知りたくても、そもそも言語コミュニケーションの世界の極点や赤道がまだ発見されておらず、経度や緯度が割り出せない。それぐらい、私たちは言語コミュニケーションの世界をわかっていない。
このように言語コミュニケーションに対する私たちの理解が限られているのは、そもそも言語コミュニケーションにおける「意味」というものが、その世界に生きる者が直感によって生み出すものであって、世界の「外側」から客観的に計測し尽くせるものではないということによるのではないか。何かを正面きって考察しようとする際には、直感は、とかく排除されてしまいがちだが、私たち自身の言語コミュニケーションを考察する場合にかぎって言えば、直感は客観的計測とは別に、重要な一つの手段たり得るのではないか。
「日本語社会の考察には、キャラクタという概念が必要」ということを主張するのに、私がややこしい数式やグラフを持ち出さず、名だたるものとはいえ、文学作品の断片ばかりを取り上げているのは、読者に、キャラクタというものに直感で思い当たってもらうことがベストだと考えているからである。
ま、これって結局、「そういう作品が好きだから」ってことかもしんないけどね。







