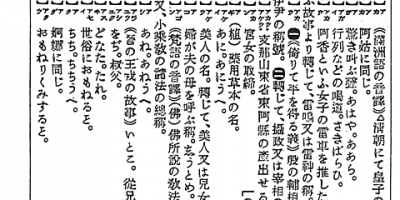これまで「城の崎にて」を分析するにあたって,ふたつの構造をこの物語に重ね合わせてきました。ひとつは「行って帰ってくる」物語で,もうひとつは死の周辺から核心へと描写を進めるプロセスです。
しかしながら,これらふたつの構造を下敷きにしてこの小説を読まねばならないという必然的な理由は,実のところありません。「城の崎にて」について一連の文章で私が示した見方は,言ってみれば,そのように解釈すると整合性の高い読みができますよ,という提言のようなものです。読み方のひとつの指針でしかありません。
ただ,もしここで取り上げたふたつの構造が無関係なものではなく,互いに連動していることを示せたら,両者を作品解釈に適用することの信頼度はさらに高まるはずです。最後にその点について考えてみましょう。
「行って帰ってくる」物語の構造を分析に用いたのは,おもに作品の冒頭部と終幕部に対してでした。他方,死の周辺から核心へと至るプロセスは,小動物の死に関する3つのエピソードに関係づけて取り入れました。つまり,これまでの分析では,「行って帰ってくる」物語は作品のはじめと終わりに対応し,死の周辺から核心へのプロセスは作品の本体部分に対応する,という分業がありました。
ところが「行って帰ってくる」物語は,作品の周辺部分だけでなく,3つのエピソードを説明するのにも役立ちます。
まずはおさらいです。「行って帰ってくる」物語は,典型的には英雄の冒険潭の形式を取り,おおむね次のように展開します。
(94) a. 不安定な欠損状態の存在
b. 主人公の旅立ち
c. 主人公の試練
d. 安定状態の回復
e. 主人公の帰還
(94)を下敷きにすると,「城の崎にて」は,もちろん主人公が城崎に行って帰ってくる話であると同時に,死に対して失った畏怖をふたたび主人公が獲得し,生と死の緊張感を取り戻す話でもあります。そういった主題を小動物の死に対する観察からその過程を浮かび上がらせる,それがこの小説の基本設定です。
このうち,作品の冒頭部(第63回の(80))と終幕部(第64回の(84))はそれぞれ,(94b)の「主人公の旅立ち」と(94e)の「主人公の帰還」に当たります。そして,残る3つの部分は,以下のように対応します。
(95) a. ハチのエピソード:不安定な欠損状態
b. ネズミのエピソード:主人公の試練
c. イモリのエピソード:安定状態の回復
ハチのエピソードでは主人公が山手線の事故以来,死の静かさに親しみを抱いていることが語られます。彼は死に対して麻酔がかかった状態にあるのです。生の躍動を意識できず,それと表裏一体にある死に対しても畏怖の念を失ってしまった。その意味において,主人公は危うい不安定な状態にいます。彼は怪我を癒す養生のために城崎を訪れますが,それは同時に精神に健全さを取り戻すための旅立ちでもあったのです。

ネズミのエピソードは,そのような主人公の上辺の安穏さを脅かす試練を与えます。「鼠が殺されまいと、死ぬに極まった運命を担いながら、全力を尽して逃げ廻っている様子」は,主人公にとって直視できない痛切なものでした(「自分は鼠の最期を見る気がしなかった」)。そして,「今自分にあの鼠のような事が起こったら自分はどうするだろう」と,不安定さを引き起こした電車事故について思いを巡らせます。
最後のイモリのエピソードで主人公は自らイモリの死を引き起こします。そして,死のとらえ方に対してすでに心を揺さぶられていた主人公は,「生きている事と死んでしまっている事」に対し意識を新たにします。
(96) 死んだ蜂はどうなったか。その後の雨でもう土の下に入ってしまったろう。あの鼠はどうしたろう。海へ流されて、今頃はその水ぶくれのした体をと一緒に海岸へでも打ち上げられている事だろう。そして死ななかった自分は今こうして歩いている。そう思った。自分はそれに対し、感謝しなければ済まぬような気もした。しかし実際の喜びの感じは湧き上っては来なかった。生きている事と死んでしまっている事と、それは両極ではなかった。それほどに差はないような気がした。
主人公がとらえた生と死の対立について寡黙な作者は多くを語りません。しかし,「そして死ななかった自分は今こうして歩いている」というふうに,主人公は自分が生の側にあることを実感しています。死に対して親しみを覚えていた当初に比べると,明らかに自然な状態と言えるでしょう。
「城の崎にて」は静かな心境小説です。「行って帰ってくる」英雄の冒険潭がその背景にあるというのは,意外な取り合わせのように思えるかもしれません。しかし,「行って帰ってくる」物語を下敷きにすることで,「城の崎にて」の主題は引立ちます。主人公が最後にたどり着いた境地に対する説明がほとんどないにもかかわらず,私たち読者が何か分ったような気がするのは,主人公が一度なくしたものを回復したと想定するからではないかと思います。