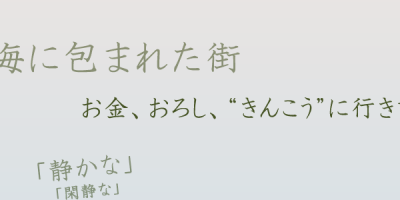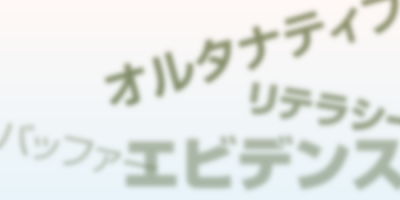去年の晩秋のこと、ある女友だちと飲んでいて、「来年は生誕100周年ですね」という話になった。だれが生まれて100年なのかというと、太宰である。二人とも、ファンなのだ。
「関連本が、いろいろ出るみたいですよ」
「そっか。ぼくも何か書きたいなあ。手持ちの材料には四字熟語くらいしかないけど」
「いいんじゃないですか。桜桃忌までに出せば、そこそこ売れますよ。きっと」
というわけで書き始めた拙稿、運良く、三省堂さんから出版していただけることになった。題して、『太宰治の四字熟語辞典』。内容は書店でご覧いただくこととして、ここでは、その「こぼれ話」を5回ばかり、連載させていただくこととしよう。
*
四字熟語の中で、最もよく使われるものは何か?

この質問に対する答えは、はっきりしている。「一生懸命」だ。ぼくのパソコンの中には、日本文学を中心とするさまざまな文献から、約3000語の四字熟語の用例を2万強集めたリストが入っている。その中で頻度数が一番高いのが「一生懸命」で1200超、2位は「不可思議」で350弱。まさにケタ違いなのである。
ぼくも「一生懸命」仕事をするたちだから(?)、この四字熟語をよく使う。でも、その原稿を出版社に送ると、「一所懸命」の間違いでは? とご指摘をいただくことがある。
主君から領地を安堵された武士が、その1か所の土地を命がけで守り抜く。それが、「一所懸命」の語源だということは、よく知られている。だから、たしかに「一生懸命」は、語源的には間違いだ。でも、この「誤用」、かなり古くからあるらしい。
たとえば、江戸時代の浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』(1748年初演)では、恋人おかると会っていたせいで主君の大事の場に居合わせられなかった早野勘平が、「主人一生懸命の場にもあり合はさず、……その家来は色にふけり」とほぞをかむ。語源に近い用法だが、表記は「一生懸命」である。
また、ぼくの調べた限りでは、夏目漱石は「一生懸命」しか使わないし、芥川龍之介も同様だ。先ほどのリストにも、「一所懸命」は約130例、「一生懸命」の10分の1程度しか出てこない。つまり、語源的な正しさは別として、現実の生活の中では、「一生懸命」は「一所懸命」よりもはるかに定着しているのだ。
おもしろいのは森鴎外で、「一所懸命」も「一生懸命」も使わない。
「僕は後に西洋人の講義を聞き始めた時と同じように、一しょう懸命に注意して聴いていると」(『ヰタ・セクスアリス』)
「間もなく窓に現れた小僧は万年青の鉢の置いてある窓板の上に登って、一しょう懸命背伸びをして籠を吊るしてある麻糸を釘からはずした」(『雁』)
漢字の使い方については、相当な一家言を持っていた鴎外のことだ。「一しょう懸命」と書いているからには、その頭脳の中には、「1か所の土地」といったイメージはなかったに違いない。
*
それでは、太宰はどうかというと、『太宰治の四字熟語辞典』のコラムにも書いたことだが、「一生懸命」の用例は43を数えてやはりダントツに多い。ただ、別に「一所懸命」が1例だけある。
たった1つの「一所懸命」、それは、『満願』(1938年)という、文庫本にしてわずか3ページの小品に出てくる。ある年の夏、富士山を望む三島の町に間借りして、小説を書いている「私」。お酒を通じて親しくなった医者の家に、毎朝、新聞を読みに行くのだが、「その時刻に、薬をとりに来る若い女のひとがあった」。清潔感が漂うその女性を、お医者は「もうすこしのご辛棒ですよ」と言って送り出す。3年前から肺を悪くしていたご主人が、このところどんどん回復しているのだ。
「お医者は一所懸命で、その若い奥さまに、いまがだいじのところと、固く禁じた。奥さまは言いつけを守った」
さて、その夏の終わり、「私」は「美しいもの」を見る……
ただ1度だけ使われたこの「一所懸命」は、なぜ「一生懸命」ではないのか? 「いっしょう」よりも「いっしょ」の方が、リズムが軽やかだからか? あるいは、大酒飲みの町医者には、武骨な板東武者の面影があったからか? いやいや、編集者が勝手に手を入れただけかも!
そんなことを、ああでもない、こうでもないと考えている時間。ぼくは、とても幸福なのである。