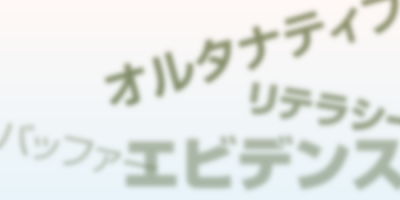以前、日本語の授業で自分の育った場所を紹介する作文課題を出したことがある。するとある学生が「大連は海に包まれた街です」と書いた。私は前回、ことばの正しさを「意図したとおりに通じる」「受け手の気分を害さない」の二つから説明できるとした。ここでは「海に囲まれた街」と言いたいことはよくわかった。その意味では、意図は通じていると思われるし、特に気分を害する表現でもない。
日本語教育を担当していると、このような表現によく出会う。そして考えさせられる。これに赤ペンを入れるべきかどうか、と。「包む」と「囲む」を比べると、前者は立体的で、後者は平面的だ。大連は、ご存知の方もいるかと思うが、海に突き出した半島の町で、三方を海に「囲まれて」いる。
だが、私は「海に包まれた街」という表現を見た瞬間に、かつて大連の海辺を訪れた時の青い空と青い海に「包まれた」ような、美しい光景を思い出した。いや、正確には街全体が立体的に包まれたようなイメージを喚起されたのである。
「海に包まれた街」は隠喩(メタファー)である。「街」をモノに見立て、「海」を、それを包む布か紙に見立てたような比喩である。おそらくこれを書いた学生は、ただ「囲む」と「包む」の違いがわかっていなかったか、「囲む」という語を知らなかっただけであろう。この2語の違いは、日本語教師としては教えるべきであろう。しかし、「海に包まれた街」があまりに素敵な表現だったので、そこに赤を入れることはためらわれた。これは「月曜日」を「火曜日」と間違えるのとは、質もレベルも異なる“誤り”である。
このことは、少し広げて考えると、近年、母語以外の言語で書く作家や、クリオール(二つの言語が混ざってできたピジン[pidgin]が母語化した言語)の作家が全世界的に注目を集めていることとも関係していると思われる。すなわち、母語使用者にはないような発想が新たな表現を生んでいるということである。
私の好きな日本語作家のひとり、デビット・ゾペティは、スイスで生まれ育ったが、母親がアメリカ人で、家では英語、学校ではフランス語を使い、ドイツ語もイタリア語も身に着けて育った人である。そんな彼が日本語で書いたデビュー作『いちげんさん』(集英社)は、すばる文学賞を受賞し、芥川賞の候補にもなったが、そのレトリック(修辞、表現技巧)が評価された面が大いにあるであろうことは読んでみればすぐにわかる。
ことばの規範(正しさ)も美しさも、その言語社会の中で時間をかけて作られていくものであり、その時々に少しずつ変化していくものである。母語でない人がそれを作ることに参加できないわけがない。
参考文献
デビット・ゾペティ(1997)『いちげんさん』集英社