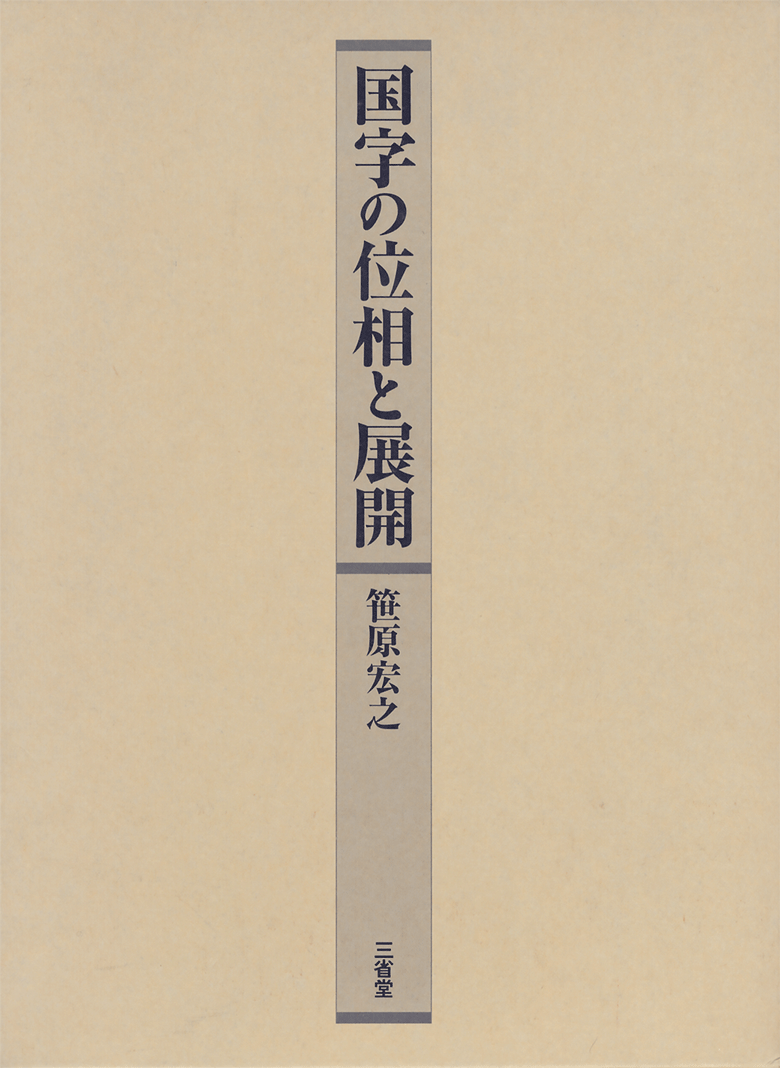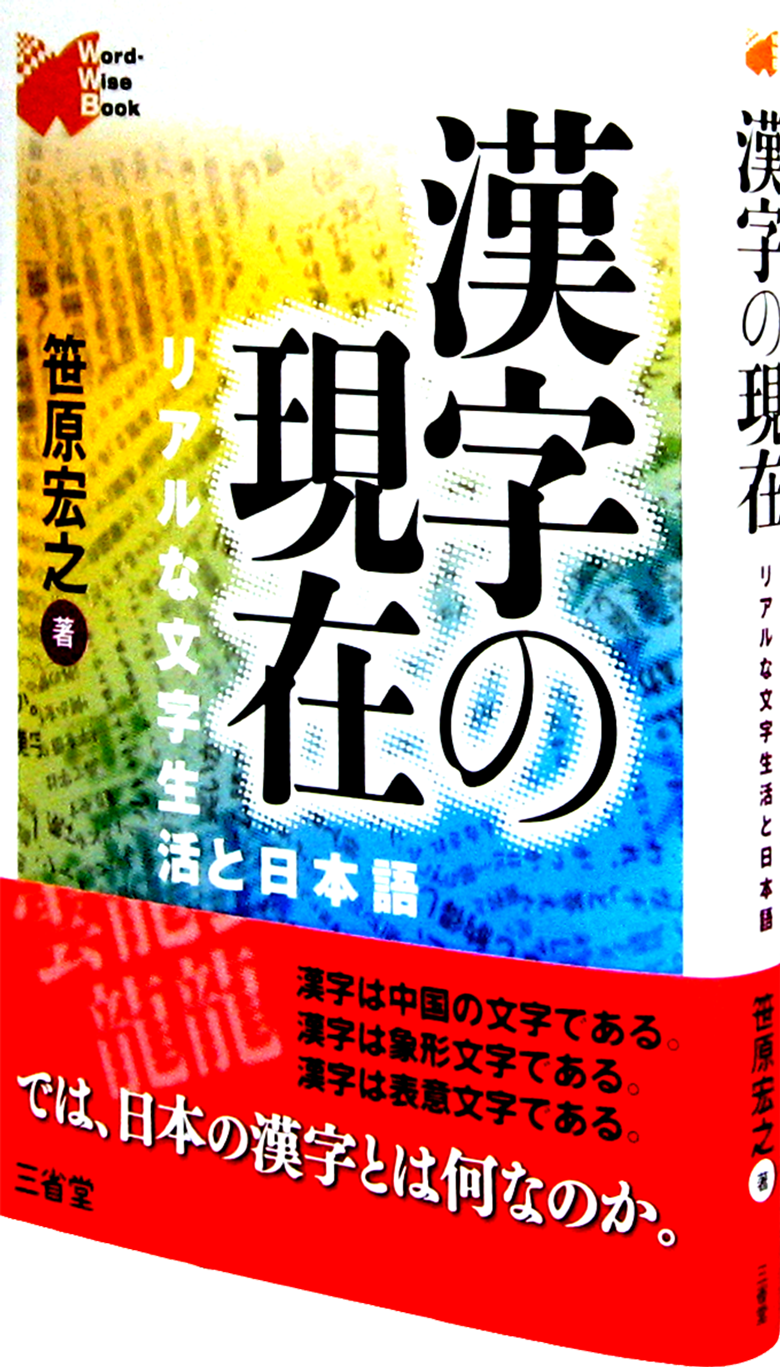前々回に触れた、江戸時代の70画台の「字」は、恋川春町の『廓 費字尽(さとのばかむらむだじづくし)』(天明3(1783)年刊)という戯作本に登場する。かの蔦屋重三郎の手がけた黄表紙で、そこには79画とも数えられる形に「おういちざ」(おおいちざ)と読みが添えられている【図】。この本の元となったものが『小野篁哥字尽』で、影響力も大きく、何種類もの亜種、中には目を疑うような語をも扱った異種までが派生した。
費字尽(さとのばかむらむだじづくし)』(天明3(1783)年刊)という戯作本に登場する。かの蔦屋重三郎の手がけた黄表紙で、そこには79画とも数えられる形に「おういちざ」(おおいちざ)と読みが添えられている【図】。この本の元となったものが『小野篁哥字尽』で、影響力も大きく、何種類もの亜種、中には目を疑うような語をも扱った異種までが派生した。
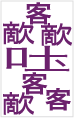
【図】
「今昔文字鏡」など、正方形にデザインするものがあったが、その実物は細長く、とても一字としてのまとまりを持たないもので、さらにその次に並ぶ「字」は、方形にまったく収まっていない。「おういちざ」とはむろん大一座のことであるが、『異体字研究資料集成』には本文だけが影印されていたため、従来いろいろな意味が推測されてきた。
これは、原文の挿絵と、そこに記されている科白などまでを確認すれば、団体客のことを指していて、その「字」に含まれている「敵」は敵娼(あいかた)たちであることが分かる。その中で、悪酔いした「客」の一人が「吐」いてしまっている、という困った状況を表すことは、『別冊太陽』89(1995)で、鈴木俊幸氏が解説しているとおりであると考えられる。
84画の字もそうであったが、紙の本や活字の辞書が典拠となって、WEBに情報が転記されたり、テレビでも取り上げられたりする。多くの人にとって面白い情報は、情報化社会の中で循環しつつ、拡散していくものである。84画の字については、姓としてはなくなっているが、それを元にした名としては実在する、といった都市伝説のたぐいをいくつか耳にし、実際に確認に遠路走ったこともあった。それとともに、意味内容や裏話のようなものが膨らんでいくことも常である。
字義が忘れられ、字面から得られるイメージの良さから、人名に用いたいという要望が複数あることが見つかった「腥」という漢字の読み方も、かつて調査に当たったときには、「セイ」しか確認していない。私は、そのようにしか述べたり書いたりしていないはずだが、今ではこの話にまつわり、種々の「名乗り訓」が流布しだしている。ほかにもし確かな出所がないとすると、「セイ」よりもそれらしい和語の方が想起しやすく、あるいはピンと来るためであろうか。
名付けで大きな話題となり、有名となった「悪魔」という届け出も、あの読みは「デビル」だった、と複数の学生が述べるようになった。それでは結局「亜駆」とされたということの意味が半減するが、何か別の話題と混じながら、より驚きの勝る方へ話が増大したのであろう。
JIS漢字の幽霊文字として知られるようになった「妛」は、もとは「𡚴」(あけび 合字 第3水準として採用)であったが、「あけんばら」に対する本来的な代用による使用を経て、種々の新たな読みでHN(ハンドルネーム)などにも使われるようになった。「安」を誤植した例から、実は姓に使われていた字であったという話までも、まことしやかに流れたことがあった。
偶然に字体が一致する例さえも見つかっていない「彁」までが、JIS漢字に採用され、典拠不明と一部で注目されるようになってからは、面白がって使われ、独自の音義を与えられ、新たな用例を蓄積してきている。こうした立派な幽霊文字が新たに関係のない魂を注入されることで、個人文字、さらには位相文字へとなっていく過程を目の当たりにできそうだ。それらには、漢字、国字というレッテルが後付けながら貼られることになるであろう。