『日本百科大辞典』は、日本ではじめての本格的な百科事典として、明治31年(1898)ごろ、三省堂の辞書編集者・斎藤精輔によって企画された。
明治29年(1896)秋、三省堂は『和英大辞典』(F・ブリンクリー他 編)を刊行した。この辞書の編纂時、動植物関係の専門用語の訳出で苦労したことが、『日本百科大辞典』の発案につながった。のべ数百人の学者・研究者に通訳を依頼して集めた各分野の専門用語にかんたんな解説をつけ、1冊の百科事典にまとめて出版したら便利だろうと思いついたのがきっかけだ。当初、斎藤は、その編修を2年あまりでしあげるつもりでいた。
当時の三省堂には、辞書編修の核たる存在である斎藤精輔はもちろん、ひとりひとりの社員にいたるまで、「辞書のために働く」「よりよい辞書をつくる」という気風が浸透していた。『日本百科大辞典』は、そんな基本理念のなかから生まれた企画だった。
編修は、明治31年(1898)からはじまった。各分野の識者から原稿をあつめて整理し、印刷のための組版が開始されたのが明治36年(1903)。第1巻が刊行されたのは明治41年(1908)のこと。すでに企画発案から10年、組版開始からでさえ5年の年月がながれていた。
なにしろ、当時は金属活字をもちいた活版印刷である。百科事典という膨大な情報量、ページ数の原稿を組むために、金属活字を1字1字、棚からひろって版を組んでいかなくてはならないのだ。その作業量と活字の物量は、コンピューターで組版をおこなっている現代のわれわれには、想像することすらむずかしい。

活版印刷では、必要な金属活字を職人が棚から1字ずつ手で拾い(文選)、版を組んだ
(写真は大正7、8年ごろの三省堂印刷 植字部)
しかも、「1冊にまとめたら便利」というアイデアからはじまったはずが、「よりよい百科事典をつくろう」と進められるうち2巻、3巻と増えていき、ようやく1巻の発売開始となったときには、全6巻と索引1巻の合計7巻の計画へとふくらんでいた。
1巻の刊行までに10年かかったため、当初集めた原稿は古くなり、使えなくなった。変更がくりかえされたことで、むだな原稿もかさんでいった。それにともない、活字組版は何度も組み替えがおこなわれることになった。そうして1ページの植字代(組版代)は通常の数十倍の金額へとふくれあがっていった。
三省堂の印刷所は、『日本百科大辞典』発行のために準備した六号活字の分量が、同書を3000ページ組み置きしても余りがあったと誇った。しかしそれも、後に三省堂社長となった亀井寅雄(創業者・亀井忠一の四男)は「過剰・先行投資の一例」と語っている。[注1]
内容がふくれあがったのは、斎藤精輔のこだわりの強さの影響でもあった。亀井寅雄は後にこれを「斎藤氏一流の採算を度外視したいいもの主義」[注1]とバッサリ斬っている。たとえば、芝居の挿絵のよいものがないからとわざわざ歌舞伎座に出向き、役者を使って撮影して持ち帰ったにもかかわらず、やはり気にいらずに使うのをやめてしまったことがあった。あるいは、柔道のよい挿絵がないからと講道館に出向いて高段者に実演してもらい、それを撮影するということに多くの金をつかった。木版画にしても、極端なものでは百数十度刷りというものまであったという。
こうして、『日本百科大辞典』の編修は、三省堂の経営をしだいにおいつめていった。1巻の発売開始が報じられると注目を集め、申し込みも相次いだが、一方で「一出版社が取り組むには無謀な計画なのではないか」と、企画の先行きを懸念する声も聞かれるようになった。
『日本百科大辞典』第1巻は明治41年(1908)11月に刊行。第2巻は明治42年(1909)6月、第3巻は明治43年(1910)3月、第4巻は明治43年(1910)12月、第5巻は明治44年(1911)8月、そして第1巻発売時に「終巻」として発表した第6巻は大正元年(1912)8月に刊行された。しかしそのころには、『日本百科大辞典』の内容はすでに、6巻でも収拾がつかないほどにふくれあがってしまっていた。6巻では終われなかったのだ。
そうして第6巻が刊行された大正元年(1912)。2か月後の10月18日に、三省堂の経営破綻があきらかとなった。
※写真は『三省堂の百年』(三省堂、1982)より
[参考文献]
- 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)
- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)



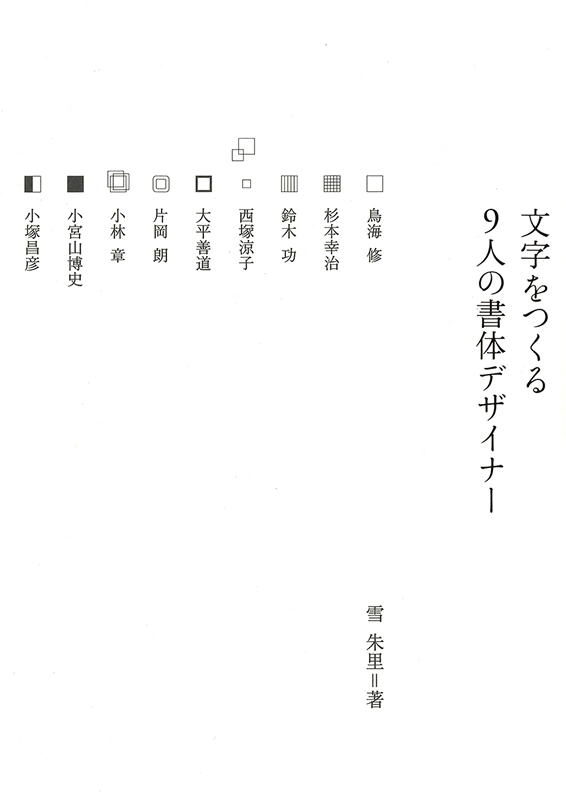





[注]