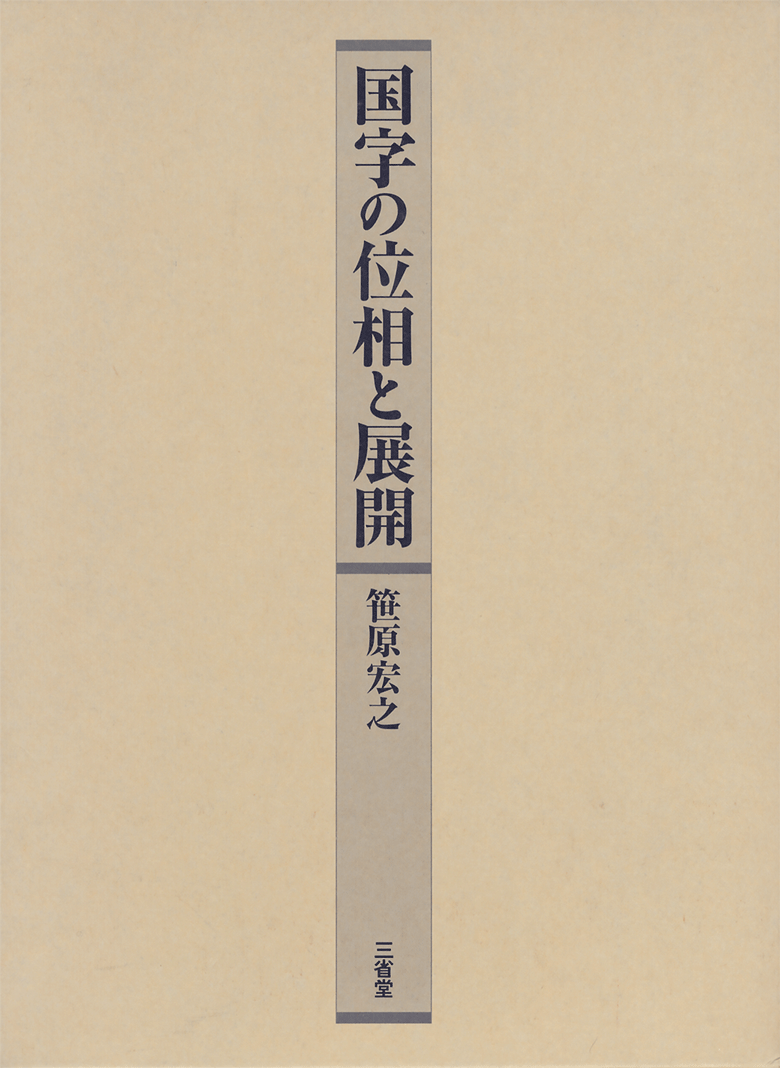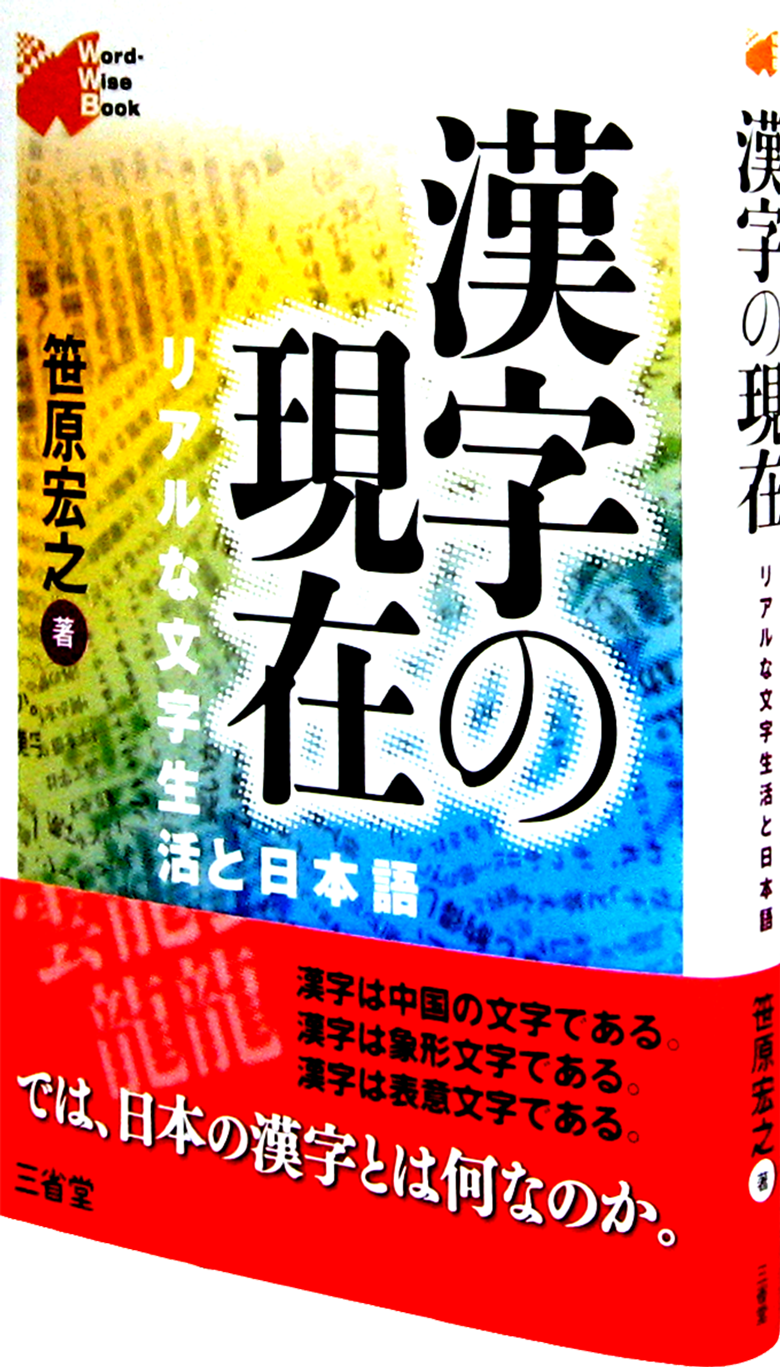奥三河、奥飛騨、奥湯河原、地名に「奥」が付くと交通が不便そうだが、なにか未知を感じてしまう。平家の落人伝説のような歴史の闇に隠された神秘を垣間見られそうな気がするためだろうか。

2,3日前、直前になって突然近郊の宿を取ろうとしたって、いくら不景気でもそうそう空いてはいない。熱海は手頃なのだが、客慣れしたような旅館に入ってしまったこともあった。遠く城崎は、街全体に湯煙の風情が漂う、情緒に満ちたところだったが、今回はそう足を伸ばせない。ドラえもんにふだんの室内に温泉を写す素晴らしい道具があって、いまだに忘れられないが、そういうものに頼りたくもなる。あれこれ探す内に、やっと1つだけ奥湯河原に見つかった。ここしかもう取れない。ホームページを見れば、宿の敷地で「瀧」が見られる、そして「空の青、山の巒(あお)」とある。これは少し面白そうだ。「(あお)」のような括弧内での注記は、振り仮名を示す場合(新聞業界では「付け仮名」とか言ったと聞く)と、意味の説明を添える場合との区別が形式面ではないため、どちらなのかが判別できないようなケースもあるのだが、ここでは対句になっているところから、読み仮名とみて間違いなさそうだ。
これは、この旅館の字音語の名に基づく読みのようだが、「出藍」の「藍(あい)」とも日本漢字音の一致から連想が起こりそうだ。「巒」は山、小山、続く峰などを意味するばかりで、色を字義には持たないようだが、ここでは違っていた。これは位相訓(義)といえるか。「翠巒」の語は、漢文の世界から飛び出して各地で使用されている。高崎高校には「翠巒祭」がある。漢字は違っても「横浜翠嵐高校」などの「翠嵐」も、この「嵐」はアラシの意ではなく、モヤや2字で樹木の青々とした様子を指していて、実は意味に重なる点もある語のようだ。
「巒」はあまり使われない字であるが、画数の多さによって、新字体などからの類推が働き、「恋」「変」のように、あるいは簡体字の如くに略されることも、そうした地では起きているのかと思われる。神奈川と静岡の境目、天下の険の箱根山のカルデラにできた芦ノ湖につながる所で、さほど遠くはない温泉宿に、くたびれた自分はもちろん、親や家族のためにもここは奮発を決意する。
温泉で字を見た義父は、「これは正式な字なのか」「(崩し字を見て)糸偏なのか」「読めないなあ、振り仮名をつけると効果がないのかな」と気になる様子だ。たしかに振り仮名があれば読みやすくなるが、同時に安っぽく感じられてしまうという陥穽もある。滝の落ち落ちる池、草木と竹林の匂い、都内ではいつもの喉の痛みもいつの間にか薄れている。
母も、「面白い字ね」、「せいらんそう、せいらんそう、せい…」、家内はランと読むと分かっていながらも言いよどむ。この字も、高級感や非日常感などにつながっているようで、略字はカウンターをのぞき込んでも見つからなかった。この漢字で宣伝効果を発揮できているのかもしれない。
再来週の済州島出発を前に、はからずも夕食には鮑(アワビ)の踊り焼きが出てきた。アワビには気の毒だが、「鮑」が国訓なのか、「蚫」が国字なのか、日本、韓国、中国の残存文献を通してできる限り調べた縁かもしれない。研究者として、現在の資料で何がどこまで判明するものか、どこからが歴史の闇に閉ざされているのか、名前と資料を示しつつ責任をもって明らかにし、批判を待つべく同時代に還元し、そして後代にゆだねることも使命というか役目の一つだと思っている。
私が仮にここで箸を付けなくても、眼前のアワビの運命を変えることはもうできない。せめてありがたく食してみて、アワビが宋代にすでに、日本から中国に輸出されるほどの品だったのかを、確かめておこう。新聞の広告欄でも、「ランチに「鮑」の贅沢。」(読売2012.7.26)というホテルの中華料理の宣伝があった。料理の写真はあっても、振り仮名などどこにもないところがまた高級感を演出している。年に一度くらいは豪勢にと奮発した甲斐があって、大人たちの前に並んだ鮑は、熱に身をよじって激しく跳ねた。口にすると、なるほど奈良時代から日朝間で、宋代からは日中朝で国境を越えて取引され、「鮑」も「蚫」も使用が伝播しただけのことはあった。