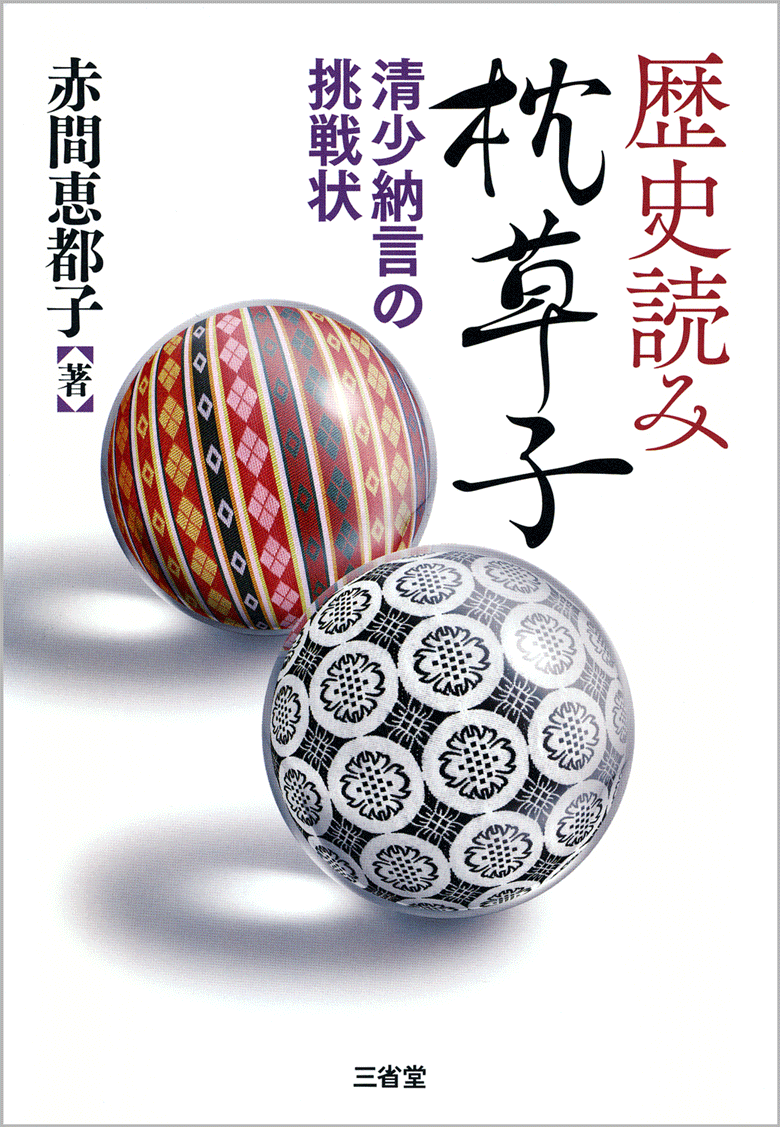職曹司時代の長徳四年冬から長保元年正月までの時期を扱った章段に、中宮御前の雪山作りの話が記されています。『源氏物語』では、光源氏が紫の上に寝物語として、藤壺中宮の御前で作った雪山のことを語りますが、その歴史上で最も近い前例として挙げられるのが、『枕草子』のこの段です。
「雪山の段」と呼ばれるこの章段は、初冬の精進日、一人の尼乞食が仏前の供物の下がりを求めて登場する場面から始まります。清少納言たちが面白半分に、「他の物は食べないで、仏様の供物だけ食べるなんて、尊いことよ」とちゃかすと、女は真面目に「それがないから供物をもらいたいのです」と答えます。同情した女房たちは女を近くに呼び寄せ、様々な食べ物を与えます。さらにあれこれと質問して答えさせているうちに、女は調子に乗って歌を歌い、舞い出しますが、それが下品な歌詞と踊りでしたから、定子のひんしゅくを買ってしまいます。その時歌った歌詞の一句から「常陸の介」と呼ばれるようになった尼乞食は、それから度々職曹司に顔を出すようになるのです。
中宮が滞在する職曹司に、物乞いをする下衆(げす)が入り込んで来たということに少し驚きますが、広大な敷地に多くの建物が立ち並ぶ大内裏では、警備の対象とならない下衆女のたぐいなら容易に入ることができたのでしょう。
常陸の介は、定子サロンの内部に登場してきた《笑われ者》です。作者がこれまで描いてきた、称賛すべき上流貴族たちが定子の周辺から姿を消した時、その代わりに選ばれた描写対象が、人寂しい没落家に入り込んでくる下衆たちだったのです。彼らは身分相応の言動で周囲の失笑を誘う存在です。しかし、作品内で生き生きと活動し、清少納言ら女房たちと関わりながら、新たな作品世界を形成していきます。
ある日、常陸の介とは別の、もっと品のいい尼乞食が職曹司に現れたので、女房たちが彼女にいろいろ質問し、中宮からも着物が下されました。そこに常陸の介が来合わせ、様子を見てしまいます。それから急に職曹司に来なくなった常陸の介のことを、女房たちはすっかり忘れていました。
12月中旬に積雪があり、御前で雪山作りが行われます。そして、この章段の主筋である雪山の賭けの途中で、常陸の介が再登場するのです。清少納言が常陸の介に、長い間、姿を見せなかった理由を問いかけたところ、彼女は自分の心境を和歌で答えます。
うらやまし足もひかれずわたつうみのいかなる人に物たまふらむ
(うらやましいこと。歩けないほども沢山、どのような人に物をお与えになったのでしょう)
下流の身分で一人前に詠じた和歌は、やはり身分相応のものでした。章段構成としては、この常陸の介の和歌を挟んで、前に内裏からの使者に対応する清少納言の歌、後に大斎院選子から定子へ贈られた歌、と和歌が三首、並んで配置されています。
三首の和歌の中心に置かれているのが下衆の常陸の介の歌であり、彼女は詠歌の後、雪山の上をうろうろ歩き回って退出してしまいます。《笑われ者》常陸の介の役割は何だったのか、歴史的背景を対照させながら、後で改めて考えてみることにしましょう。