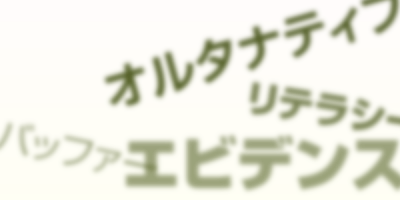PISAは嫌われている。けっこう嫌われている。
理由はさまざま。だが、PISAというと「世界はこうなっている。だから日本もこうすべきだ」という論法が見え隠れするあたりが大きいように思う。
この論法は日本政府の常套手段だった。正確には外務省の常套手段だった。長くて重たい伝統をもった日本はそうそう簡単には変わらない。だから外圧を使って変えようというのである。これは日本人の同調性を利用した部分もある。日本人の習性からして、「みんながそうしていますよ。そうしていないのは日本人だけですよ」と言われると不安でたまらなくなるからだ。
だが、最近は外圧も通用しなくなりつつある。それどころか「ここは日本だ」という感情的な反発を招きやすい。PISAに対しても同様の反発がいまだに消えない。
PISAというと「国際的に通用する能力」というような文脈で語られることが多いが、これは得策ではないと思う。どこの国の人にしても基本的には国内的に生きているのであって、国際的に生きているのではない。国際的に通用する能力など必要ないのである。だから、PISAで求められている能力についても、その能力が今後は国内的に必要になることを力説すべきなのだ(*)。
PISAがいきなり測定から始まったことも不幸であった。本来ならば、まず指導があって、それから測定というのがスジだろう。誰だって習っていないことについて、いきなりテストをやられたら文句のひとつも言いたくなる。子どもならば確実に「まだ習ってませ~ん」と文句を言う。
PISAがいきなり測定から始まったにもかかわらず、いわゆる「PISA型読解力」なるものの指導が奨励されたことも不幸であった。熱心な先生たちは、公開されたPISAのサンプル問題から、その背景にある指導法を推理しなければならなくなったのである。(さらにいえば、公開されたサンプル問題が欧米型の読解問題としては出来の悪いものばかりだったことも不幸であった。もしかすると出来が悪かったからこそ、サンプルとして外部に放出されてしまったのかもしれない⇒第14回「PISAサンプル問題を評価する」へ)
当然のことながら、指導のための発問と測定のための発問は違う。また、指導は発問だけで成り立っているわけでもない。PISAのサンプル問題から指導法を推理するのは至難のわざであったに違いない。ほとんど不可能であったに違いない。
この連載でも繰り返し述べてきたように、PISAの読解力は欧米型の読解教育を基盤にしている。だから、その指導法を知りたければ、サンプル問題を参考にするよりも、むしろ欧米型の指導法を参考にしたほうが早道だろう。もちろん日本と欧米とは違うのだから、欧米の指導法をそのまま取り入れても仕方がない。あくまでも参考にするのである。
前回まで3回にわたってPISAの発問について説明してきたが(情報の取り出し・解釈・熟考と評価)、あれも基本的には測定のための発問についての説明であった。今後は具体的な指導法について、欧米での指導事例などを紹介しつつ説明していくことにしようと思う。
* * *
(*)このあたりについて詳しくは拙著『ニッポンには対話がない』(平田オリザ氏との共著/三省堂 2008年)を参照されたい。