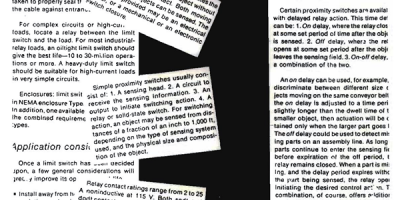●歌詞はこちら
//www.songlyrics.com/sugarhill-gang/rappers-delight-lyrics/
曲のエピソード
喋る音楽、アクロバティックなブレイクダンス、DJが第三者のレコードを使ってターンテイブルを巧みに操る技(手でレコード盤をこする“スクラッチ”など)、“グラフィティ”と呼ばれる街角や地下鉄の車体にスプレー缶で描かれた独特の文字やイラスト――それらを総称してヒップ・ホップ、またはヒップ・ホップ・カルチャーと呼ぶ。ヒップ・ホップ元年もしくはラップ元年を1979年とする説が有力なのは、このシュガーヒル・ギャングの「Rapper’s Delight」が同年にリリースされ、翌1980年にラップ・ナンバーとして初めて全米トップ40入りを果たすという快挙を成し遂げたからだ。彼らがレコード・デビューした当初、“ハーレム出身のトリオ”という経歴がまかり通っていたが(実はメンバーのひとりがニューヨークのサウス・ブロンクスの出身だったりする)、現在では“ニュージャージーのイングルウッドで結成された”と紹介されている。真偽のほどは判らないものの、そもそも“ジャンク・ミュージック”、“ただの騒音”と蔑まれていたラップ・ミュージックのアーティストについての情報など、ヒップ・ホップ黎明期には甚だアヤシイものだった。その証拠に、今から20年ぐらい前、ニューヨークのヒップ・ホップ専門のあるインディ・レーベルに所属しているアーティストの経歴を調べようとオフィスに電話したところ、電話口に出た女性はあっけらかんと「私たち、誰ひとりとして彼(=筆者が大好きだった同レーベル所属のDJ)の年齢を知らないのよ」と言われたことがある。
また、この曲がリリースされた当時、同じ年にリリースされて大ヒットしたシックの「Good Times」(全米No.1/R&Bチャートでは6週間にわたってNo.1/ゴールド・ディスク認定)のバック・トラック(早い話がカラオケ)を無許可でそのまま用い、それに載せてラップしていると言われたものだが、後年になり、「Rapper’s Delight」はシックのバック・トラックをサンプリングしつつも、新たに生演奏を加えていたことが判った。かつてラップが別名“リサイクル・ミュージック”、“ストリート・ミュージック”と呼ばれたのは、第三者の楽曲のバック・トラックを使ったり、その一部をサンプリングしたりして曲を作り、加えて、まだラップがレコード化されなかった頃、ラップを聴くことのできる場所は野外(公園や路上)だけだった、というのがその理由。シュガーヒル・ギャングのレーベルメイトでもあったグランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイヴにはメッセージ色の濃い楽曲もあったが、ラップ・ミュージックの基本は“青空の下でみんなで楽しく踊る”ためのパーティ・ミュージックだったのだ。よって、その歌詞に綴られているのは、ごく日常的な出来事や、パーティの様子の描写などが多い。もちろん、この「Rapper’s Delight」もノリのいいパーティ・ソングである。
曲の要旨
みんなでこの曲に合わせて楽しく踊ってくれ。俺たちは、ラップのテクニックもルックスもサイコーのトリオさ。高級車だって持ってるんだぜ。そんな俺たちに女の子はイチコロ。俺たちの曲を聴いたら、身体がムズムズしてきて踊りたくなるに決まってる。さぁ、みんなで声を合わせて“ホテル、モーテル、ホリデイ・イン”って言ってみな。それにしても、友だちの家に食事に招待された時、料理がマズかったりすると悲惨だよな。例えばフライドチキンが木みたいに硬かったりしてさ。そんなことより、この場では大いに盛り上がろうぜ。みんな、とことん踊りまくってくれよ。
1979年の主な出来事
| アメリカ: | スリーマイル島の原子力発電所で大量の放射能漏れ事故が発生。 |
|---|---|
| 日本: | 携帯用小型カセットテープ・プレイヤーのWALKMANをソニーが発売。 |
| 世界: | イギリスでマーガレット・サッチャーが同国初の女性首相に任命される。 |
1979年の主なヒット曲
I Will Survive/グロリア・ゲイナー
Tragedy/ビージーズ
Good Times/シック
Sad Eyes/ロバート・ジョン
Pop Muzik/M
Rapper’s Delightのキーワード&フレーズ
(a) hip hop
(b) to a T
(c) fly
とにかく長い曲である。最長の12インチ・ヴァージョンは、約15分(!)もある。そして自分たちの自慢話や、日常の出来事を延々と語るのだ。ハッキリ言ってしまえば、メッセージ性のカケラもない。でも楽しい。パーティ・ソングはこうでなくっちゃ! ただ、ダンス・フロアでは15分の曲を流せても、ラジオではとても無理である。ラジオでのオン・エア用に作られたシングル・ヴァージョン(英語では“Radio Edit”という)は、12インチ・ヴァージョンの約3分の1の5分足らず。シングル・ヴァージョンは、何だか尻切れトンボのようだ。筆者は今でもラップ・ミュージックはアナログ盤で聴くのを好むが、特に12インチ・シングルで聴くのが大好き。カッティング・レヴェルの高さはもちろんのこと、このまま曲が永遠に続くかと思われるほどに演奏時間が長いところがいい。それらを耳にする時、ヒップ・ホップがこの世に誕生した頃、ラップ・ミュージックがイコール“ダンス・ミュージック”と捉えられていたことにも納得する。7インチのシングル盤も大好きだが、ラップに限って言えば、12インチ・シングルに優るものはない。
ヒップ・ホップ・カルチャーの誕生期にラッパーたちが活躍した時代を俗に“オールド・スクール”と呼ぶが、シュガーヒル・ギャングは、パーティ・ソングで最も名を馳せたグループだった。2010年頃から小さなハコでまたライヴを開始したようだが、当然ながら、この「Rapper’s Delight」は昔も今もステージには欠かせないだろう。当時、ラップ・ナンバーが全米トップ40入りするだけでも奇蹟のような出来事だったのだから。そして全英チャートでは堂々のNo.3を記録した、ということに驚かされる。基になったシックの大ヒット曲「Good Times」(全英チャートではNo.5)との相乗効果だったのだろうか(しかも全英チャートでは「Rapper’s Delight」の方がランクが上!)。
(a)は、ハイフン入りの“hip-hop”、もしくは大文字のHを用いて“Hip-Hop”と表記しても意味は同じ。今では日本でもカタカナの“ヒップホップ”でも通じるが、筆者は中黒(・)なしのその表記にはどうしても馴染めない。もともと造語であり、ワン・ワードではないからだ。(a)はヒップ・ホップ・カルチャー全般を指す場合もあるし、ラップ・ミュージックを指す場合もある。そしてこの点が肝心なのだが、ラップ・ナンバーで、初めて(a)の言葉が歌詞に登場したのがこの「Rapper’s Delight」であると、遥か以前にオールド・スクール時代からのラップ愛好家が教えてくれた。“hip”は1940年代頃からアフリカン・アメリカンの人々(特にジャズ・ミュージシャンたち)の間で用いられてきたスラングで、「カッコいい、楽しい、流行に敏感な」という意味を持ち、“hipster”には「流行に敏感でお洒落な人」という意味の他に「ジャズ愛好家」という意味もある。その“hip”と語呂合わせが良かったのか、たまたま“hop”とつなげた造語が今では堂々と普通の英和辞典にまで載るようになった。新語の誕生秘話には、興味が尽きないものである。
過去に洋楽ナンバーで何度か耳にしてきた(b)は、辞書の“T, t”の項目にイディオムとして載っており、意味は「完全に、ぴったりと、ちょうどよく」、などなど。“T”は“tittle(小点、点画)”の頭文字で、(b)のイディオムは辞書の“tittle”の項目にも載っており、例えば、以下のように使う。
♪This dress fits me to a T.(このドレス、私にピッタリだわ)
数々のメッセージ・ソングで人気を博したR&Bアーティストのカーティス・メイフィールド(1942-19999)の代表作に、映画『SUPERFLY』(1972)のサウンドトラック盤がある。タイトルは、1960年代から既にアフリカン・アメリカンの人々の間で「カッコいい、素晴らしい」という意味で使われていたスラングだが、同映画とサントラ盤の大ヒットにより、そのスラングの流行はしばらく続いた。そしていつしか“super”が省略され、同じ意味を持つスラングとして(c)が定着したのだった。1990年代に突入すると、(c)もその基となった“superfly”も廃れてしまったが、2000年代半ば過ぎ頃から突如として再流行し、若いラッパーたちが積極的に歌詞に取り入れ始めた。新陳代謝の激しいスラングが復権するのは非常に珍しい現象なので、あの時は本当に驚かされたものだ。1990年代初期、R&Bやヒップ・ホップ・アーティストを擁するニューヨークのプロダクション勤務の白人男性と雑談した際、彼が苦笑いしながら、「“fly”を歌詞で初めて聴いた時、映画の『THE FLY(邦題:蝿男の恐怖/1958,1986年には同映画のリメイク版も制作され、邦題を『ザ・フライ』といった)』を連想してビックリしたよ」と言っていたのが忘れられない。
ヒップ・ホップ・カルチャーが誕生したばかりの頃、ラップが聴きたい、ラップに合わせて踊りたいと外へ繰り出した人々が、青空の下で楽しんでいる様子を想像すると、自然と笑みがこぼれてくる。ラップ・ミュージックが商業ベースに乗り、音楽の一ジャンルとして定着してから数十年が経つが、1990年代初期にハーレムの外れにある公園で真っ昼間のDJバトルを観戦した経験のある筆者は、青空の下で繰り広げられる在りし日のヒップ・ホップが懐かしくてたまらない。