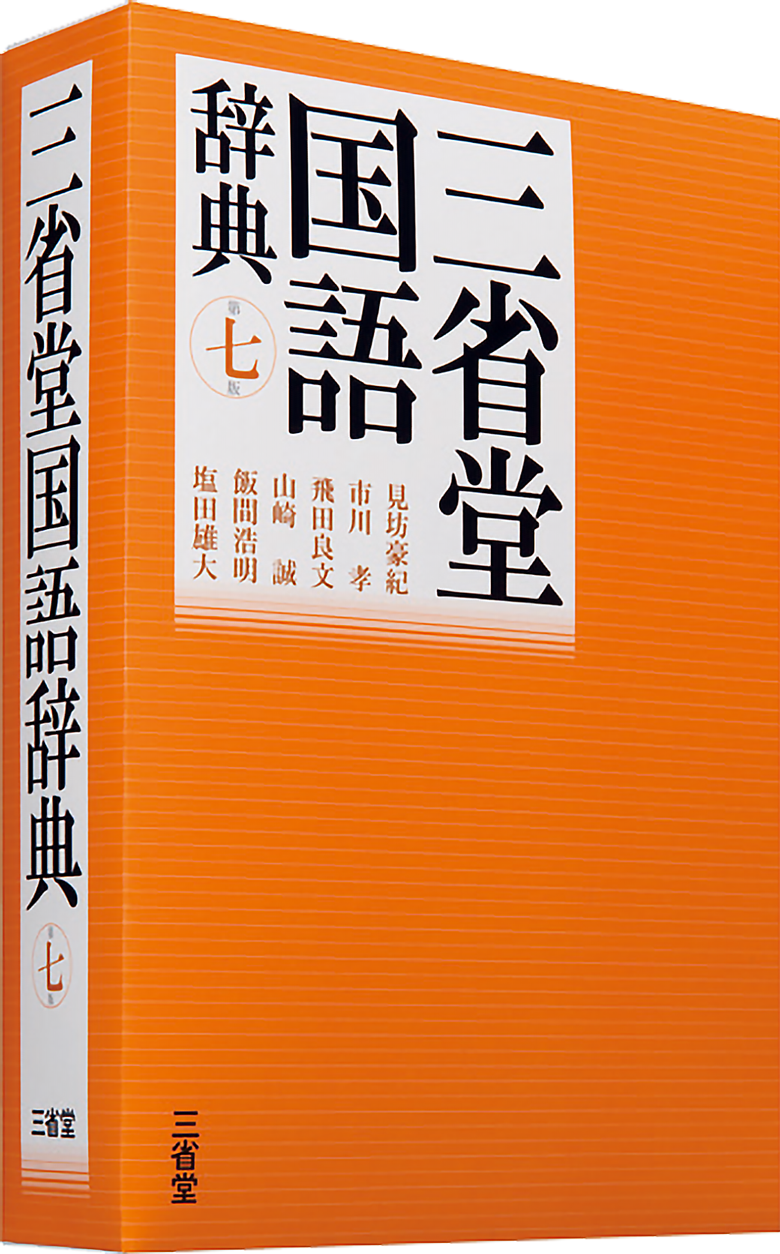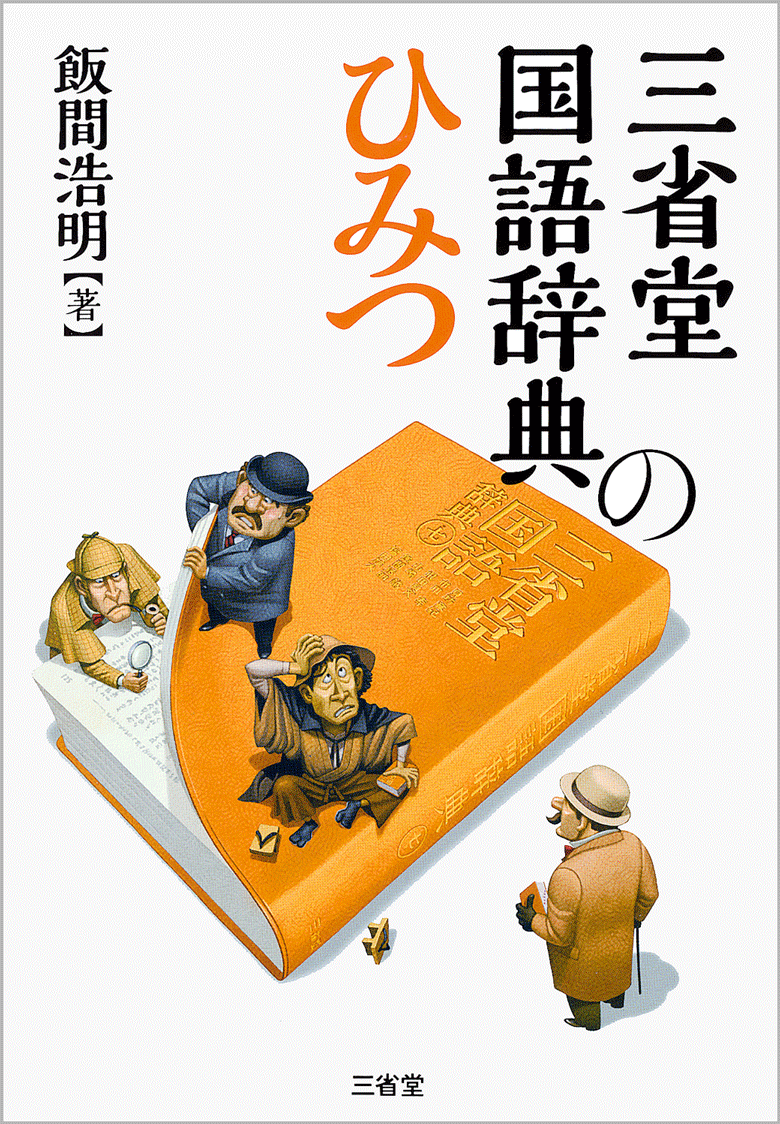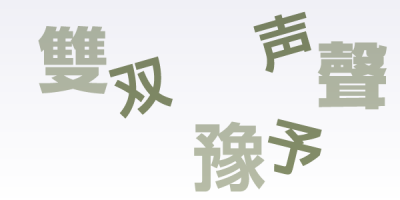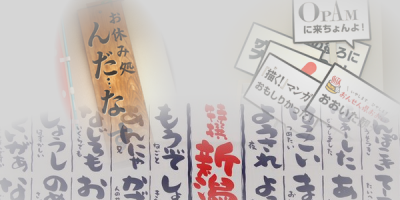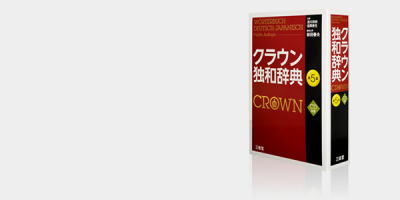東京・世田谷の祖師谷(そしがや)に、「ウルトラマン商店街」という名の商店街があります。近くの砧(きぬた)にある撮影所が、ウルトラマンの誕生の地だからだそうです。入り口広場にはウルトラマンの像が立ち、アーケードには両手を広げたウルトラマンが飛んでいます。

「ウルトラマン」は、1960年代の後半に放送が始まって以来、いくつものシリーズが作られました。私を含めて、多くの子どもたちが熱狂しました。この商店街も、「ウルトラマン」の名を冠したことで、きっとお客が増えたでしょう。
じつは、『三省堂国語辞典』でも、第四版(1992年)から第五版(2001年)まで、「ウルトラマン」という項目を載せていました。放送開始から30年近く経って、キャラクターが広い層に親しまれ、また、比喩としてもよく使われるようになっていました。
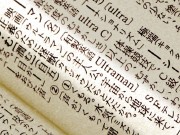
たとえば、1990年に、かのピンク・レディーが2か月だけ再結成することになった時、新聞に、歌手自身のこんなコメントが出ました。
〈MIEは「地球からの要望で宇宙から帰ってきたウルトラマンのような気持ち。うれしい」と語り、〉(『読売新聞』夕刊 1990.9.18 p.11)
このコメントを理解するためには、たしかに、「ウルトラマン」について解説してある辞書があれば、役に立ちます。
とはいえ、同様の事情は、「鉄腕アトム」や「ゴジラ」「月光仮面」「ドラえもん」「おしん」などにも当てはまります。いずれもよく知られ、比喩などにも使われるキャラクターです。「ウルトラマン」が辞書に載るなら、彼らも載っていいはずです。でも、それでは際限がなくなってしまうことも事実です。
今回の第六版では、議論の結果、「ウルトラマン」には退場を願うことになりました。第四・五版での活躍には感謝しつつも、やはり、『三国』には彼はふさわしくないと思います(前後して、別の大きな辞書に「ウルトラマン」が採用されたのは偶然でした)。
もっとも、第六版にも、キャラクターの名前に由来する項目が新しく入っています。「マスオさん」「耳をダンボにする」がそうです。これらは、もはや固有名詞の用法を離れて、一般のことばとして定着したと考えられるからです。