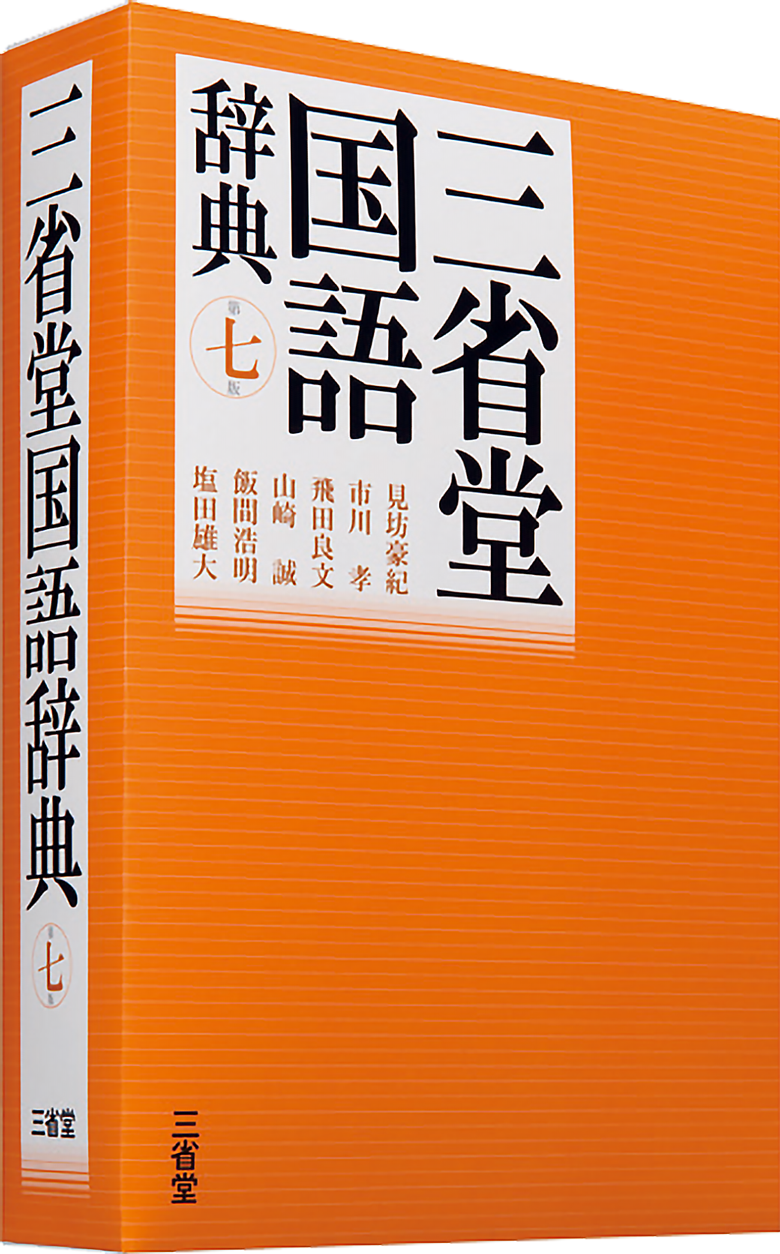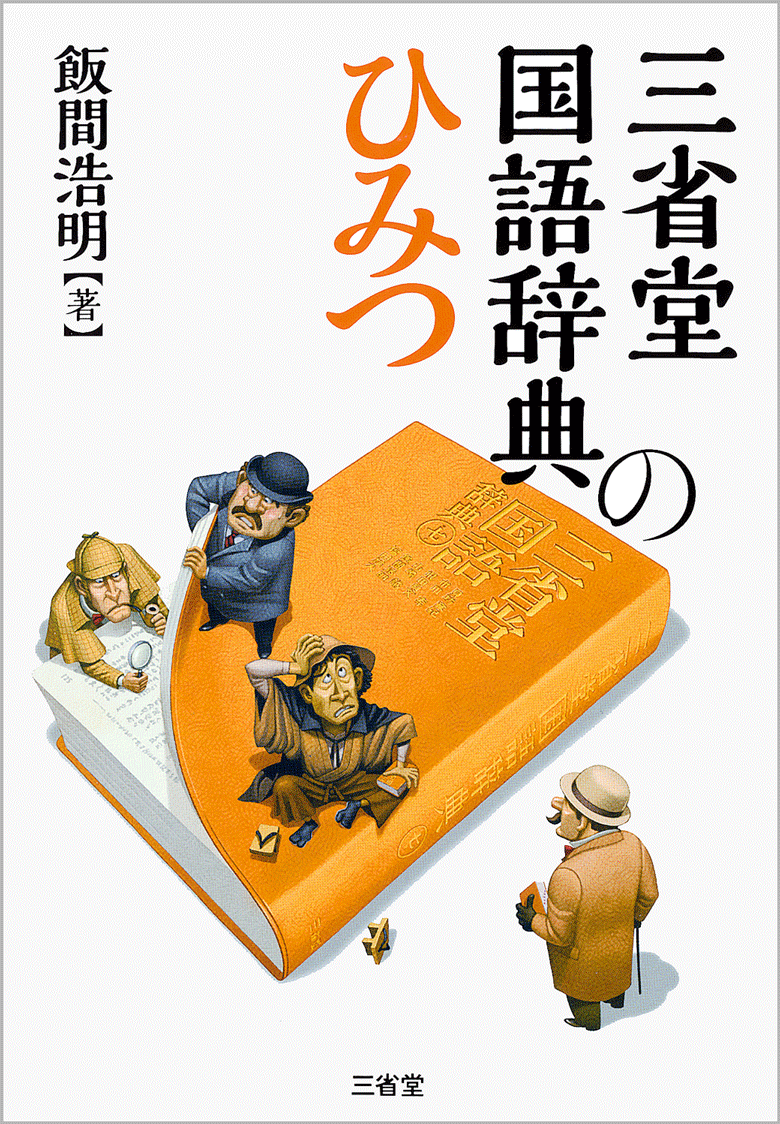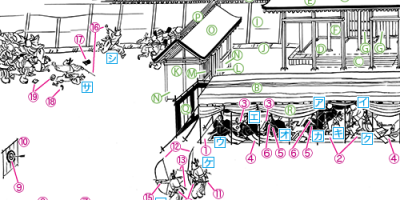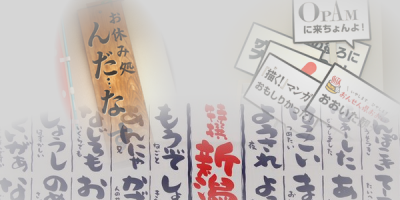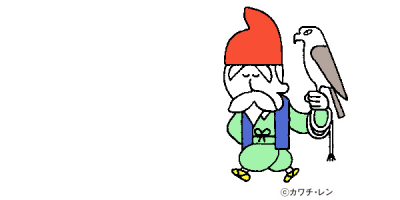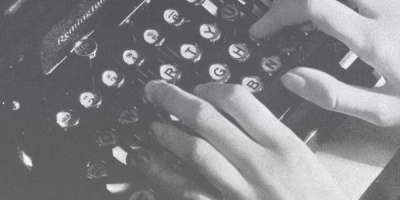最近の社会現象として、すぐ思い浮かぶものと言えば、何があるでしょうか。メイド喫茶? 新型の携帯端末? 地方自治体の「ゆるキャラ」?──いろいろありそうですが、そもそも、「社会現象」とはどういう現象を指すのでしょうか。
ある分厚い辞書を引くと、〈社会に現れる一切の現象……〉と説明してあります。自然現象に対する概念で、人間の社会活動の結果起こる、あらゆる現象をこう呼ぶのです。とすれば、メイド喫茶や最新の携帯端末に限らず、私たちの身の回りで起こる人為的な現象は、なんでも社会現象です。〈犯罪から日常に至るさまざまな社会現象〉(NHK「ドキュメンタリー89」1989.11.1)などという使い方が典型例です。


ところが、一方では、次のような表現に多く接するようになりました。
〈社会現象化している人気韓国ドラマ「冬のソナタ」〉(『毎日新聞』2004.7.9 p.28)
テレビドラマは人間が作ったものですから、もともと社会現象の中のひとつです。それが「社会現象化する」というのは意味をなさないように思われます。ここでは、「社会的に熱狂する現象」という特別の意味で使っているのです。
『三省堂国語辞典 第六版』は、こうした実態を踏まえつつ、「社会現象」を新規項目として採用しました。もとの意味と、特別の意味とを、次のように並べて記しました。
〈1 社会の中のさまざまな現象。2 ブーム。「―になる」〉
2つ目の意味を載せた辞書は、これまでにないはずです。〈ブーム。〉とあっさり一言で説明しましたが、ここに至るまでには試行錯誤がありました。用例によっては、次のように、「ブーム」の大きいものが「社会現象」であるようにとれる表現もあります。
〈〔さぬきうどんの〕ブームは一気に巨大化し、社会現象となってこの街のすべてをその喧噪の中へと呑み込んで行きました。〉(本広克行監督映画「UDON」2006年)

とはいえ、かつての「ミッチー(美智子皇太子妃)ブーム」などは、たいへん大きな騒ぎで、今日ならば「社会現象」と表現されるところです。要するに、両者は同じものと考えられます。ただ、「静かなブーム」「マイ(自分だけの)ブーム」などという言い方が現れ、「ブーム」が小粒に感じられるようになってきたのも事実です。そこで、より強い印象をねらって、「社会現象」が使われるようになったのでしょう。