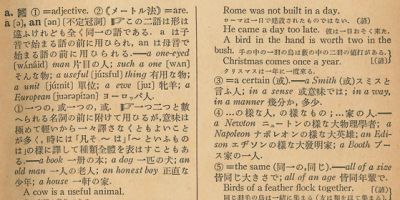●歌詞はこちら https://www.google.com/search?q=hazy+shade+of+winter+lyrics
曲のエピソード
サイモン&ガーファンクル名義の他の大ヒット曲――「The Sound of Silence」(1965)、「Mrs. Robinson」(1968)、「Bridge Over Troubled Water」(1970/いずれも全米No.1)――に較べれば、チャート的にはそれほど振るわなかったように思われるが、この曲を彼らの最高傑作とする熱心なファンや音楽愛好家は少なくない。彼ら名義の4枚目のオリジナル・アルバム(ライヴ盤やベスト盤などの類ではない、の意)『BOOKENDS』(1968)に収録されているが、それ以前に、ライヴの場で歌われていた。2002年になってからリリースされたライヴ・アルバム『LIVE FROM NEW YORK CITY, 1967』(1967年1月22日にリンカーン・センターのホールで行われたライヴの模様を収録)にこの曲のライヴ・ヴァージョンが収録されている。邦題を「冬の散歩道」という。1994年にTBS系で放映されたドラマ『人間・失格~たとえばぼくが死んだら』で劇中歌として使用されたことにより、サイモン&ガーファンクルの人気が日本で再加熱した。なお、オリジナル・ヴァージョンのリリースから約20年後の1987年、L.A.出身の女性バンド、バングルス(Bangles)がカヴァーし、全米No.2を記録する大ヒット。1980年代の快楽主義の若者たちの日常を描いた映画『LESS THAN ZERO』(1987)の劇中歌で、同映画のオリジナル・サウンドトラック盤に収録されている。
メロディ、歌詞共に哀愁を帯びている。主人公は、夢や希望を追い求めているうちに何もかもが上手く行かなかったと気づき、生きることに押しつぶされそうになっている悩める青年。ポール・サイモンが作詞・作曲したこの曲は、将来に対する漠然とした不安を“a hazy shade of winter(迫りくる冬の気配)”に重ね合わせている。暗く沈みこんだこの青年には、友人の「希望を持てよ」の忠告も耳に入らない。将来への不安は増すばかり…。
曲の要旨
夢を追い続け、希望を抱きながら生きてきた若き青年(注:ポール・サイモンがこの曲を作った時、彼は20代半ばだった)。季節は巡り巡って冬の足音が聞こえてくる。ふと今までの人生を振り返ってみると、何ひとつ自分の思い通りに事が運ばなかったことに気づいて愕然とする。周囲を見回せば、晩秋の空はどんよりと曇り、今にも冬の足音がひたひたと近づいてくるようだ。街路樹の葉は無残にも赤茶けて枯れてしまっている。自分には、早くも人生の晩秋、そして冬が訪れているのだろうか?
1966年の主な出来事
| アメリカ: | NOW(National Organization for Women/全米女性機構)が結成される。 |
|---|---|
| 日本: | ビートルズが来日し、日本武道館でコンサートを行う。 |
| 世界: | 中国で文化大革命(通称「文革」)が始まる。 |
1966年の主なヒット曲
We Can Work It Out/ビートルズ
Good Lovin’/ヤング・ラスカルズ
When A Man Loves A Woman/パーシー・スレッジ
Pain It, Black/ローリング・ストーンズ
Stranger In The Night/フランク・シナトラ
A Hazy Shade of Winterのキーワード&フレーズ
(a) be (so) hard to please
(b) a hazy shade of winter
(c) cup in one’s hand
高校時代、3年間で300個の英作文を暗記させられた。1年間で100個。英語の授業はグラマー(英文法)とリーダーのみならず、英作文も週に何回かあったのである。なので、毎日、英語の授業があった。その英作文の教科書に次のようなセンテンスが載っていたのを今でも忘れられずにいる。
Her husband is hard to please.(彼女の旦那さんは気難しい)
これと同じ表現を「A Hazy Shade of Winter」の歌詞に発見し、高校時代に狂喜乱舞したものだ。書き換えるなら、以下のようになる。
It is hard (or difficult) to please her husband.(直訳:彼女の旦那さんを喜ばせるのは骨が折れる/意訳:彼女の旦那さんはちょっとやそっとのことじゃ喜んでくれない)
この曲の主人公も「なかなか喜ばない」タイプだったようで、「僕はかなりの気難し屋だった」と(a)のフレーズで告白している。思い切った解釈をすると、「ちゃらちゃらしたのが嫌いな人間だった」となるだろうか。ここのフレーズから想像できるのは、主人公が人づきあいが苦手で、周りに迎合するのをよしとしない人物である、ということだ。さぞかし息苦しい日々を送っていたことだろう。
そんな主人公に迫りくるのが、タイトルにもなっている(b)の陰鬱な空気。“hazy”は「霞んだ、もうろうとした、漠然とした、不確かな」という意味で、“shade”はご存知のように「日陰、闇、うっすらとした暗がり」などという意味。ここは、目に見える「冬の霞んだ闇」ではなく、「目には見えないけれど、確かに感じられる冬の気配」を暗喩している。それを曇り空にたとえているわけだ。街路樹にしがみついている、今にも落ちそうな赤茶けた葉っぱは、主人公の「夢も希望も失った」ことへの絶望感を代弁するための比喩として歌詞に登場しており、「自分の人生もいずれは舞い散る落葉のようにはかなく終わってしまうのだろうか」と、不安に掻き立てられている様子が手に取るように判る。直接的な表現を用いていないため、じつに抒情的で詩的な歌詞だ。
字面通りに受け取るとかなり奇妙な光景になってしまうのが(c)。「愛用のカップを手にして辺りを見回せ」と直訳すると、実際にカップを持ちながら外をふらふらと歩いて周りを見回している人を想像してしまう。でもって、その人はかなりアブナい人になってしまう(苦笑)。ここの“cup”も当然のことながら比喩であり、その背景には『聖書』がある。
『聖書』における“cup”は「運命、経験、運命を左右する杯」という意味であり、数えてみたところ、『旧約聖書』では計36回、『新約聖書』では計31回、合計67回もそうした比喩として“cup”が登場していた。もちろんこの曲でも「運命」の意味で用いられており、「自分の運命をしっかり受け止めて世間一般を見渡してみろ」と言っているのである。このフレーズは、自分自身を鼓舞させるものであり、この曲を聴いている人々へのメッセージでもある。
20代半ばの青年が綴ったにしては、どこか老成していて絶望感すら漂う歌詞である。そうしたこともあってか、曲の完成度は高いのに、これはサイモン&ガーファンクル名義の名曲にしてはさほどヒットしなかった。むしろ、後年になってから評価が高まった曲、と言っていいだろう。歌は世につれ、世は歌につれ、という。この曲全体に漂う絶望感と閉塞感が、1966年から時を経てまたぞろ世間を覆い尽くした、と考えるのはうがちすぎだろうか。