『三省堂国語辞典』の改訂がなされ、まもなく第6版が店頭に並ぶという。
この「三国(さんこく)」の略称で親しまれてきた国語辞書は、見坊豪紀(けんぼう・ひでとし)先生が、実際の文学作品やマスメディアなどの中から、新しい語、辞書から落ちていた語などを見付けるたびに、それをカードに地道に記録し、その蓄積を元に編み上げた、実証性に富む辞書であった。
見坊先生の極めて高感度の「アンテナ」に集まる用例は膨大なものであり、そこから導き出された掲出語は、特にその「活きの良さ」で知られていた。この辞書の編纂に打ち込むために、国立国語研究所を退職されたと聞く。ことばと伴走され続けた一生だった、とも評されたが、たった一例ずつであっても、個々の例を見付けていく楽しみと、それを元にして真の現象を追いかけ、さらにそれを生み出す背景の真実に迫ることで、知ることの歓びをかみ締めていらしたのでは、と想像する。
『三省堂国語辞典』は、実は、見出し語の漢字表記の欄においても異彩を放っていた。例えば、第1回で扱ったような地域文字であっても、使用の稀ではないものについては採用していた。たとえば「潟(かた)」には、新潟を中心に残っている略字「泻」が併記されていた。

【写真1 第4版「かた」】
また、石炭を掘った後の岩石を意味する「ずり」には、「 」という、炭鉱労働に従事する社会集団に遍在する文字が示されていた(後に硑となる)。つまり、特定の社会で通用するような字も拾い上げていたのだ。こういう特定の社会集団で使用されるような文字を、筆者は「位相文字」と呼んでいる。寿司屋の隠語や学生ことばなど、ある社会集団に特徴的な語のことを日本語学では「位相語」と呼ぶのだが、それを応用した用語である。この「
」という、炭鉱労働に従事する社会集団に遍在する文字が示されていた(後に硑となる)。つまり、特定の社会で通用するような字も拾い上げていたのだ。こういう特定の社会集団で使用されるような文字を、筆者は「位相文字」と呼んでいる。寿司屋の隠語や学生ことばなど、ある社会集団に特徴的な語のことを日本語学では「位相語」と呼ぶのだが、それを応用した用語である。この「 」は、新聞に投稿された俳句を根拠として、『三省堂国語辞典』に採用したものだそうだ。これらについてお尋ねした筆者の拙い質問状にも、たいへんご丁寧に細かな字でお返事を下さったものであった。
」は、新聞に投稿された俳句を根拠として、『三省堂国語辞典』に採用したものだそうだ。これらについてお尋ねした筆者の拙い質問状にも、たいへんご丁寧に細かな字でお返事を下さったものであった。

【写真2 第5版「ずり」】

【写真3 第6版「ずり」】
極め付けは、動物の「てん」という項目であった。そこには「貂」という、どの辞書にも示される漢字のほかに、「 」という字が掲出されていた。これは、漢和辞書を含め、他のいかなる辞書にも収められていない、不思議な字である。この字のことが気に掛かり、三省堂で辞書編集を担当されている方に、見坊先生が遺された膨大なカードを調べていただけないかと依頼してみた。すると熱心にお調べ下さり、また飯間浩明氏も協力してくださり、見坊先生による「てん」の当該カードには、新聞に挟み込まれていたような、毛皮に関するチラシの切り抜きが、几帳面に貼り込まれていたことが判明した。それは、ゴシック体で作字された版面である。このことから、毛皮業界あたりの位相文字であったのではなかろうか、と推測される。
」という字が掲出されていた。これは、漢和辞書を含め、他のいかなる辞書にも収められていない、不思議な字である。この字のことが気に掛かり、三省堂で辞書編集を担当されている方に、見坊先生が遺された膨大なカードを調べていただけないかと依頼してみた。すると熱心にお調べ下さり、また飯間浩明氏も協力してくださり、見坊先生による「てん」の当該カードには、新聞に挟み込まれていたような、毛皮に関するチラシの切り抜きが、几帳面に貼り込まれていたことが判明した。それは、ゴシック体で作字された版面である。このことから、毛皮業界あたりの位相文字であったのではなかろうか、と推測される。

【写真4 第3版「てん」】
見坊先生が亡くなられた後の改訂で、この辞書特有のこういった見出しの漢字は、多くは削除されたと聞いた。辞書としては異例のそれらを削ることは、辞書上の表記に対して抱かれる規範意識からしても、自然な流れであったのかもしれない。現実を映し出す「鏡」としての辞書よりも、こうあるべきだという標準を示す「鑑(かがみ)」(*1)としての辞書に、文字については比重が傾いたのかもしれない。
しかし、今回の改訂では、「最新の表記の実態に基づ」くという方針(序文)に沿ったものであろうか、少し変化が見られる。たとえば生物の「えび」の項目に「蛯」という表記も採用された。近代の国語辞典としては、史上初のことであろう。これは、「えび」の漢字表記について、筆者が追跡した結果を、「もじもじカフェ」(//www.moji.gr.jp/cafe/)などでお話ししたことに原因があると仄聞する。「蛯」は、固有名詞、つまり姓や地名、店名などとしてはもちろんだが、普通名詞としても、確かに現代の日本で、実際に使用されることがあるのだ。時代による変化はもちろんだが、地域的な偏り、さらに性別や趣味などによっても使用傾向や認知度に差が見られる字なのである。この現象については、回を改めて述べていきたい。

【写真5 第6版「えび」】


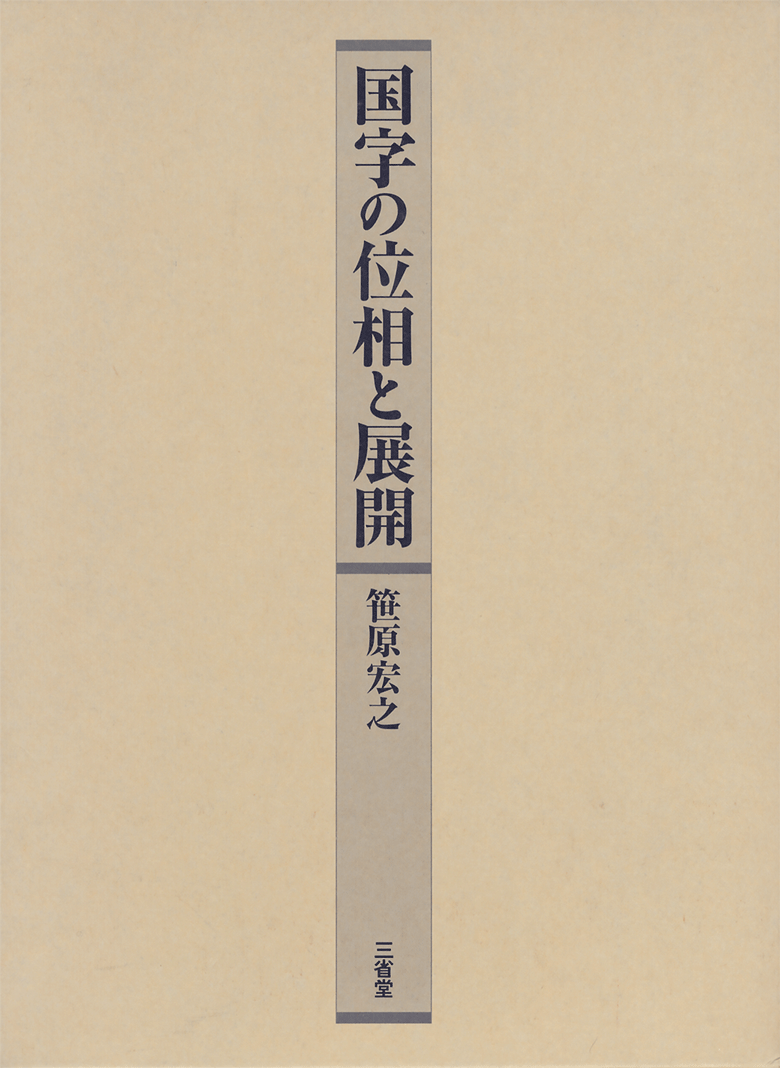
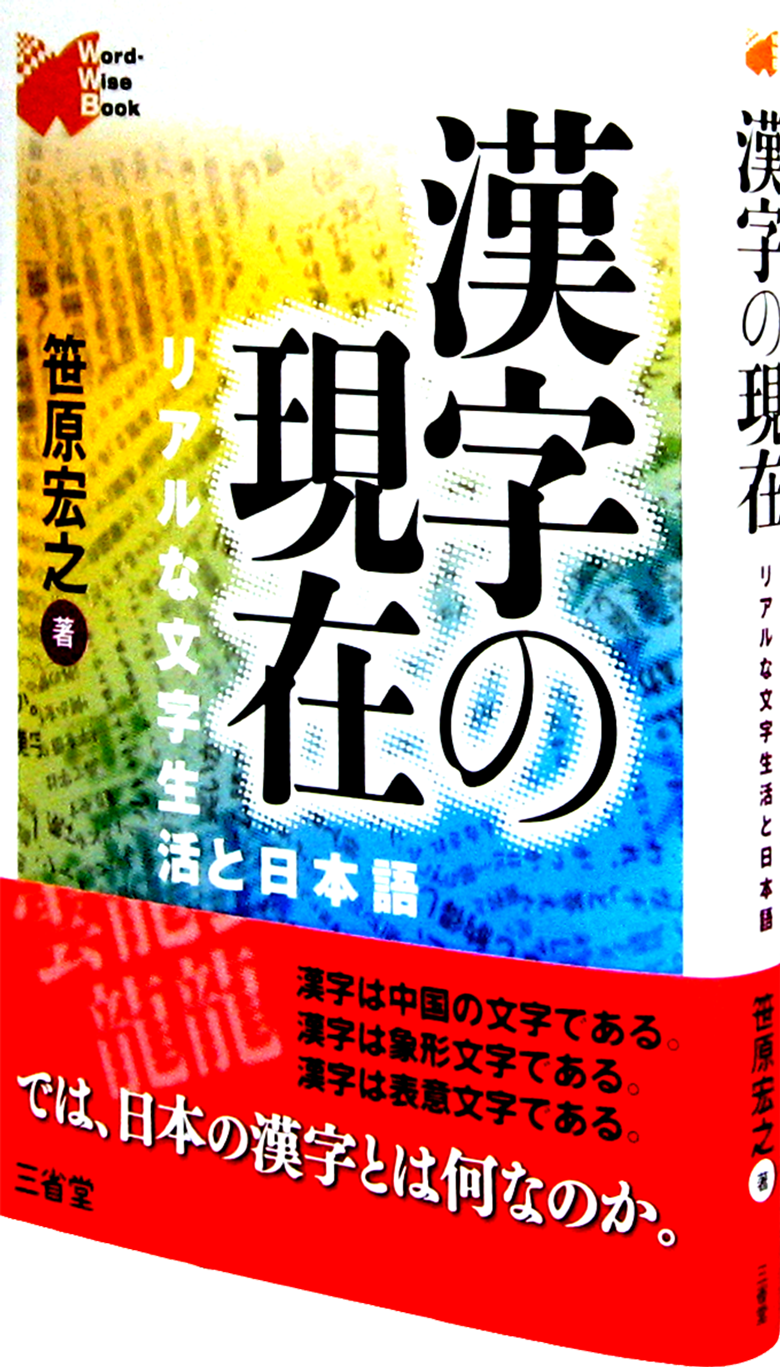




【注】