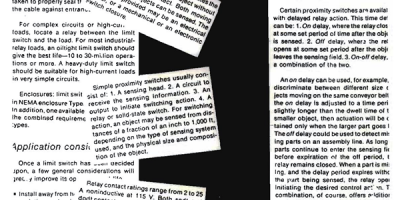ここで少し話が転じます。続きを読んでみましょう。
さて物に就て prejudice, superstition の二ツあり。臆斷とは自分流儀に事を決するを言ひ、惑溺とは徒らに事を信するにあり。其二ツの生する所以は眞理を得さるにあり。例へは今彼處に狐ありて能く人を欺らかすといへは、其を徒らに信して實に狐は人を欺くものなりとせり。是を惑溺と言ひ、又人ありて狐の人を欺く能はすといふ所以の理を知らすして、徒らに狐は人を欺くものにあらすとなす、是を臆斷といふ。
(「百學連環」第41段落第21文~第25文)
ここでは、prejudice と superstition の左側に、それぞれ「臆斷」「惑溺」と添えてあります。また、「欺らかす」の「欺」にはその右側に「タフ」とルビが振ってあります。では、現代語にしてみましょう。
さて、物事については「臆断(prejudice)」と「惑溺(superstition)」の二つがある。「臆断」というのは、自分の〔得手勝手な〕流儀で物事を決め込むことをいう。「惑溺」というのは、やたらと物事を信じ込むことである。なぜこの二つが生じるのかといえば、それは真理を得ないからだ。例えば、いま「あそこに狐がいるが、あれは人を騙すぞ」と言われて、それを無闇に信じ、「本当に狐は人を騙すものだ」と思うようになる。これを「惑溺」という。また、ある人が「狐は人を騙したりしない」ということについて、その訳を知らずに、ただ闇雲に「狐は人を騙したりしない」と思うのを「臆断」というのである。
「臆断(prejudice)」と「惑溺(superstition)」という言葉が出てきました。まず、これらの語彙について少し眺めてみましょう。
まず「臆断」ですが、これは日本語としては、「憶測(臆測)で物事を判断すること」でした。つまり、本当かどうかは分からないけれど、自分としてはこうだと思う、思いたい、そこでこう判断するというわけです。もう少し言えば、実際にどうなのかではなく、その判断をする人の頭のなかだけのお話です。
西先生は、この言葉を英語の prejudice の訳語として当てています。この prejudice という言葉は、現在では「偏見」や「先入観」などと訳されることが多いでしょうか。ラテン語の praejudicium に由来して、prae(予めの)、judicium(審理、判断)、つまり「予審」「予断」という意味を持つ言葉でした。
また、「惑溺」は、「惑い溺れること」ですね。なにかに惑い溺れこんでしまう様子を指します。現在では、あまり使われているのを見かけない気もしますが、私たちは相も変わらずいろいろなものに惑溺し続けていますから、あながち無縁の言葉ではありません。こちらは superstition の訳語として使われています。いまならさしづめ「迷信」とでも訳すところですね。
これらの言葉に触れて、はしなくも思い出されるのは福澤諭吉です。西先生とともに明六社の同人でもあった福澤は、例えば『文明論之概略』(明治8年=1875年)などの著作で「惑溺」という言葉を多用しています。
西洋学術の総覧を試みる「百学連環」の文脈に合わせて引くなら、「陰陽五行の惑溺を払わざれば窮理の道に入るべからず」といった福澤の一節は、西先生の関心に響き合うものがあります。また、同書には「臆断を以て先ず物の倫を説き、その倫に由て物理を害する勿れ」という具合に、「臆断」という語もしばしば使われています。
これはたまさか西先生と福澤諭吉という二人の知識人による用例を挙げただけではあります。しかし、二人がともに(少なくとも学術という営みにおいては)「臆断」と「惑溺」とを「真理」を疎外する悪しきもの、退けるべきものと見て、これを唱えている様子は、なにか彼らが向き合っていた状況を浮かび上がらせるようにも思えて印象深くもあります。
さて、「百学連環」に話を戻しましょう。西先生は、人がどうして「臆断」と「惑溺」とに陥ってしまうのか、その理由を説いています。つまり、真理を手にしていないからだというわけです。
これもついでのことではありますが、福澤諭吉も「陰陽五行の妄説に惑溺して事物の真理原則を求るの鍵を放擲したるの罪なり」(『時事小言』明治14年=1881年)というふうに、「惑溺」を「真理」との関係で用いています。真理と相反するものという認識です。
西先生は、狐の例でこのことを補足していますね。面白いのは、「狐は人を騙すぞ」と信じ込み惑わされるのは「惑溺」で、しかし根拠も分からないまま「狐は人を騙さない」と信じるのは「臆断」だと、この例を両面から使っていることです。
素朴に考えると、「狐が人を騙すなんて、迷信に決まってるだろ」と、「惑溺」を退けて終わりそうなものですが、しかしどうしてそう言えるのかという「真理」を知らずしてそう信じ込むこともまた、本当のところを知らないという意味では「惑溺」と五十歩百歩の「臆断」なのであると釘を刺しているわけです。
これは、真理を探究する学術の徒としては、ぜひとも警戒が必要な二つの態度でありましょう。ポイントは、惑溺を退けても臆断に陥っては元も子もないというところだと見ましたが、いかがでしょうか。
デカルトが、確実ならぬ知識は、いったん全て疑わしいものとして退けて、本当に確実であると思えることに基づいて真理に近づこうとした「方法的懐疑」も連想されます。