印刷・出版界の視察のためアメリカにやってきた三省堂の常務・亀井寅雄。その現地助手をつとめていた今井直一は、1922年(大正11)春、ATFからベントン彫刻機を買い入れる契約をむすんだ寅雄に、とつぜんこうもちかけられた。
「活字について研究してみる気はないか?」
寅雄が宿泊するペンシルベニア・ホテルの一室でのことだった。
「印刷が重要なことはもちろんだが、そのなかでも、書物の印刷がいかに大事なものであるかはいうまでもない。社会に有用なりっぱな書物をつくるためには、第一には内容だが、その内容を盛るのにもっともふさわしい、うつくしいりっぱな容器がなければならない。それには用紙、製本、装丁とともに、文字の印刷をすぐれた、読みよいものにする必要がある。文字印刷をよくするためには、よい活字がなければできない。よい活字は、よい母型以外のものから生まれるはずがない。母型や活字をおろそかにして、よい書物を得ようとすることは、木によって魚を求めるにひとしい」
ところが、と寅雄は続ける。
「活字はこれほど重要であるというのに、日本ではあまりにも関心がうすく、なおざりにされているようだ。きみをはじめ、若い印刷技術者諸君はみんな、写真製版やカラー印刷を追い求め、文字印刷をかえりみない。これでよいのだろうか? 欧米に比べて日本の文字印刷があまりにも見劣りするのは、26文字のアルファベットに対し数千字の漢字というおおきなハンディキャップを背負っている結果だということは、認めざるをえない。しかし、ハンディキャップがおおきければおおきいほど、日本の技術者はいっそう奮起し、これを乗り越え、克服する努力をすべきではないだろうか」
寅雄の話は止まらない。
「おおくのひとが研究するカラー印刷をいまから勉強したとて、努力すれば先輩に追いつけるかもしれないが、それで一生を終わってしまう。日本では、活字の研究をしているひとはまだすくない。きみもいまから勉強さえすれば、活字の第一人者になることも不可能ではあるまい。これはもっとも有意義な、やりがいのある仕事ではないか? 三省堂はいま、あたらしい工場の建設計画を立てている。きみがもし将来ともに活版に献身する決心をいだくなら、三省堂はきみにもっとも適したところであるということを、おぼえておいてほしい」
夜のふけるのもわすれ、寅雄は今井を口説いた。
最初に「活字について研究してみる気はないか」と言われたとき、今井は迷った。自分には活版印刷の経験がない。しかも、実業練習生として渡米したほんとうの目的は、パリに行って絵の修業をすることだった。その旅費と学費を得るため、実業練習生の試験を受けたのである(実業練習生には、農商務省から月150円の手当があたえられた)。
しかし寅雄の話は、若い今井の心を強くゆさぶらずにはいなかった。
知らぬ他国で、いままであかの他人だった人からこんなにまで見込まれるという、そんな機会は一生のうちめったにあるものではない。[注1]
そうして今井は、三省堂への入社を決意した。
寅雄は、今井が入社の約束をしてはじめて、ベントン彫刻機の契約のことを打ち明けた。リン・ボイド・ベントンのもとでベントン彫刻機の操作を学ぶことを、このときはじめて、今井は知らされたのである。寅雄は今井にベントン彫刻機のことを託すと、大正11年(1922)3月に日本へと発った。
かくして私の生涯の方向は、このときにきまったのであります。これは一九二二年春のことでありました
今井直一「それは一九二二年のこと」 『亀井寅雄追憶記』
(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)P.51
[参考文献]
- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、
亀井寅雄「三省堂の印刷工場」
今井直一「我が社の活字」 - 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)
- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 橘弘一郎「活字と共に三十五年――今井直一氏に聞く」『印刷界』40号(日本印刷新聞社、1957)
- 「辞典と組んで30年 今井直一氏の業績」『印刷雑誌』(印刷雑誌社、1957年3月号)



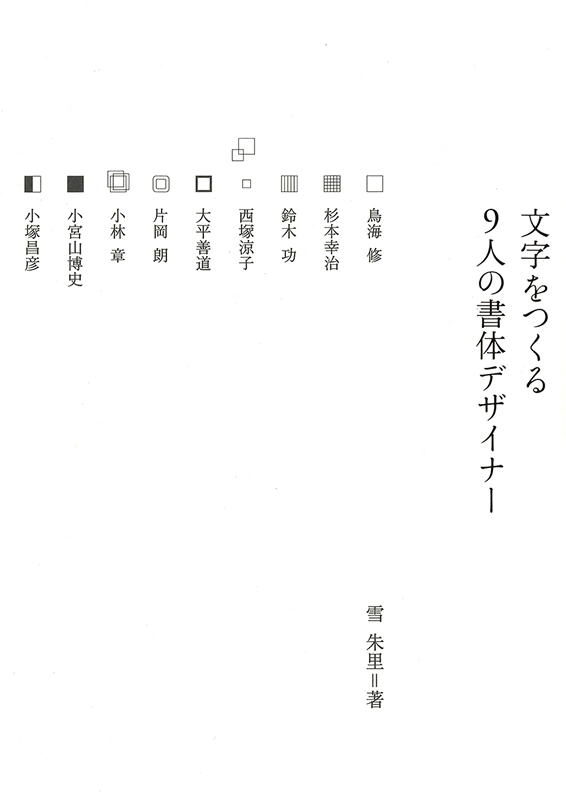




[注]