話はすこし、ベントン彫刻機から離れる。
辞書に使われている紙を思いうかべてみてほしい。あるいは、もしちかくに辞書があるならば、手にとって、そのページをめくってみてほしい。とても薄い紙が使われているのではないだろうか。
辞書の本文用紙には、いろいろな技術がつまっている。辞書は掲載する情報量がおおいため、どうしてもページ数が増え、厚くて重い本になりがちだ。それをできるかぎり薄く、かつ軽くするために、ごく薄で超軽量の紙を使っている。ただし、辞書は両面印刷をして、内容を読ませるものだ。薄い紙を使ってどんなに軽くなったとしても、裏面の印刷が透けて読みにくくなっては意味がない。つまり、辞書の本文用紙は「ごく薄くて軽いけれど透けない(裏うつりしない)、印刷適性のある紙」である必要があるのだ。
この薄い紙はインディアペーパーとも呼ばれ、辞書や聖書などにもちいられている。そして、日本初のインディアペーパーは、三省堂の創業者・亀井忠一の発案によって開発された。忠一の印刷へのこだわりは、専用紙をも生み出していたのだ。辞書の歴史におおきな影響をあたえたできごとでもあるから、ふれておきたい。
明治末ごろ三省堂が辞書に使っていたのは、ベルギー産の「ユニオンB」、日本では「赤門」[注1]と呼ばれる紙だった。当時はまだ国産紙にくらべ舶来紙のほうが品質がよく、三省堂ではもっぱらこの舶来紙を辞書用紙としていたが、忠一には、国産で舶来紙に代わるよい紙ができれば、そちらを使いたいという思いがあった。
忠一はまず和紙の薄葉紙(うすようし。薄い紙のこと)に着目し、これを改良して辞書用紙がつくれないかと印刷局の技師・佐伯勝太郎[注2]に相談した。佐伯から越前に研究者がいると聞き訪ねたが、和紙の改良研究は不発におわった。
このころ忠一は、ポケット用の小型辞典を出版したいとかんがえていた。しかしそれは、薄くて透けない紙が手に入らなければ実現不可能だ(紙が厚いと必然的に本も厚くなる)。忠一は、紙の卸商・中井商店(現・日本紙パルプ商事)の岡本経紀がたずねてくるたびに、「薄くて不透明で裏うつりせず、両面印刷のきく紙がほしい。なんとかなりませんか」と口癖のようにくりかえしたという。[注3]
そこで岡本が王子製紙本社販売部長の井上憲一にたのみ、大阪分社の都島工場で試抄してもらうことになった。忠一がもとめた紙は、つぎのようなものだった。
一)書籍ノ嵩ヲ減ズルタメ能フ限リ薄葉トナス事
二)紙質均一ニシテ不透明ナル事
三)紙面二光澤ヲ有シ且ツ滑カナル事
四)色合純白ナル事
五)塵埃ノ混入皆無ノ事
六)印刷用「インク」ノ滲透ヲ防グ爲メ「サイズ」十分ナル事[注4]

王子製紙・都島工場
王子製紙でこれを担当したのは、都島の当時の工場長・堀越寿助、技師の鈴木金十、真壁豊などだ。しかし開発は、すぐにはうまくいかなかった。裏うつりしないよう不透明度をあげるための填料をおおくすれば、紙質がよわくなってしまう。
大正10年(1921)晩秋に二度目の試抄がおこなわれたとき、忠一は抄造に立ち会うべく、都島工場にむかった。真壁技師が抄造見本をわたすと、忠一は自分のふところから紙を取りだし、
実はこんな紙がほしいんです。この紙はざらついてめくりにくいから、この質ですべりのよい紙ができたら、封度(筆者注:ポンド)二十銭以上五十銭まで出しますから、どうか造って下さい。[注5]
と言った。
その場にいただれもが、はじめて見る紙だった。工場で抄きかけていた紙とはまるで違っていたため、この日の試抄は中止となり、忠一の望みに沿う紙をあらためてつくることになった。
忠一が持参した紙はイギリス製のバイブル用紙だった。聖書のための紙である。真壁技師のもとで紙の開発にたずさわった王子製紙の技師・浅田泰輔が書き残した『インディアペーパー』によれば、忠一の持参した紙は、雪のように白く強靭で、かつきわめて薄く、これまで見たことのないような不透明性を有していたという。[注6]
工場技師たちはどうしたらバイブル用紙のような紙が抄けるのかかんがえたが、なかなか名案がうかばなかった。1カ月ほどたったある日のこと。真壁技師はふと「バイブル用紙は、佐伯勝太郎の著書『製紙術』に登場するイギリス製の『インディアペーパー』に似ているのでは?」と思いあたり、本を読んでみると、やはりそうだった。
その夜、真壁技師は夢を見た。
都島工場でつくっている紙に、「シガレットペーパー(別名ライスペーパー)」という、紙巻きたばこの巻紙がある。インディアペーパーの製法はこれに似ているようだ。ならば、シガレットペーパーをすこし厚めに抄いて、これに適度なスーパーカレンダー(紙に圧力をかけ、平滑さと光沢をもたらす工程)をかけたら、薄くて平滑な、印刷適性のある紙がつくれるのではないか? そうかんがえて、紙を抄く夢だった。
シガレットペーパーには、通常はスーパーカレンダーをかけない。しかし真壁は、夢で見たとおりにやってみた。すると、忠一の持参したバイブル用紙と同じ厚さの紙ができたのだ。そのサンプルを見て忠一も「これでよかろう」と承諾したので、さっそく抄造にとりかかることになった。麻50%に木綿50%をまぜ、不透明にするために填料をシガレットペーパーよりおおめにして、できた紙にスーパーカレンダーをかけたところ、りっぱなインディアペーパーができたのである。
抄造の日、忠一は中井商店の岡本とともに、朝早くからスーパーカレンダーの機械のまえで、紙ができあがるのを待っていた。できあがったばかりの紙を一連(1000枚)だけ断裁してもらうと、それを持って、大阪の市田オフセット会社にハイヤーを飛ばした。
そのときの忠一の様子を、岡本はこう書いている。
会社に着くなり、和服の翁のために用意してあった赤鼻緒の草履には目もくれず、きれいにしてある板張りの工場へ下駄ばきのまま駆け上り、市田氏はじめ技師工員が待機しているオフセット印刷機の前にかけ寄り、物もいわずに紙を差し出した。即席試験の結果は上々であった。もとより印刷インキの性質その他は前以て充分に研究してあったことはいうまでもないが、その時の翁の姿は今もなお眼底に彷彿としている。[注7]
こうして完成した国産インディアペーパーが三省堂に入荷したのは、翌大正11年(1922)春になってからだった。製本可能になるまでに静電気の問題などでまたひと苦労あり、大正11年(1922)8月発行の小型辞典『袖珍コンサイス英和辞典』初版には使えなかったが、大正12年(1923)9月に発行された『袖珍コンサイス和英辞典』では初版からインディアペーパーを使い、期待どおりの薄くて軽く、印刷も両面鮮明な本ができあがった。ただこの初版は、発行日が関東大震災と重なり、すべてが焼失してしまった。[注8]

初版からインディア紙を使用した『袖珍コンサイス英和辞典』(1923、三省堂)
しかしのちに『コンサイス辞典』シリーズはたいへんな好評を博し、「辞書の三省堂」のスローガンをゆるぎないものにした。それだけでなく、三省堂の辞書は「すぐれた印刷と製本が他の追随をゆるさない」とうわさされたのだった。[注9]
※写真は『三省堂の百年』より
[参考文献]
- 『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955)から、
亀井寅雄「三省堂の印刷工場」
今井直一「我が社の活字」(いずれも、執筆は1950) - 今井直一『書物と活字』(印刷学会出版部、1949)
- 『亀井寅雄追憶記』(故亀井寅雄追憶記編纂準備会、1956)
- 亀井寅雄 述/藤原楚水 筆録『三省堂を語る』(三省堂、1979)
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 橘弘一郎「活字と共に三十五年――今井直一氏に聞く」『印刷界』40号(日本印刷新聞社、1957)
- 浅田泰輔『インディア・ペーパー』(1924/紙の博物館により復刻 2003)



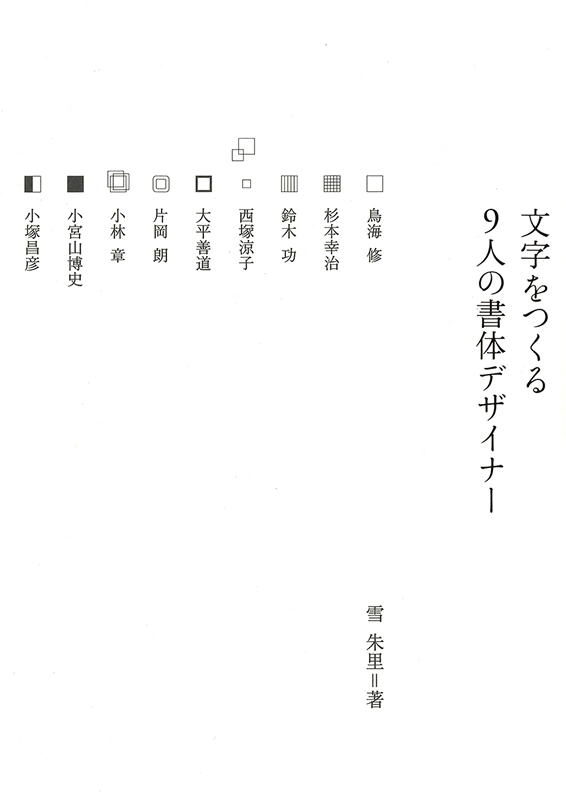




[注]