大正13年(1924)9月1日。三省堂・大手町本社復興から約4カ月、そして、関東大震災から丸1年が経ったこの日、今井直一が中心となり、桑田福太郎らとともに建設計画を進めていた三省堂の蒲田工場が、新工場としての操業を開始した。
新工場は、それまで下請け会社に依頼していた製本部門も含めて、組版から製本にいたる全工程を一貫しておこなうことのできる総合工場だった。〈思えばわが社が出版業をはじめて以来、約四〇年、自営の印刷工場を設けてからでも三〇余年を経て、ようやく自家製本工場を持つこととなったのである〉三省堂の勝畑四郎は、「製本工場の歴史と設備 ――昭和二十年まで――」[注1]という文章にそう記している。
![蒲田工場製本課の外観図。『三省堂の百年』(三省堂、1982)[注2]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp-images/column_benton/benton35_01.jpg)
蒲田工場製本課の外観図。『三省堂の百年』(三省堂、1982)[注2]
自社が出版する本の品質にこだわり、活字まで独自につくる三省堂が、なぜ製本部門だけはそれまで下請けにまかせていたのだろうか。その理由として勝畑は、ひとつは下請けの製本所にめぐまれたことを挙げている。創業者・亀井忠一は、朝から製本所に出向き、終日監督のように指図をした。下請けとはいえ、自家工場とかわらぬ関係性をきずいていたため、自社に製本部門を設ける必要性を感じていなかったのだ。
二番目の理由としては、当時の製本業はおおきな資本を必要とする設備もなく、広大な場所を必要とする大部数の出版物もなかったため、家内工業程度の規模があればよく、いわゆる工場形態の業種ではなかったから、自ら経営する対象としてはかんがえられなかったのではないか、と推測をつづけている。
当時の製本業では、いわゆる「わたりの職人」がおおかったようだ。勝畑の文章にその様子がくわしく書かれており、興味深いので、話はややそれるのだが引用したい。
今日ではちょっと想像できないが、当時、製本に従事する人たちは職人と呼ばれ、職人をもって自負し、箱盤と呼ぶ作業台(当時の製本業は居職の仲間で、作業中はあぐらのままだった。今日のような立姿の作業は大工場ではじまり、次第に町工場にいきわたったのである。松本製本など、戦災で焼けるまで座式作業だった)兼用の道具箱を各自が所持し、職場通いをしたもので、今日の大工や左官と同類だった。当時、官庁では製本職という区分はなく、表具師として扱われていたくらいである。
いわんや、今日見るような終身雇用的な慣習はなく、製本所を転転としてわたりあるく臨時が常態で、常傭になることをきらい、かつ恥とし、常傭となった職人は“老いぼれ”と見る風習が強かった。また当時、職人は一種の資格を意味し、その職人になるには、まず親方の家に徒弟となって住み込み、年季が明けると(満二〇歳の徴兵検査までが一応の目安だった)、はじめて一人前の職人となることができた。勝畑四郎「製本工場の歴史と設備 ――昭和二十年まで――」[注3]
製本業がこのような様子だったため、三省堂も蒲田工場をつくるまでは、製本所を自家工場内に設けようとはおもわなかったようだ。しかし大正10年(1921)に欧米視察に出かけた際、亀井寅雄にはすでに製本工場直営の構想があったようで、行程には製本会社の調査・見学もふくまれていた。[注4]
*
さて、製本所までを含んだ総合施設であった蒲田工場は、はたしてどのような工場だったのだろうか。
関東大震災による建設の一時挫折をのりこえてつくられた同工場は、その経営の基本理念や運営方法、技術の適用などにおいて「あたらしい工場」と注目された。時代は操業から20年後になるが、昭和19年(1944)に『印刷雑誌』に掲載された「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」[注5]という記事から、工場の様子が垣間見える。
記事を書いた馬渡力[注6]は、〈この工場は世の常の印刷所ではない〉[注7]としるしている。なんといっても、蒲田工場は株式会社三省堂という出版社の一組織であって、その出版物を生産するための機関であるということ。だから、独立採算はもとめられず、印刷工場としての収支計算は度外視されるということがおおきい。工場で赤字が出たとしても、それは母体である出版社・三省堂から補填されるのだ。
採算を度外視してでも、出版社である三省堂が蒲田工場をもつ理由と目的は、〈よそで出来ない「美と堅牢」を具有した書物を安く造る〉ことだった。
われわれはその代表作品としてコンサイス辞典を見る。少しでも技術に関係のある人間なら、あの愛すべき小辞典の一冊に打込まれた精妙な工人の腕と良心とに感歎しない者はなかろう。豊麗雪白なインヂア紙、腕時計の歯車のように精巧な微小活字、美しい墨色――これらの綜合して発散する快適さ、これこそ三省堂の武士道精神が生んだ不朽の技術的傑作である。
馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」(印刷雑誌社、1944)[注8]
さらに同記事にしるされている、今井直一が工員に講演したという言葉に、三省堂が蒲田工場にかけた思いがよくあらわれている。
「半世紀の長きに互って算盤に合わぬ仕事をなぜ継続しているのか。……人まかせではどうにも我慢が出来ない、良心が許さない。最良主義に徹せんが為には自ら紙を選び、活字を作り、インキを吟味し、優秀な印刷機械を設備し、一心同体となって製作に従事する立派な工員を得ることが絶対に必要なのである。このやむにやまれぬ良書製作の欲求から我蒲田工場は生まれているのである。」
馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」(印刷雑誌社、1944)[注9]
(つづく)
[参考文献]
- 三省堂百年記念事業委員会編『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」『印刷雑誌』昭和19年5月号(印刷雑誌社、1944)



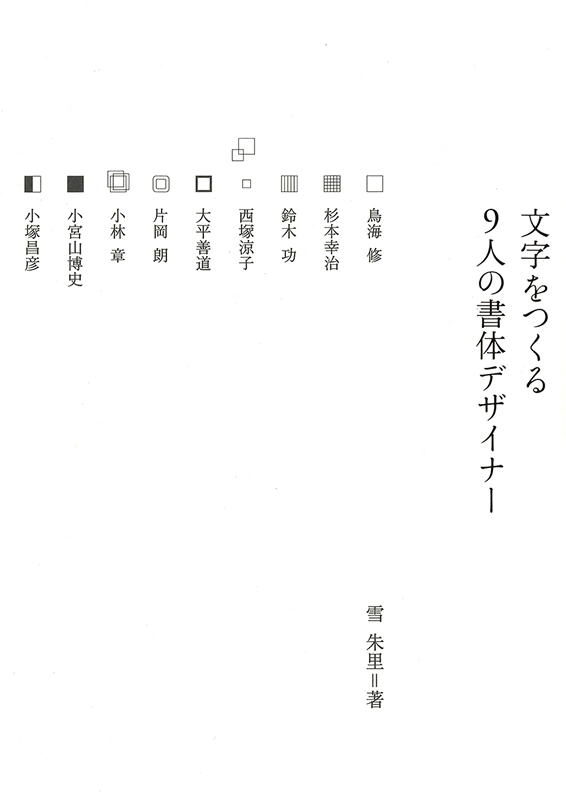




[注]
なお、大正13年9月の製本課は従業員64名でスタート。建物は当初はバラック建てだったが増改築を重ね、最盛期といわれた昭和11、2年ごろ(1936、7年ごろ)は、延べ500坪、機械60台、人数140名を超す大世帯となり、東洋一の製本工場と称されるようになった。同稿P.370より
明治39年(1906)佐賀県生まれ。昭和3年(1928)東京高等工芸学校印刷工芸科卒業後、印刷雑誌社に勤務。昭和21年(1946)印刷学会出版部を創業。代表取締役、日本印刷学会常務理事を兼任。昭和31年(1956)日本印刷共同研究協会常務理事、昭和42年(1967)社団法人日本印刷技術協会常務理事、研究委員長、副会長を歴任。昭和62年(1987)8月31日逝去。享年81際。おもな著書に『印刷術入門』(印刷学会出版部、1949)、『印刷ダイジェスト』(印刷学会出版部、1960)、『印刷発明物語』(日本印刷技術協会、1981)など
https://www.jagat.or.jp/archives/12427