関東大震災での一時建設挫折をのりこえて、大正13年(1924)9月1日に操業を開始した三省堂・蒲田工場は、活字組版から製本にいたるまで、造本の全工程を一貫しておこなえる総合工場だった。
その設備はどのようなものだったのか。操業から20年後に『印刷雑誌』に掲載されたレポート記事「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」[注1]に、くわしくしるされている。20年間で機械台数が増え、建物の増改築をおこなうなど、設備が増強されていると思われるが、当時の様子がなんとなくうかがえる。
記事によると、工場が建設されていたのは〈蒲田仲六郷、重工業とその勤労者住宅とのごった返している一角、新潟鉄工所の巨大な建物の向〉。5000坪の土地に、建坪2400坪の工場が分散的に建てられていた。設備は下記のとおり。
・書籍輪転印刷機 3台
・二廻転印刷機 3台
・平台全判印刷機 20台
・小形機 多数
・写真製版、電気版、鉛版設備一切
・自動活字鋳造機 1台
・植字台数:欧和文 20台
・製本設備一式
・馬力数 218馬力
・工員 200余名
ひところは400名いた工員は、この記事が書かれた昭和19年(1944)のころには半数に減っていた。終戦前の時期である。〈食堂の神棚の下に掲出された出征者の名札の数〉がその理由のひとつを告げていた。[注2]
工場の作業部門は、ここでは純粋に凸版一点張りに整備されている。中でも力を入れてあるのは植字部である。この工場にはとても町の印刷所では引合ったものではない面倒な数式や欧文の組版が無数にある。だから印刷能力よりも植字の方が大きい。一人ひとりが至宝といったような熟練した工人が、目にも止まらぬほど細かい五ポイントの英和辞典の組版に精出している。文撰場のケースは長年の統計から割出された「三省堂常用文字三千字」が出張ケースに番号入で整頓され、欠字の出たケースは、ケース1枚ごと予備ケースと差換えられる。印刷場では全判平台や二廻転で、一分間二十四、五枚の速度で、全紙のインヂア紙が「当てられ」ている。
馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」(印刷雑誌社、1944)[注3]
ひろい敷地に充実した設備をそなえ、腕のよい職人たちが仕事をしていた様子がうかがえる。
神田三崎河岸にあった三省堂印刷所の工場も、そこに入社することを「別荘行き」といわれるほど待遇がよかったが、蒲田工場もまた、待遇のよさは印刷工仲間の羨望のまととなるほどだった。給料はもとより、労働条件も他の印刷工場にくらべ格段のものであり、別名「蒲田女学校」とよばれたほどだ。これは、蒲田工場に通勤する女子工員たちが当時女学校の制服だった紺のはかまを身に着けていたことや、工場内に図書室があり、生花や茶の湯といったクラブ活動もさかんだったことから、まるで女学校のようだということでつけられた呼称である。[注4]
![蒲田工場華道部の様子。『三省堂の百年』(三省堂、1982)より[注5]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp-images/column_benton/benton36_01.png)
蒲田工場華道部の様子。『三省堂の百年』(三省堂、1982)より[注5]
さて、亀井寅雄が今井直一とともにアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)を訪問して買いつけたベントン彫刻機は、関東大震災(大正12年9月1日)前に日本に到着し、一時は行方不明になったものの、横浜の保税倉庫のなかにあったのを今井が見つけていた。しかしベントン彫刻機は、大正13年(1924)9月1日に蒲田工場が操業を開始してすぐに使われたわけではなかった。
三省堂がようやくベントン彫刻機を荷ほどきして組み立てたのは、大正14年(1925)春ごろのこと。蒲田工場が立ち上がって半年ほど経ってからのことだった。
ベントン彫刻機の試刻の開始はさらにあと、大正15年(1926)4月のこと。このころになりようやく、三省堂は写真製版と母型彫刻の作業を研究的にスタートすることになった。植字課と製本課とのあいだに32坪の木造平屋一棟を建築し、ベントン彫刻機やその他の仕上機、研磨機などを設置して、「書体研究室」とした。この「書体研究室」開設のころになり、文字の製図、パターン(ベントン彫刻機で母型を彫刻する際の原版)、母型の彫刻から仕上げまで、全工程ひととおりの作業が進められるようになっていた。[注6]
![蒲田工場に設置された書体研究室。『三省堂の百年』(三省堂、1982)より[注7]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp-images/column_benton/benton36_02.png)
蒲田工場に設置された書体研究室。『三省堂の百年』(三省堂、1982)より[注7]
ここからの書体研究室の成果は、20年後に馬渡力の「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」(印刷雑誌社、1944)にて、こんなふうに書かれている。
あの傑出した可読性と形態美とを兼ね備えた活字の完成のために、この会社及び工場は二十数年の日子と莫大な費用とを投じて、倦むことのない追究をつづけている。
馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」(印刷雑誌社、1944)[注8]
余談だが、蒲田工場建設にあたり三省堂に入社した機械技師の桑田福太郎は、この時期に2つの特許を取得している。ひとつは「活字仕上機」(特許出願公告第3796号/出願人・発明者は亀井寅雄と連名。出願 大正13年5月21日、公告 大正14年3月18日)、もうひとつは活版の「輪転印刷機」(特許出願公告第4381号/出願人は亀井寅雄、永井茂弥と連名、発明者は永井茂弥と連名。出願 昭和2年5月11日、公告 昭和2年11月2日)だ。
蒲田工場の立ち上げ期に、自社のもとめる生産設備を実現すべく力をつくしていたことがうかがえる。
![蒲田工場に設置された書体研究室。『三省堂の百年』(三省堂、1982)より[注7]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp-images/column_benton/benton36_03.png)
桑田福太郎らが特許を取得した「活字仕上機」の図面(特許出願公告第3796号より)
なお、ベントン彫刻機の到着前から書体研究にたずさわっていた桑田は、ようやく試刻がはじまるという大正15年(1926)4月ごろには出版部企画課に異動になり、文字の原図は松橋勝二、ベントン彫刻機による母型彫刻は青木強、仕上げは中野定が担当したという。書体設計も手がけていたはずの桑田が異動になった理由は、あきらかではない。[注9]
異動前の桑田がデザインした三省堂のオリジナル活字書体に「桑田式カナモジ」がある。それはどのような文字だったのか。くわしくは次回でのべる。
(つづく)
[参考文献]
- 三省堂百年記念事業委員会編『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 馬渡力「新しき工場[2]三省堂蒲田工場」『印刷雑誌』昭和19年5月号(印刷雑誌社、1944)
- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)


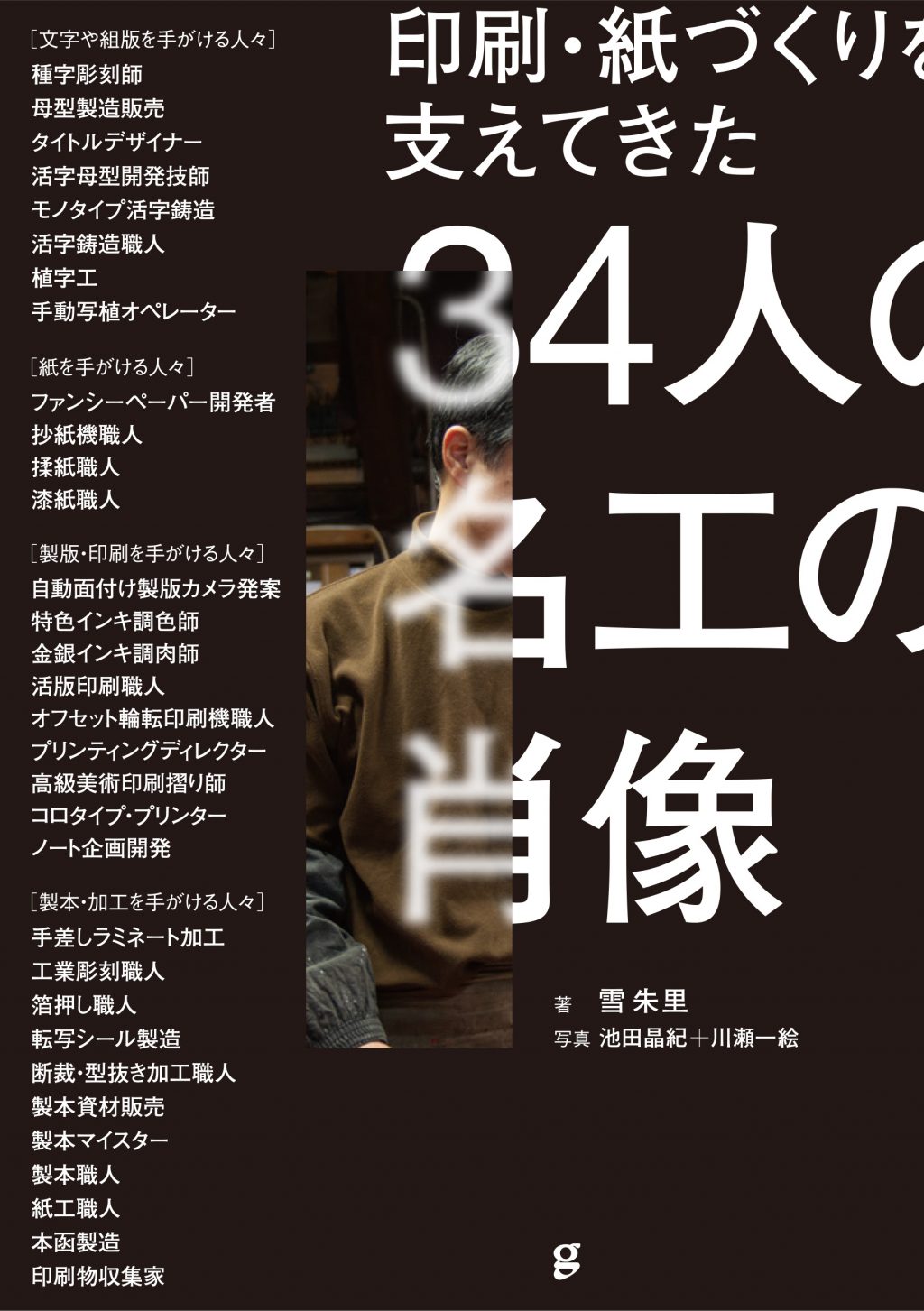





[注]