大正末期から昭和のはじめにかけて、三省堂ではベントン彫刻機で母型を彫るべく、書体研究や原字制作、パターン製作方法の研究などがすすめられていた。パターンとは、ベントン彫刻機で母型を彫るための型である。
前回ふれたように、今井直一がアメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)でまなんできたパターンの製作方法は、文字数のおおい日本語でおこなうには時間と費用がかかりすぎた。そこで三省堂の技師・桑田福太郎は、文字をパーツに分解し、組み合わせてつくる「組立式(組合せ式)パターン」をかんがえ、和文数字や簡単な約物、点物などを練習的に製作した。製作するパターンの数を少なくできれば、デザインする原字も少なくてすむという〈きわめて横着な考え〉[注1]があってのことだ。
これは植字工場でよくやる作字と同じ考え方で、「木へん」とか「草かんむり」とか「しんにゅう」など、共通に使われるものを切りはなしてパタンにする。そうすると組合せでかなり多くの字を作ることができる。たとえば「木へん」の巾を変えたもの二、三種用意すれば、「つくり」を組合せて優に三〇〇字位は作字できる。またその「つくり」にしても、たとえば根の「つくり」艮は根、眼、恨、狼、艱、堤、限などに共通に使えるし、格の「つくり」各は格、挌、恪、絡、酪、珞、烙、洛、賂などと共通する。項とか須などの「つくり」頁は「へん」を変えれば、四十数種の文字ができる。というようなわけで、御利益の方ばかり考えてさっそく実行に移した。真ちゅうの板に多数の小さい穴をあけ、その上に切り抜きのパタンをフックで止め、どんな位置にも自在に固定できるようにした。かくして試刻を何回もくりかえしてみたが、どうもおもしろくない。極端にいえば全然字になっていない。これはあたりまえのことであって、字画による線のバランスや錯覚の現象を無視した結果、当然起るべくして起った大きな誤りなのである。
今井直一「文字の印刷」(日本印刷新聞社、1952)[注2]
けっきょくは、組立式パターンではよい文字ができない、機械的に漢字を分解してパターンをつくることにはむりがあるとわかり、組立式パターンの製作は中止へ。手間はかかれども、1文字1文字を克明にデザインして原字を書き、パターンをつくる方法におちついた。そこで参考にしたのが、東京築地活版製造所(以下、築地活版)のパターン製作法だった。
関東大震災前にアメリカから届いていたベントン彫刻機を大正14年(1925)春にやっと荷ほどきした三省堂に先がけ、築地活版は大正11~12年ごろ(1922~23)からベントン彫刻機をつかいはじめていた。築地活版でのベントン彫刻機活用について、今井直一はこんなふうにのべている。
当時築地活版製造所にはわが社よりも一足先きにベントン彫刻機が据着けられ、宮崎栄太郎、上原竜之介の諸君が同機の研究に当っていた。築地活版では、主として印刷、約物、数字等の彫刻を行い、かなは試刻程度で実用には供せず、漢字は全然問題にしていないようであった。したがって彫刻機は実際面では大して活用されていなかったが、パタンの製作では新機軸を出し、腐蝕法を比較的簡単に製作していた。
今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.30[注3]
本連載第27~31回の増補編でもふれたように、築地活版が今井の言うほどベントン彫刻機を活用できていなかったのかは検証しきれていない。しかし、パターンの製作においては別であったようだ。三省堂が悩んでいたこの問題において、築地活版がおこなっていた「腐蝕法」がおおきなヒントとなったのだ。
(続き)この腐蝕法にヒントを得て亜鉛板に字面を蝕刻する現在のパタン製作法を完成したもので、これは昭和五年頃のことであった。
今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.30[注4]

腐蝕でつくられたパターン(三省堂印刷所蔵)
「腐蝕する」とは、薬液によって金属板などの任意の部分だけをへこませること。たとえば現在、凸版印刷でもちいられている金属凸版は、次のように腐蝕してつくられている。
- あらかじめ感光性の皮膜(ゼラチン質)を塗った金属板に文字を製版したフィルムを密着させ、強い光を当てる
- フィルムの黒い部分(この場合は文字)には光が当たらず、周囲の部分には光が当たってゼラチン質が硬化する
- これを洗うと、硬化していない文字部分だけゼラチン質が洗い流され、金属が露出する
- これを薬液に浸すと、皮膜のない金属部分だけが腐蝕され、へこみができる
三省堂がベントン彫刻機での母型の試刻を本格的にはじめたのは昭和5年(1930)7月ごろのことと思われる。書体研究室の移転がおちつき、実用的なパターン製作方法にたどりついたことで、ようやくベントン彫刻機による母型彫刻の環境がととのったということだろうか。
なお、腐蝕によるパターンを最初に実用したのは「12ポイント用ひらがな」一組で、昭和5年(1930)12月の製作。昭和6年(1931)2月ごろから明朝体の漢字に着手し、独自にさだめた「三省堂常用漢字三千字」のパターンを完成したのは、昭和10年(1935)7月のこと。また、このころからギリシヤ文字やゴシック体など他の書体についても、電胎母型(種字を手彫りしてつくっていた母型)の破損のつど彫刻し、補充した。[注5]
三省堂のパターン製作年代は、表にまとめてのこされている。ひじょうに貴重な記録だ。
![三省堂のパターン製作年代表(今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.31[注6]](https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp-images/column_benton/benton41_02.jpg)
三省堂のパターン製作年代表(今井直一「我が社の活字」(三省堂、1955/執筆は1950)P.31[注6]
こうしてパターンの製作方法も軌道にのり、三省堂は、ベントン彫刻機をもちいた母型彫刻に着手していった。
(つづく)
[参考文献]
- 今井直一「我が社の活字」『昭和三十年十一月調製 三省堂歴史資料(二)』(三省堂、1955/執筆は1950)
- 今井直一「文字の印刷」『印刷界』1952年9月号(日本印刷新聞社)
- 『三省堂ぶっくれっと』No.103(三省堂、1993)


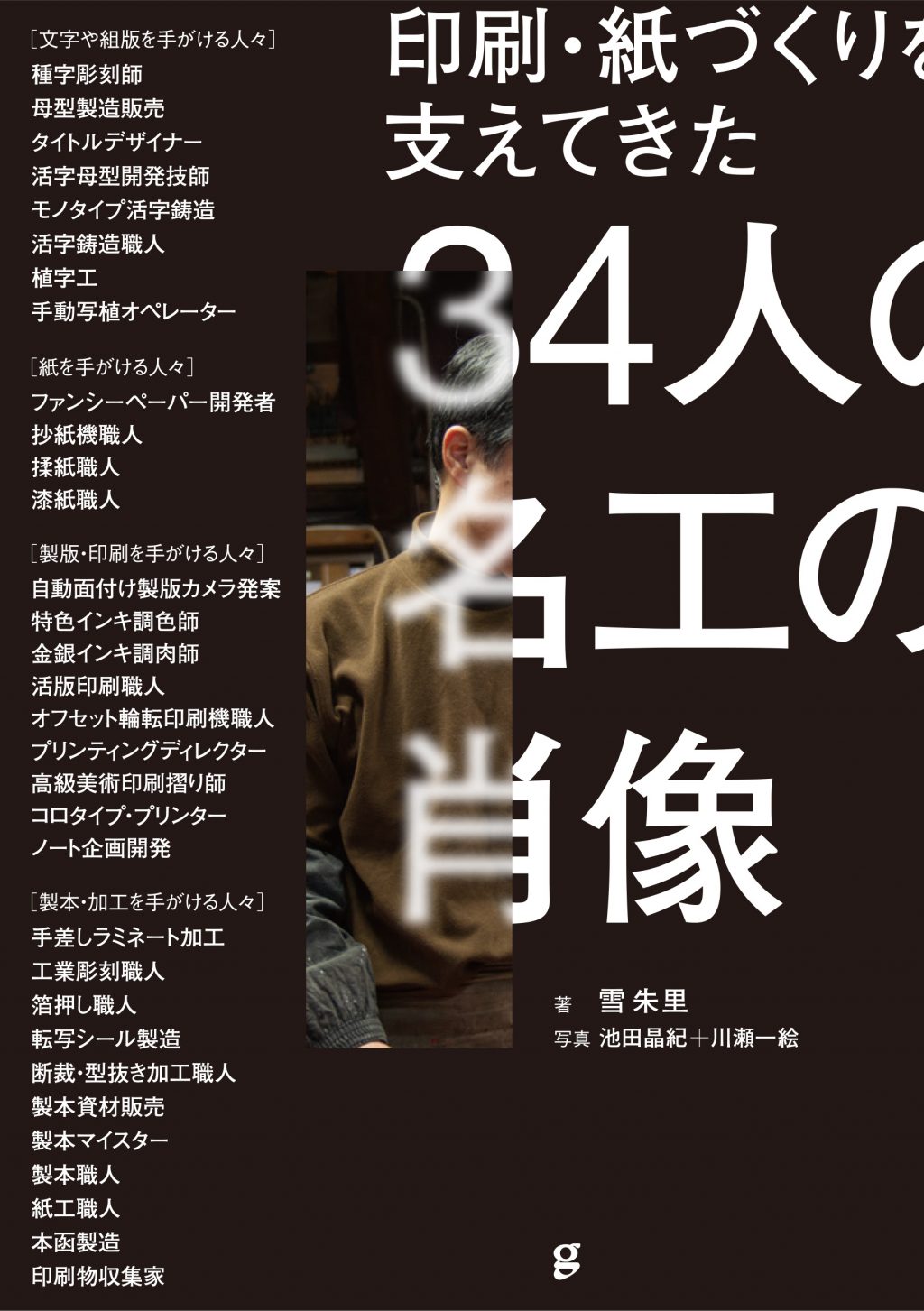





[注]