昭和20年(1945)4月15日、三省堂蒲田工場は空襲により焼失してしまった。しかし前年12月、ベントン彫刻機や活字鋳造機、パターンや活字など、辞書の活字組版に必要な機材・資材の一部を三崎河岸の神田工場に疎開させていたため、三省堂がたいせつにしてきた活字とその生産設備はうしなわれずに済んだ。ベントン彫刻機の疎開は、専務・今井直一の特命をうけた工場技師・細谷敏治のはたらきによるものだった。

焼けのこった神田工場(『三省堂の百年』1982)
当の細谷は、蒲田工場からの重要機材・資材の疎開という任務を終え安堵していたところ、昭和20年3月に召集令状をうけ、同月13日、横須賀海兵団に入隊。4月15日に蒲田工場が空襲をうけたころには、霞ヶ浦航空隊に召集兵100人ほどで移動し、整備兵として配属されていた。機械の好きな細谷は「航空機の整備ができるのでは」とすこし期待を抱いていたが、ひと月ほどで栃木県鬼怒川温泉の変電所の擬装工事要員として同じ部隊で移動。しかしまたほとんどなにもせずにひと月ほど日を過ごし、次は宮城県の松島航空隊に移動した。
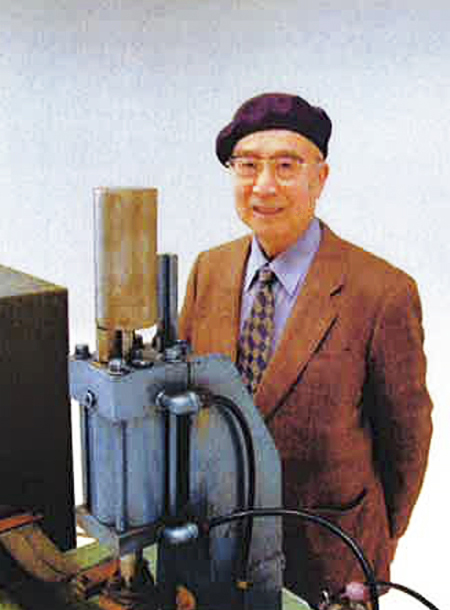
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)に貼られていた写真
今度は前線に出動とか言われて、愈々(いよいよ)かと思っていたが、何の軍事訓練をも受けていない召集部隊では何かなと思っていたがやはり、宮城県の松島航空隊であった。松空といっていた。
此の松空では、毎、朝晩アメリカ空軍艦上機からの機銃掃射を浴びたのであったが異状なく昭和20年8月の終戦を迎えこの松空を最後にして、思いがけずに帰郷することが出来た。戦時中の海軍では、生きて帰郷するのは終戦のためとは言え全く夢物語であった。山形の家に帰ったのである。復員できたのである。全く突然の出来事であった。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
終戦をむかえほっとした細谷は、東京にもどる気のまったく起きないまま、故郷の山形で家族とともに静かにくらしていた。いつのまにか季節は秋になっていた。9月のおわりごろになり、細谷のもとに1通の手紙がとどいた。三省堂の今井直一からだった。
〈元気で復員できて良かった、体調が悪くなかったら、東京に出てきてみてはどうか……〉なにごともなかったかのような便りに恐縮した細谷は、すぐに返事を書いた。田舎の様子や食事、近況など、報告をかねてしたためた。しかし、東京に出て行く気持ちはまったくなく、〈三省堂の工場の作業立ち上がりに必要な資材関係、活字鋳造機3台も地下倉庫に「安置」しておいたのであるから、当分の心配は無い筈〉と手紙に詳細を書いておくり、自身はそのまま山形で過ごそうとかんがえていた。
また静かなのんびりした生活に戻った。三省堂に戻ってまたもとのように仕事につくなどと言うことは、この敗戦国の雰囲気では現実的には全く考えにくいことであった。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
しかし数日後、今井直一からふたたび手紙がきた。〈いろいろ話もあるので兎に角一度上京して欲しい〉。細谷とて、今井に話したいことは山ほどあった。〈東京行きの乗車券が入手次第お伺いしたい〉と返事を出し、数日後には上京して今井に会い、神田工場の倉庫を見た。今井は、これからの細谷の住まいのことなどを話してくれたが、先のことはまだ見当がつきにくい国の状況のなか、〈出来ることから始めるつもりで〉細谷は山形にもどった。昭和20年(1945)10月のことだ。
そして11月初旬、細谷は妻子を山形にのこし、母と2人で上京した。三省堂が第二工場とする計画を立てていた玉川学園の幼稚園舎に細谷は暮らし、そこから神田工場に通勤をはじめた。電車は立錐の余地もない満員電車だった。

三崎河岸の倉庫内に、神田工場はつくられた
さて自分が搬入した機材の問題である。社員は、まだ殆ど誰もいない。文寿堂に移籍した人達は、当然誰も来られない。活字の鋳造作業の人達は、一人も来ていない。文寿堂に移籍してしまっていたのである。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
蒲田工場から空襲で焼けだされた従業員は、文寿堂根岸工場へ移り、働いていた。[注1]
細谷が蒲田工場から運びこんだ活字のストックがあるとはいえ、まずは活字の補充ができなくては、本格的な活字組版(植字)の作業ができない。活字鋳造機の「湯わかし(活字地金の溶融の呼称)」には都市ガスを利用していたが、東京ではまだガスが復活しておらず、その目処もたっていなかった。電気は、動力は復活していなかったが電灯線が復活していた。細谷は電灯線を電熱器として利用する以外に方法はないとかんがえた。
しかし活字地金釜を溶融するのは、普通の電熱器では全然問題にならないことは始めから解りきっている。この問題を解決しなければ、植字組版作業が不可能である。つまり、三省堂の仕事を進めることが出来ないと言うことになるので、絶対に溶融問題は解決しなければならない決意で考えた。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
細谷はけっきょく、地金釜をすっぽりとおおう形状の電熱器をつくってみることにした。千葉県浦安市にある素焼き工場に行き、地金釜に合う寸法のおおきな素焼きのどんぶりのようなものを焼いてもらい、その側壁に電熱用のニクロム線をはいまわして、電熱装置をつくった。ここに鋳造機の地金釜を入れ、期待と不安で胸をいっぱいにしながら電気をとおしてみた。
通電して待つこと約20分、でも、地金は溶けないが、期待が持てる状態に釜の地金の変化が現れてきた。それから25分つまり最初から45分経過して地金釜の活字合金が完全に熔解したのであった。そして、活字の鋳造が可能な温度まで湯(熔解した地金を通称「湯」と言っていた)の温度が昇ったのであった。従来のガス装置の場合は30分であったが、電熱では約45分であったが、完全に成功である。これで総てが完了してしまったような気分になってしまった。三省堂の活字植字組版が何の支障もなく進められる。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
やがて、戦場からの帰還者や引揚者、文寿堂工場への転出者などがつぎつぎと三省堂に復帰してきた。電気やガスの供給事情がいちじるしく悪化していたことを改善すべく、昭和21年(1946)7月には自家発電設備が設置された。こうして、三省堂神田工場は終戦後のスタートを本格的に切ることができた。[注2]
ベントン彫刻機は3階に設置されることが決まり、附属施設とともに配置された。彫刻室のとなりは今井直一のいる役員室となった。そしてここから、日本の活字界における大革命ともいえるできごとがはじまるのである。――ベントン彫刻機の国産化だ。
(つづく)
[参考文献]
- 『三省堂の百年』(三省堂、1982)
- 細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)


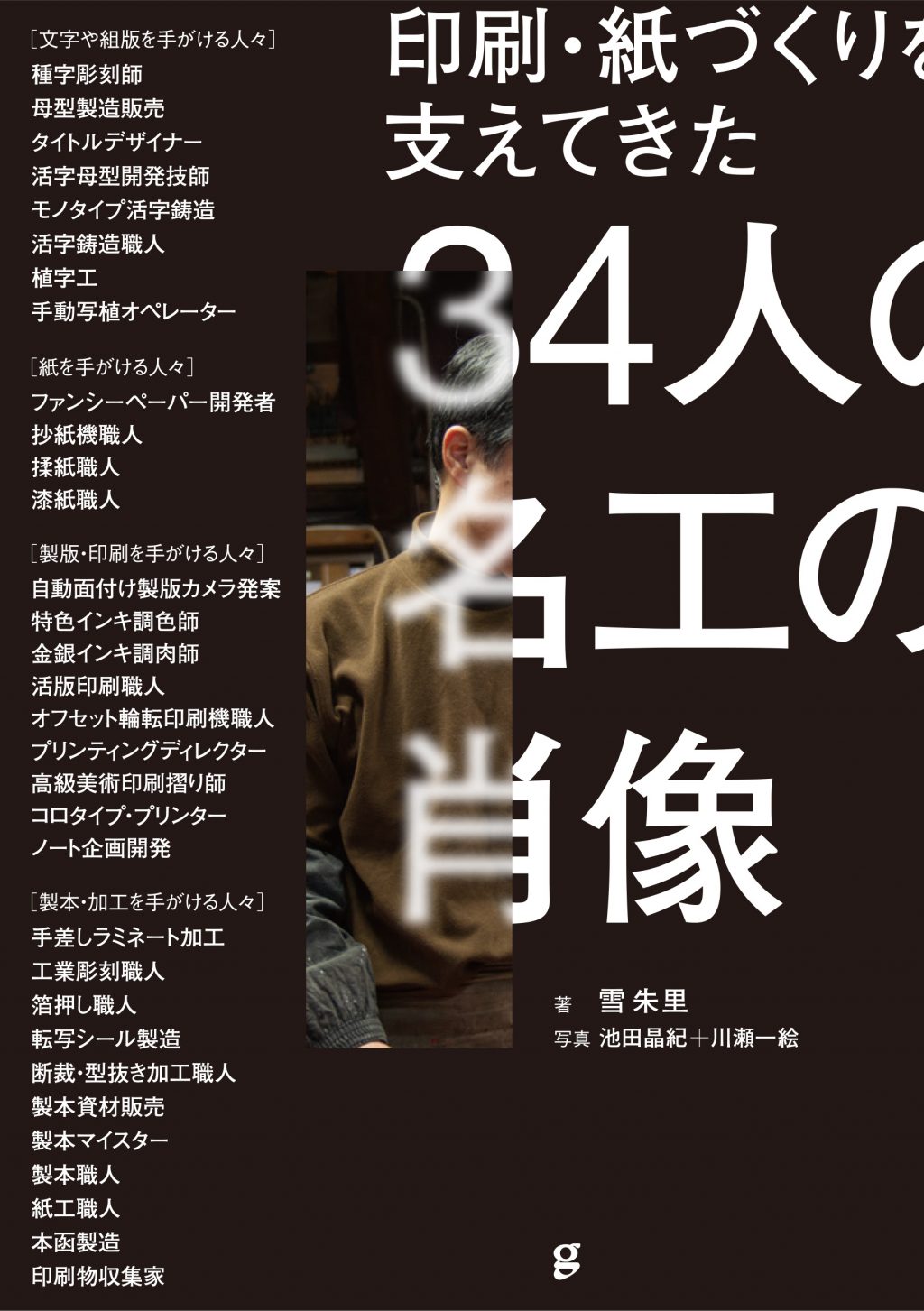





[注]
※本項はおもに、細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)をもとに執筆