昭和22年(1947)――太平洋戦争敗戦からの復興を目指し、日本の各業界が奔走していた時期、三省堂の専務・今井直一は、おおきな決断をした。それまでは門外不出として、自社の社員にすら関係者以外には非公開としていたベントン彫刻機の「公開」である。大日本印刷と協力し、ベントン彫刻機の国産機をつくることを決めたのだ。
三省堂のベントン彫刻機は、アメリカン・タイプ・ファウンダース(ATF)から輸入したものだ。戦前、日本国内でベントン彫刻機を所有していたのは、印刷局、凸版印刷(もとは東京築地活版製造所にあったもの)、そして三省堂だけであり、このうち印刷局のベントン彫刻機は大正12年(1923)9月の関東大震災で焼失してしまっていた。「ベントン彫刻機を有しているがゆえに、三省堂の印刷物はうつくしい」とまでいわれるほど、出版・印刷界で三省堂の存在感をおおきくした理由のひとつが、ベントン彫刻機の存在だった。
しかも、本連載第13回「寅雄、欧米視察に行く」でものべたとおり、アメリカを訪れて「機械を売ってほしい」と言う三省堂・亀井寅雄にたいしベントン彫刻機の開発者であるATFのリン・ボイド・ベントンがしぶった際、寅雄は「三省堂は出版社であって活字販売会社ではないから、機械を複製して売ったりしない」と言ってベントンを説得し、入手した。大事に守りぬいてきたその機械を、公開すると決めたのである。
終戦後印刷界つまり活版印刷の復興に際して、戦前先駆して導入した三省堂のベントン彫刻機を国産化して業界のために公開して印刷界の復興発展のために、(中略)製作を依頼することに、三省堂としての方針が決まった。1947年(昭和22年)のことであった。終戦が20年であるから、印刷業界ばかりでなく、まさに国家的復興の時期であった。
細谷敏治ノート「焼結法によるパンチ母型 1」(2008年ごろ執筆)
三省堂でのちに書体設計をつとめた杉本幸治も、この「公開」について〈あれは当時専務の今井さんが「印刷業界の復興のために、戦前よりもっと良い活字をつくらないと、活字・印刷部門の復興はもとより発展がない」という観点から、おもいきって公開したのです〉と語っている。[注1]
しかし、細谷ノートには「戦後の復興のため」と書いたものの、細谷の本音はちがったようだ。筆者が細谷に取材した際、彼はこんなふうに語っていた。
「今井さんが、大日本印刷とベントン彫刻機をつくることを約束したらしいんです。しかし三省堂にとって、ベントン彫刻機をもっているということが、その存在価値のおおきな理由だった。とても大事なものなのに、それを公開して国産でつくるようになったら、三省堂は何年ももたないでしょう、とぼくは大反対したんです。今井さんは、何年にもわたり、ベントン彫刻機は大事なもので、絶対に門外不出だと言いつづけてきた。それを、公開することにした。最後まで教えてくれませんでしたが、今井さんと大日本印刷とのあいだで、なにか特別な、秘密の約束をかわしたにちがいないと想像しています」[注2]
その「秘密の約束」の相手である大日本印刷では、なぜ「ベントン彫刻機の国産化」にとりくむことになったのか。それは昭和21年(1946)11月、同社に「活字地金、活字母型、活字鋳造機及び活字類に関する研究改良対策委員会」が発足したことからはじまる。この委員会は、〈敗戦の混迷の中から立上がろうとする意図の一つの芽として生まれた〉ものだ。[注3]
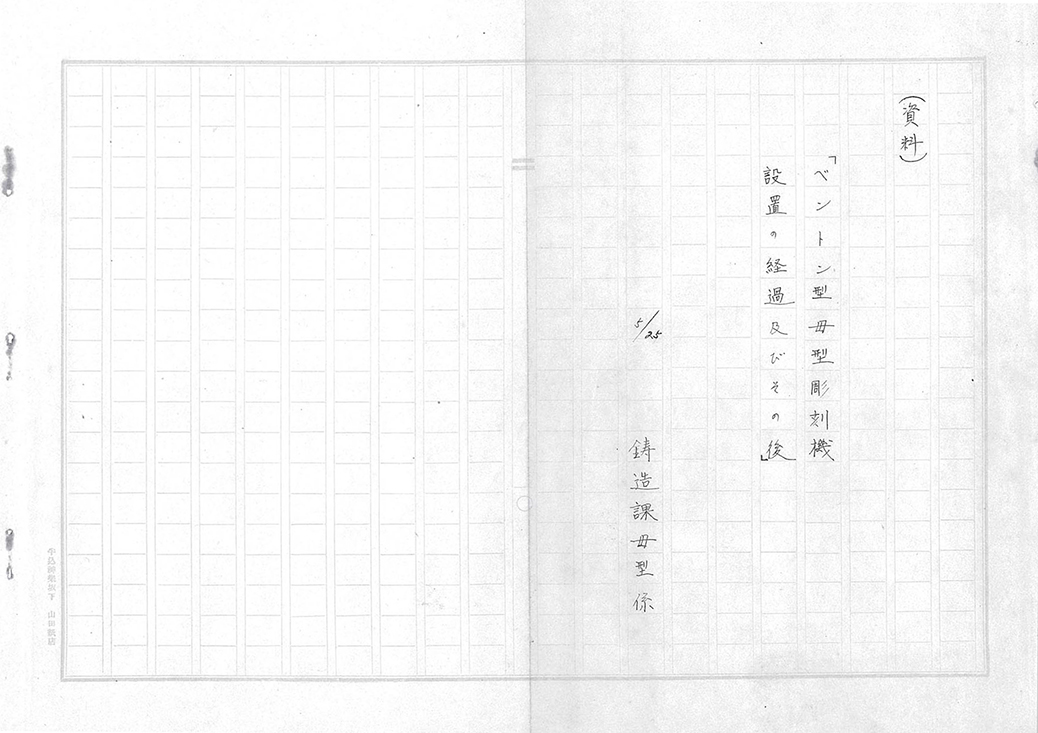
大住欣一「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」表紙(大日本印刷、1951)
この時期、大日本印刷の活字の製造、管理はおおきな危機にひんしていた。同社の活字は当時、おおくの母型製造会社や印刷会社がそうであったように、彫刻師が原寸大に手彫りした種字から製作する「電胎母型」からつくられていた。しかし戦前から戦後にかけて「種字彫刻師」は次第に減り、それ以前にくらべると、腕前も落ちて、彫刻師不足が浮き彫りになっていた。種字彫刻師は一人前になるまでに何年もかかる。修行中の若者たちが徴兵されたことが、彫刻師不足に影響をおよぼした。
さらに大日本印刷では、それまで使用してきた活字母型のほとんどが傷みがはげしく、高低がそろっていないという問題もかかえていた。しかし戦後、それを修理できる字母工(活字母型師)も不足した。同社活版課の浅野吉雄は、当時をふりかえり〈戦后の一、二年間は各活字とも惨憺たる状態でありました〉と書いている。[注4]
大日本印刷は明治9年(1876)10月9日、秀英舎として創業した印刷会社だ。昭和10年(1935)に日清印刷と合併し、大日本印刷と改称した。秀英舎時代にルーツをもつ大日本印刷のオリジナル書体「秀英体」は、東京築地活版製造所の「築地体」とともに、日本の明朝体の二大潮流といわれてきた伝統書体である。その母型や活字の大半が危機にひんしつつある状態を憂いた「活字地金、活字母型、活字鋳造機及び活字類に関する研究改良対策委員会」は、解決策をさがしていた。おおきなヒントをもたらしたのが、昭和22年(1947)2月の三省堂・今井直一の来社である。[注5]
大日本印刷は、三省堂・今井から同社におけるベントン彫刻機の使用状況を聞き、三省堂の活字をよく調べる機会を得た。三省堂はかつて、ベントン彫刻機のみならず、自社の活字でさえ門外不出としていたので[注6]、このとき今井にはすでに、公開に向けたある種の決意があったのかもしれない。
今井の来社を経て、大日本印刷「活字地金、活字母型、活字鋳造機及び活字類に関する研究改良対策委員会」は、ベントン彫刻機こそが自分たちがかかえる「母型精度および書体・彫刻者不足問題」の解決手段となりうるものなのではないか、とかんがえた。ただちに同社・片山技師長のもと、ベントン彫刻機設置の可能性と、その他の具体策が検討された。[注7]
まずは三省堂の協力を得なくてはならない。大日本印刷は三省堂の許可を得て、ベントン彫刻機の国産機製作への第一歩をふみだした。
(つづく)
[参考文献]
- 大日本印刷 鋳造課母型係・大住欣一 記「ベントン型母型彫刻機設置の経過及びその後」(社内資料/1951年5月25日)
- 朗文堂/組版工学研究会 編集・制作『杉本幸治 本明朝を語る』(リョービイマジクス発行、2008)
- 片塩二朗『秀英体研究』(大日本印刷、2004)


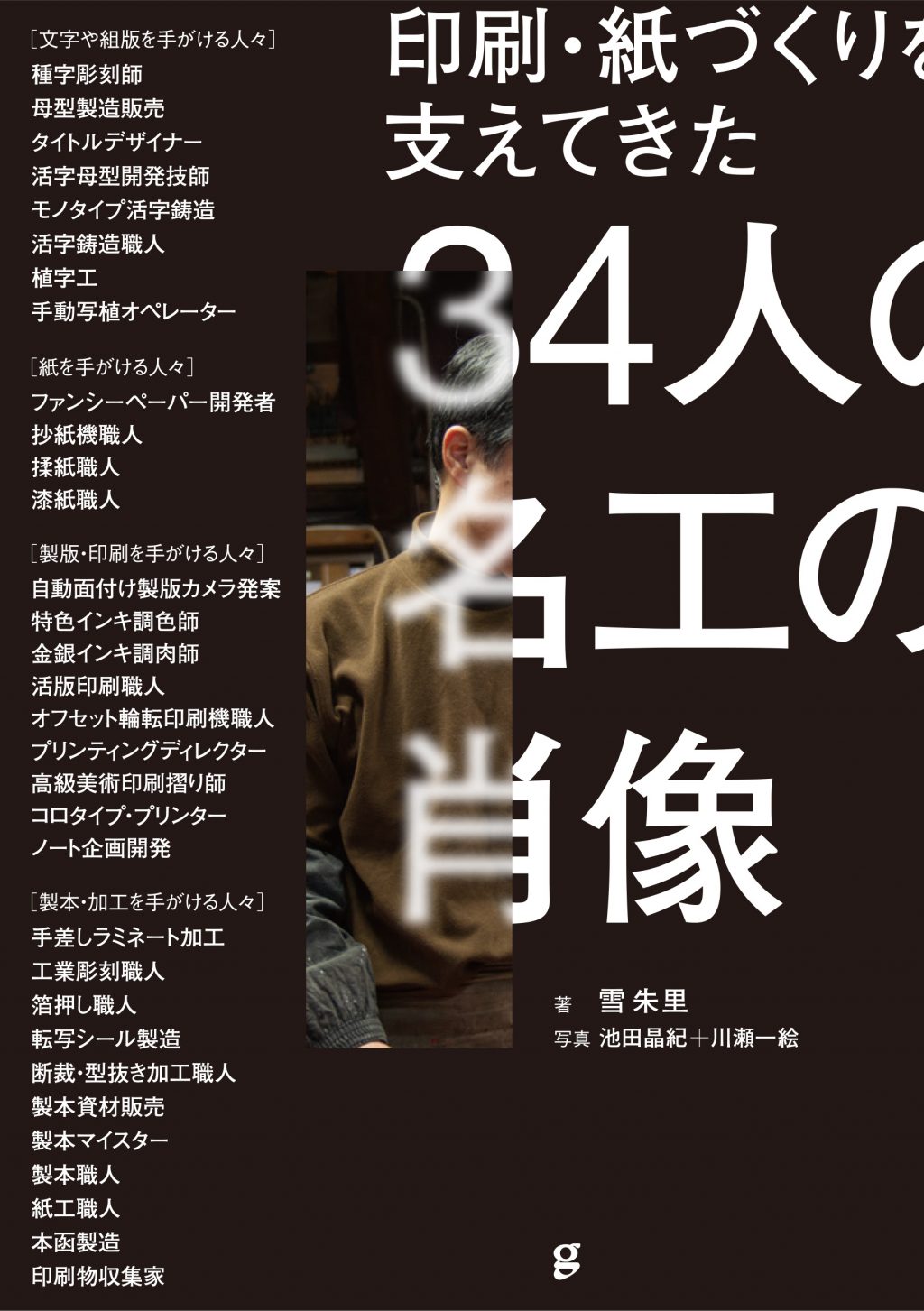





[注]
※片塩二朗『秀英体研究』(大日本印刷、2004)に所収