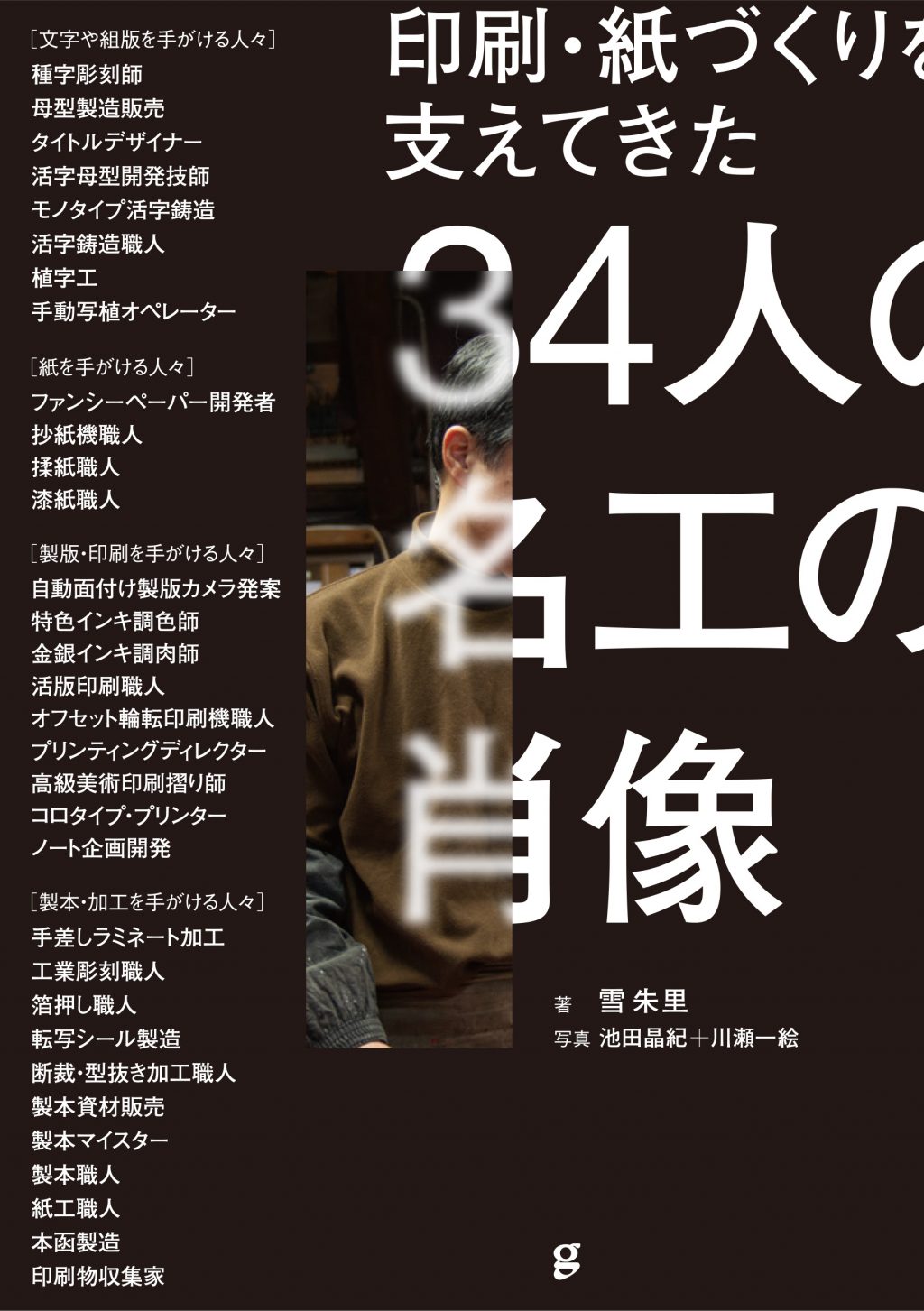三省堂の初号活字(三省堂印刷所蔵、2018年撮影)
「活字は、かつてそのおおもととなる種字を職人が原寸・左右逆字で1本ずつ彫刻していた。終戦後の1948年(昭和23)、津上製作所により国産ベントン彫刻機が開発され、機械による母型彫刻が普及していった」
活字の歴史を調べると、たいていこうした記述に出会った。私自身、手彫りの種字から母型をつくっていたものが機械化され、効率よく生産されるようになったのだとおもっていた。しかし国産ベントン彫刻機の開発・普及があたえた影響は、単に「活版工程の機械化」ということではないのではないか。そうおもいはじめたことが、本連載のきっかけとなった。
年表では「国産ベントン彫刻機開発」という1行で済まされていたことのなかに、どれだけのひとびとのつながりと奔走があったのか。それに気づくきっかけをくれたのは、もと三省堂で書体設計を手がけていた杉本幸治さんとの出会いだった。2009年、書体デザインについてインタビューする機会にめぐまれたのだ。三省堂時代の仕事について聞くなかで、杉本さんは、「参考に」と一部のコピー資料を渡してくれた。「昭和三十年十月調製 三省堂歴史資料(二)」と表紙に書かれた、もとはガリ版刷りだったとおもわれる資料だった。そこには、のちに社史『三省堂の百年』(三省堂、1982)に収録される亀井寅雄「三省堂の印刷工場」、今井直一「蒲田工場の建設」「我が社の活字」がおさめられ、同社がいかにしてアメリカでベントン彫刻機を入手したのか、それを使いこなすための苦労などがつづられていた。
さらに2013年、知人の紹介で、三省堂で母型彫刻にたずさわったのち、日本語パンチ母型の開発に成功して独立した細谷敏治さんに会う機会にめぐまれた。細谷さんは、

ベントン彫刻機で製作した三省堂の彫刻母型(三省堂印刷所蔵、2018年撮影)
杉本幸治さんからのガリ版刷りの社内史料、細谷敏治さんの手書きのノート、そして社史『三省堂の百年』。これらをあわせて読み、「辞書」という大量の活字が必要とされる現場で、うつくしい活字を印刷するために奔走したひとびとのことを知った。もと毎日新聞社の小塚昌彦さんと鈴木秀男さん、大日本印刷の小野秀さん、岩田母型製造所の髙内一さんなど、当時のことを知るかたにお話を聞き、当時のことが書かれた書籍や、『印刷雑誌』などの記事を読むにつれ、だんだんと、ベントン彫刻機の導入によって「書体設計」「書体デザイン」という概念が生まれたことが見えてきた。
杉本幸治さんは2011年、細谷敏治さんは2016年に亡くなっていた。おふたりに託されたというおもいもあった。三省堂とベントン彫刻機にまつわる現場とひとびとのことをどうしても書きたいとかんがえ、三省堂をたずねたのが2017年秋のことだ。かくして準備期間を経て、2018年8月から、本連載をスタートすることができた。
*
快くこの連載の場を提供くださった三省堂の方々に、最後にあらためて御礼申し上げます。数年にわたり私が胸のなかでくすぶらせていた「このテーマで書きたい」という思いを受けとめ、調査に協力し、伴走してくださいました。そして、約2年のあいだお読みくださった読者の方々にも、心から御礼申し上げます。SNSなどを通じて鋭い質問をいくつもいただき、それもまた、筆を進める際の貴重な助言となりました。ありがとうございました。
そして最後に、お知らせがあります。本連載が来年、三省堂より書籍として刊行されることになりました。書籍化にあたっては、連載を進めるなかであらたにわかったことを加筆し、また、三省堂の文字づくりにたずさわった人のことなど、書き下ろしも加える予定です。
来年また、みなさまに晴れ晴れとしたご報告ができるよう、準備を進めてまいります。楽しみにお待ちいただければ幸いです。