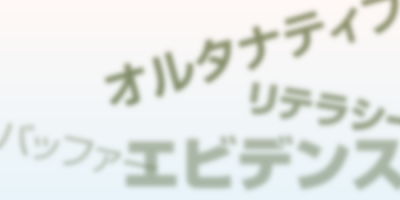山崎豊子の『白い巨塔』に登場する業者・野村は、佐々木商店が繁盛していた時と、店主が死に店が傾いてきた今とで、振る舞いがすっかり違う。「昔は揉み手をして、あんなに腰を低くして出入りしていたではないか」となじられても、「そりゃ、あの時はあの時。今は今」といった感じで平然としている。
「ずいぶんな口のききようだな。おまえ、いつからそんなに偉くなった。『下位者』キャラだったくせに」と、出し抜かれる者は、出し抜く者のキャラクタの変化を言い立てる。これまで述べてきたように、キャラクタが変わることは、遊びの場合を別とすればみっともないことである。
「あれは、あなたにお世話になっていたから『下位者』のスタイルで接していたのだ。いまは、もはやあなたの世話にはなっていない。だから『下位者』のスタイルでは接しない。自分は状況の変化に応じて『スタイル』を変えただけ」と、出し抜く者はスタイルの変化と片付けたがる。野村の「平然」を支えている考えがあるとすれば、こういうものだろう。
目上の相手に対してしゃべる場合には、目上へのしゃべり方というものがあり、目下の相手に対してしゃべる場合にもやはり、目下へのしゃべり方というものがある――まさにその通りである。だが、目上相手と目下相手でしゃべり方を切り替える時、それがスタイルの変化にとどまることはむしろ珍しく、そこにはしばしば、人間(キャラクタ)の変化が含まれている。
とはいえ、それをどこまではっきりと認めるかは微妙な問題である。
たとえばお客にとってみれば、商人の深々としたお辞儀が自分の財布に頭を下げているだけであり、[いまこの人はお客として自分に金を払おうとしている]という状況に対応してコントロールされたものにすぎないと考えることは楽しいことではない。「人間としての敬意」などと言えば大げさになってしまうが、そこに何かしら状況を越えスタイルを越えたものを期待してしまいがちである。しかし、いちど下手(したて)に出たからといって、お客が破産しても、こちらが廃業しても、おまえは生涯『下』だと決めてかかられたら、野村でなくても、なかなか我慢ならないだろう。
無論、野村は『白い巨塔』では悪役として、共感しにくく描かれている。だが、野村の行動原理そのものは私たちにとって遠いものではない。「日本と違って欧米では店と客は対等な関係で……」といった(誇張・美化された)話を肯定的に受け取る人、「ジョギングしてたら、バイト先の客に会って、思わずニッコリして愛想言っちゃった。なんか腹立つなあ。ジョギングのコース変えよかなあ」といった若者のぼやきに少しでも共感できる人には、特にそうではないだろうか。